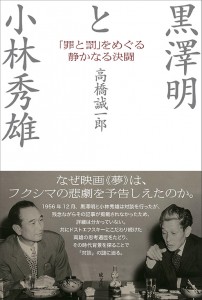『風の谷のナウシカ』(1984)における圧倒的な存在感のある「腐海の森」のテーマは、「高度に進んだ科学と自然」との関係を問いただすものでした。この映画では夢の中でナウシカが子供の頃に戻って、「王蟲」の子供が殺されそうになっているのを見て「殺さないで」と叫ぶのを再び見るシーンが描かれています。
このシーンを見て連想したのは、近代西欧の「弱肉強食の思想」から強い影響を受けた『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが「非凡人の理論」を編み出して、「悪人」と規定した「高利貸しの老婆」を殺害しようと計画を練りはじめた頃に見た「やせ馬が殺される夢」のことでした。そこでも夢の中で子供に戻った主人公は、やせ馬を「殺さないで」と叫んでいたのです。『罪と罰』のエピローグでラスコーリニコフは「人類滅亡の悪夢」を見て、その夢がきっかけとなり「非凡人の思想」の危険性を理解するようになることが示唆されています。
一方、『風の谷のナウシカ』の最期のシーンでナウシカは「怒り」のために走り出した王蟲の群れによって「風の谷」の住民が全滅しようとするところに、自分の身を顧みずに自分が助けた「王蟲の子供」とともに降り立つという献身的な行動をとるのです。
(《風の谷のナウシカ》、図版は「Facebook」より)。
宮崎駿はこのシーンに、「国家」のために「特攻」することで「神」となるような「美しい物語」とは異なり、深い傷を負ったナウシカが王蟲たちによって癒され、復活するという『罪と罰』のエピローグ的な構造を与えています。(『罪と罰』の場合は肉体的な傷ではなく精神的な傷ですが、それでも致命傷に近い精神的な傷から長い時間をかけて蘇ることになるのです)。
『天空の城ラピュタ』には『風の谷のナウシカ』で描かれていた「腐海の森」は欠けていますが、その代わりに徐々に「生命の樹」のテーマが姿を現してくることになります。
龍の巣と呼ばれる嵐を乗り越えてラピュタに上陸した主人公のパズーとシータが、灌木をかき分けていくと中央にそびえる天まで届くような巨木に出会います。それでも最初のうちは「生命の樹」のテーマはパズーが必死で掴まる根っこの形で示されるに過ぎません。
しかし、自分以外の者を「バカども」と見下すムスカが「王族しか入れない聖域」にまで入り込んでいた木の根を見て「一段落したら全て焼き払ってやる」と語るところから「科学と自然」と「非凡人と凡人」のテーマが明確に現れてきます。
たとえば、「素晴らしい! 700年もの間、王の帰りを待っていたのだ!」と語ったムスカはその一方で、「素晴らしい!!最高のショーだとは思わんかね」と問いかけ、ラピュタから落ちていく兵士たちを見ながら「あっはっは、見ろ。人がゴミのようだ」と楽しそうに語るのです。
さらに、「これから王国の復活を祝って、諸君にラピュタの力を見せてやろう」とし、旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の火」である「ラピュタの雷(いかずち)」を見せて、「全世界は再びラピュタの元にひれ伏すことになるだろう!」と語ります。
すると、恐怖心から「すばらしい、ムスカ君。君は英雄だ。大変な功績だ」と急に態度を一転させた将軍に対しても「君のアホづらには、心底うんざりさせられる」と続けたのです。
このようなムスカの言葉は、「凡人」について、「服従するのが好きな人たちです。ぼくに言わせれば、彼らは服従するのが義務で」と規定していた『罪と罰』のラスコーリニコフの言葉を想起させます(三・五)。しかも彼も自分の望みを「ふるえおののくいっさいのやからと、この蟻塚(ありづか)の全体を支配することだ!」とも語っていました(四・四)。
創作ノートにはラスコーリニコフには「人間どもに対する深い侮蔑感があった」(一四〇)と書かれています。ドストエフスキーはラスコーリニコフに、自分の「権力志向」だけではなく、大衆の「服従志向」にも言及させることでラスコーリニコフのいらだちを見事に表現しえているのです。
一方、フランス文学者の鹿島茂氏は小林秀雄がランボーを「人生斫断家(しゃくだんか)」と定義していたことに注目して、「斫断」というのは辞書にはないので「同じ意味の漢字を並べて意味を強調する」ための造語で、「いきなりぶった切る」という意味を出したかったのではないかと記しています。
そして鹿島氏は、「昭和維新」を熱心に論じあい、「斎藤実や高橋是清を惨殺した二・二六の将校」と、小林が「その深層心理ないしは無意識において」は、「それほどには違っていなかったのではあるまいか?」と推定しています。きわめて大胆な仮定ですが、「いきなりぶった切る」という意味の「斫断」という単語は、「一思いに打ちこわす、それだけの話さ」と語り、「いやなによりも権力だ!」と続けていたラスコーリニコフの言葉を想起させるのです。

小林秀雄が1940年に書いた『我が闘争』の短評でヒトラーの思想を賛美したことも鹿島説の正しさを示していると思えます。こうして、青年将校たちが「昭和維新」を熱心に論じあっていた頃に書かれた小林秀雄の『罪と罰』論は、若者たちに強い影響を及ぼしました。たとえば、ドストエフスキーの作品論をとおして「大東亜戦争を、西欧的近代の超克への聖戦」と主張した堀場正夫は、著書『英雄と祭典 ドストエフスキイ論』(白馬書房、昭和一七年)の「序にかえて」で日中戦争の発端となった盧溝橋事件を賛美しました。そして、「今では隔世の感があるのだが、昭和十二年七月のあの歴史的な日を迎える直前の低調な散文的平和時代は、青年にとつて実に忌むべき悪夢時代であった」と記して、それまでの平和な時代を罵っていたのです。
しかし、『罪と罰』の中心的なテーマである「良心」の問題などは無視して、「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」とし、エピローグは「半分は読者の為に書かれた」と解釈した小林秀雄の評論は、自分に引き付けた原作とは正反対のテキスト解釈でした。
その解釈には――1,作品の人物体系や構造を軽視し、自分の主観でテキストを解釈する。 2,自分の主張にあわないテキストは「排除」し、それに対する批判は「無視」する。 3,不都合な記述は「改竄」、あるいは「隠蔽」する――などの特徴があります。
しかし、権力者によって都合がよかったためにその評論は戦後も影響力を保って、「評論の神様」と奉られるようになったことになった小林秀雄は、1960年の「ヒットラーと悪魔」でも大衆の軽蔑と「プロパガンダ」の効用に注目しながら再び『我が闘争』について詳しく論じました。
作家の坂口安吾は小林秀雄のことを「教祖」と呼びましたが、小林はヒットラーと悪魔」を書いた翌年からは「日本会議」などで代表委員を務めることになる小田村寅二郎に招かれて「全国学生青年合宿所」と銘打たれた研修会で本居宣長などについて5回も講演を行い、それらの講演の後では青年たちとも「対話」も行われていたので、そこからは「日本会議」系の論客も育っていました。
しかし、邦訳を行った内田魯庵ばかりでなく、北村透谷や島崎藤村など明治の文学者たちは特定の個人に焦点を当てて解釈するのではなく、登場人物の人物体系や全体的な筋の流れを踏まえて『罪と罰』を精緻に分析していました。
明治の文学者たちと同じように宮崎駿のアニメを読み解く際にも、登場人物の人物体系や全体的な筋の流れを踏まえて鑑賞することが必要だと思えます。
『天空の城ラピュタ』では、パズーが「このままではムスカが王になってしまう。…略奪より、もっとひどいことが始まるよ!」と語って「非凡人の思想」を厳しく批判すると、「飛行石を取り戻したって、わたしどうしたらよいか」と悩んだシータが思い出したのが「滅びの呪文」だったのです。
そして、ムスカに「国が滅びたのに、王だけ生きてるなんて滑稽だわ」と告げたシータは、「ラピュタがなぜ滅びたのかあたしよく分かる。ゴンドアの谷の歌にあるもの。 『土に根をおろし、風と共に生きよう(中略)』 どんなに恐ろしい武器を持っても、沢山のかわいそうなロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ!」と続けています。
小林秀雄の『罪と罰』論の手法は、安倍政権による国会の議論の手法や公文書の改竄と隠蔽にも共通していると思えますが、「ラピュタのいかずち」による巨大な雲の形は明らかに原水爆の非人道性を示しています。
二度の原爆投下だけでなく水爆実験の被害にもあったにもかかわらず、身内の者のみを優遇していまだに「核兵器禁止条約」の批准も拒み、原発の推進を行っている政治家たちの前近代な「道徳」観や「公共」観の危険性を『天空の城ラピュタ』は、30年以上も前に予告していたと言えるでしょう。
こうして、科学技術の過信や「最終兵器」が世界を滅ぼすという『風の谷のナウシカ』から一貫して描かれているテーマとともに、「非凡人の思想」や独裁者の危険性が『天空の城ラピュタ』ではより明確に描写されることで、愛する地球を守るために、自分たちの生命をも危険にさらしてパズーとシータが声をそろえて「バルス!」と叫ぶシーンが感動を呼ぶのです。
一方、このアニメでは「天空の城ラピュタ」が崩壊したかに見えた後で、圧倒的な姿を現すのが「生命の樹」のテーマです。巨木の根で覆われたラピュタは、基底の高度な文明の部分が崩れ落ちたあとも、完全に崩壊することはなく、上部の美しい森や公園を残したまま、天空へと上昇していくのです。
こうしてこのアニメ『天空の城ラピュタ』は、すぐれた民話と同じように分かり易い映像で子供たちに普遍的で大切な英知を伝えているのだと思います。
→『天空の城ラピュタ』の理解と主観的な文学解釈(1、改訂版)テーマの継承と発展――『風の谷のナウシカ』から『天空の城ラピュタ』へ(+「目次」)





 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)
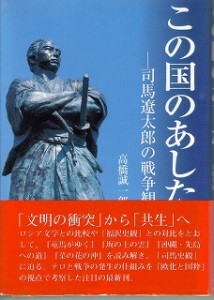
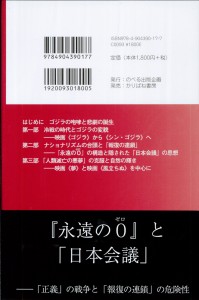








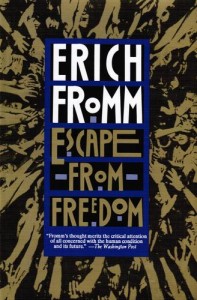









 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)