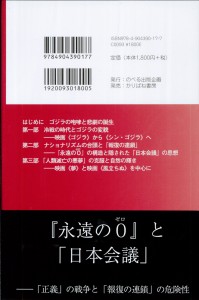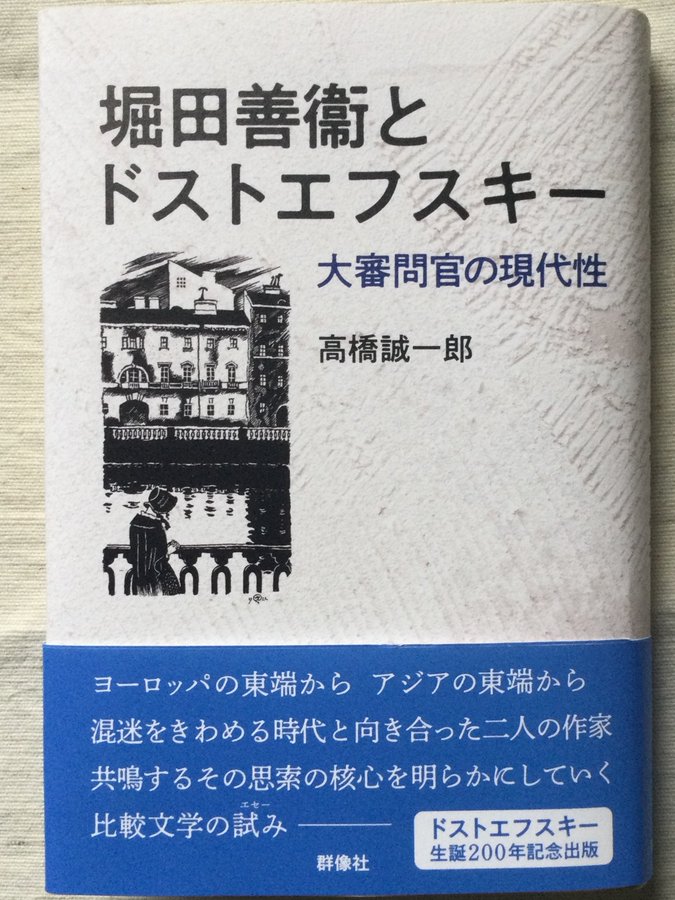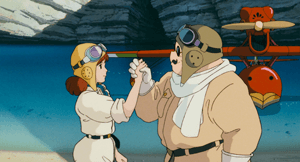はじめに
太平洋戦争における「特攻」につながる「自殺戦術」の問題点と「大和魂」の絶対化の危険性を鋭く指摘した長編小説『坂の上の雲』と子規や漱石の作品との関係については、昨日、拙著の該当部分(第5章第4節)をアップしました。
→『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』第5章より、第4節〈虫のように、埋め草になって――「国民」から「臣民」へ〉
しかし、「政治的・時代的な意図」によってこの長編小説を解釈した大河ドラマ《坂の上の雲》が三年間にわたって放映されたことで、著者の司馬遼太郎だけでなく正岡子規や夏目漱石への誤解も広がっているようです。
『坂の上の雲』を「なるべく映画とかテレビとか、そういう視覚的なものに翻訳されたくない作品」であると作者の司馬が記していた(『「昭和」という国家』、NHK出版、一九九八年)作品を、大河ドラマとして放映したことの問題については、既にブログ記事で論じていました。
→改竄(ざん)された長編小説『坂の上の雲』――大河ドラマ《坂の上の雲》と「特定秘密保護法」
それを書いた時点では私がまだ俳人・正岡子規にあまり詳しくなかったために、漱石と子規の妹律の発言をめぐる問題点にはふれていませんでした。ツイッターでは大河ドラマ《坂の上の雲》の最終回で描かれた創作されたエピソードについて考察しましたが、字数の関係で抜かした箇所などがありましたので、今回はその箇所や子規の新体詩や島崎藤村との関係、さらに新聞『日本』にトルストイの『復活』が載っていたことなどを補った追加版をアップします。
* * *
ヤフーの「知恵袋」というネット上の質問コーナーには、2012年2月に「司馬遼太郎と夏目漱石」という題で次のような質問が載っていました。
「昨年NHKでやっていた『坂の上の雲』の最終回で、夏目漱石役の人が『大和魂』を茶化すような発言をして正岡子規の妹役に諌められ、『すみません』といって謝っていたのですが、あそこのところは原作にもあるんでしょうか?どのような意図が込められているんでしょうか?
夏目漱石といえば近代日本の批判者というイメージですが、『坂の上の雲』や一般に司馬遼太郎その人にとって、漱石はどういう位置づけというか、どういう存在だったのでしょうか。」
この質問に対するベストアンサーには次のような回答が選ばれていました。
「確か原作にはなかったと思います。漱石はその著書『こころ』で、明治天皇の崩御と乃木将軍の殉死を悼み、『明治という時代が終わった。』と登場人物の『先生』に言わせていたと思います。 確か「坊ちゃん」だったと思いますが(引用者註――『三四郎』)、日露戦争後の日本について「日本は滅びるね。」と登場人物に言わせています。
そこら辺の機微をNHKが創作したものだと推測します。『坂の上の雲』では、漱石は子規のベストフレンド(文学的にも)という位置づけだったように思います。」
* * *
回答者の「確か原作にはなかったと思います」という指摘は正確なのですが、「夏目漱石役の人が『大和魂』を茶化すような発言をして正岡子規の妹役に諌められ、『すみません』といって謝っていた」というシーンについて回答者は、「NHKが創作した」と解釈することは、子規への誤解を広めることになるでしょう。
この場面は「大和魂(やまとだましい)! と叫んで日本人が肺病みの様な咳をした」という文章で始まる新体詩を主人公の苦沙弥先生が朗読するという『吾輩は猫である』の場面を受けて創作されていたと思えます。
しかし、漱石が主人公にこのような新体詩を読ませたのは、盟友・子規が「大和魂」を絶対化することの危険性を記していたことを思い起こしていたためだと思えます。
俳人・子規は、日清戦争に従軍した際に創作した「金州城」と題された新体詩で、杜甫の詩を下敷きに「わがすめらぎの春四月、/金州城に来て見れば、/いくさのあとの家荒れて、/杏の花ぞさかりなる。」と詠んでいました。さらに子規は「髑髏」という新体詩では「三崎の山を打ち越えて/いくさの跡をとめくれば、此処も彼処も紫に/菫花咲く野のされこうべ。」と詠んでいたのです。
評論家の末延芳晴氏が『正岡子規、従軍す』(平凡社、二〇一〇年)で指摘しているように、子規の従軍新体詩が「反戦詩」へとつながる可能性さえあったのです。
新聞記者としても活躍していた子規は、事実を直視する「写生」の大切さを訴え、政府の言論弾圧も批判していたことだけでなく、後に『破戒』を書くことになる島崎藤村との対談で話題となっていたように短編『花枕』などの小説を書き、ユゴーの『レ・ミゼラブル』の部分訳をも試みていました。
日露戦争の最中に新聞『日本』がトルストイの反戦的な小説『復活』を内田魯庵の訳で連載していたことも考慮するならば(拙著『新聞への思い』、191~192頁)、子規がもし健康で長生きをしたら漱石にも劣らない長編小説を書いていたかもしれないとさえ私は考えています。
なお、回答者は「漱石はその著書『こころ』で、明治天皇の崩御と乃木将軍の殉死を悼み、『明治という時代が終わった。』と登場人物の『先生』に言わせていたと思います」とも記していました。
夏目漱石の乃木観の問題は、乃木大将の殉死をテーマとした司馬遼太郎の『殉死』でも記されていますので、この問題については現在、執筆中の『絶望との対峙――憲法の発布から「鬼胎」の時代へ』(仮題)で詳しく考察したいと考えています。
* * *
NHKは大河ドラマ《坂の上の雲》を三年間にわたって放映しばかりでなく、その間には政商・岩崎弥太郎を語り手として幕末の志士・坂本竜馬の波乱の生涯を描いた《龍馬伝》も放映していました。
うろ覚えな記憶ですがこの大河ドラマの脚本家は、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』から強い影響を受けたことに感謝しつつ、それを踏まえて新しい『龍馬伝』を書きたいとの心意気を語っていました。
しかし、この大河ドラマでは、「むしろ旗」を掲げて「尊王攘夷」を叫んでいた幕末の「過激派」の人々が美しく描き出されており、結果としては『竜馬がゆく』で描かれた「思想家」としての竜馬像を否定するような作品になっていたと言わねばなりません。
さらに2015年には吉田松陰の妹・文を主人公とした大河ドラマ《花燃ゆ》が放映されましたが、文が再婚した相手の小田村伊之助こそは、山崎氏雅弘が指摘しているように「日本を蝕(むしば)む『憲法三原則』国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という虚妄をいつまで後生大事にしているのか」というタイトルの記事を寄稿していた小田村四郎・日本会議副会長の曽祖父だったのです(『日本会議 戦前回帰への情念』)。
このように見てくる時、莫大な予算をかけて製作されているNHKの大河ドラマ大河ドラマ《坂の上の雲》、《龍馬伝》、《花燃ゆ》などが安倍自民党のイデオロギーの宣伝となっていることが分かります。
本来ならば、自民党の広報が製作すべきこれらの番組の製作費が、国民からなかば強制的に徴収されている視聴料によってまかなわれていることはきわめて問題であり、これから国会などでも追究されるべきだと思います。