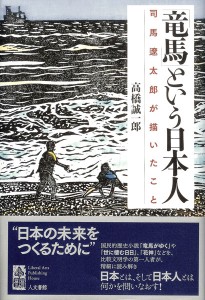Ⅰ、「物質への情熱」――小林秀雄の正岡子規論
小林秀雄に正岡子規の「歌よみに与ふる書」を論じたエッセイ「物質への情熱」があります(『小林秀雄全集』第一巻)。
この冒頭で「正岡子規に『歌よみに与ふる書』といふ文章がある事は誰でも知つてゐる。そのかたくなに、生ま生ましい、強靱な調子を、私は大変愛するのだが」と記した小林秀雄は、「読んでゐて、病床に切歯する彼の姿と、へろへろ歌よみ共の顔とが、並んで髣髴と浮んで来るには少々参るのだ」と続けていました。
さらに、「惟ふに正岡子規は、日本詩人稀れにみる論理的な実証的な精神を持つた天才であつた」と記した小林秀雄は、「どんな大きな情熱も情熱のない人を動かす事は出来ないのかも知れない。子規の言葉は理論ではない、発音された言語である」との理解を示していました。
ただ、このエッセイに戸惑いを覚えたのは、冒頭近くで正岡子規の主張に対しては「到底歌よみ共には合点が行かぬと私は思ふ。少くとも子規が難詰したい歌よみ共には通じまいと思ふ」と書き、「『歌よみに与ふる書』は真実の語り難いのを嘆じた書状である。果して他人(ひと)を説得する事が出来るものであらうか」とも記した小林が次のように続けていたことです。
「詩人は美しいものを歌ふ楽な人種ではない。在るものはたゞ現実だけで、現実に肉薄する為に美しさを頼りとしなければならぬのが詩人である。女に肉薄するのに惚れるといふ事を頼りにするのが絶対に必要な様なものである」。
Ⅱ、「歌よみに与ふる書」と『坂の上の雲』
正岡子規が新聞『日本』に掲載した「歌よみに与ふる書」については、司馬氏も長編小説『坂の上の雲』でふれています。私はこの箇所こそが『坂の上の雲』の中核となっていると考えています。
リンク→子規の「歌よみに与ふる書」と真之――「かきがら」を捨てるということ
なぜならば、『坂の上の雲』単行本の第4巻のあとがきでは、「当時の日本人というものの能力を考えてみたいというのがこの作品の主題だが、こういう主題ではやはり小説になりにくい」と記し、その理由としてこのような小説は「事実に拘束される」が、「官修の『日露戦史』においてすべて都合のわるいことは隠蔽」されていると記されています。このような「事実」の隠蔽に対する怒りが、膨大な時間をかけつつ自分で戦史を調べてこの長編小説を書かせていたのだと思えるのです。
一方、よく知られているように、小林秀雄は敗戦後の1946年に戦前の発言について問い質されると「僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか」と啖呵を切っていました。
しかし、1948年に行われた物理学者の湯川秀樹博士との対談では、「原子力エネルギー」を産み出した「高度に発達した技術」の問題を「道義心」の視点から厳しく指摘した小林は、原発の推進が「国策」となるとその危険性を「黙過」したのです。
それゆえ、俳人・正岡子規を中心に司馬氏の『坂の上の雲』を読み解こうとしていた私は、福島第一原子力発電所の大事故がまだ収束していないにもかかわらず、「アンダーコントロール」と宣言し、自然環境を軽視した政治が行われるようになった日本をみながら、「事実をきちんと見る」ためには「評論の神様とも言われる」文芸評論家・小林秀雄の方法をきちんと問い直さなければならないと痛感したのです。
Ⅲ、「好奇心に満ちた多様性」――寺田透の正岡子規観
注目したいのは、小林秀雄が正岡子規論に「物質への情熱」という題名を付けたことに強い違和感を記していた寺田透が、『子規全集』第二巻に「従軍発病とその前後」という題の「解説」を書き、そこで子規の「多様性」に注意を促していることです。
「明治二十七年の句を通読して驚嘆させられるのは、無論これは全部についても言へることだが、子規の多産であり、その病軀にもかかはらぬ健康であり、さらにこれが江戸時代の俳句と子規のそれを区別するもつとも明瞭なことだが、子規の好奇心に満ちた多様性といふことである。」
ここで言及されている明治27年には、日清戦争が勃発し、この翌年に子規は病身をおして従軍記者となるのですが、この時期についてはこのHPの「正岡子規・夏目漱石関連簡易年表」を引用することによって、この時期と子規との関連を簡単に説明しておきます。
* * *
「1894(明治27) 子規、2月、上根岸82番地(羯南宅東隣)へ転居。2月11日『「小日本』創刊、編集責任者となり、月給30円。小説「月の都」を創刊号より3月1日まで連載。3月 挿絵画家として浅井忠より中村不折を紹介される。5月、北村透谷の自殺についての記事を書く。7月、『小日本』廃刊により『日本』に戻る。7月29日、清国軍を攻撃。8月1日、清国に宣戦布告。9月黄海海戦で勝利、11月、旅順を占領。
1895(明治28) 子規、3月、日清戦争への従軍許可がおりる。4月10日、宇品出港、近衛連隊つき記者として金州・旅順をまわる。金州で従弟・藤野潔(古白)のピストル自殺を知る。「陣中日記」を『日本』に連載。5月4日、金州で森鴎外を訪問。17日、帰国途上船中で喀血。23日、県立神戸病院に入院、一時重態に陥る。7月23日、須磨保養院へ移る。8月20日、退院。8月27日、松山中学教員夏目金之助の下宿「愚陀仏庵」に移る。」
* * *
日本にとってばかりでなく、子規にとってもたいへんな年であったことが分かりますが、「たとへば次の新年の句二句すら、題材が富士であり筑波であるにもかかはらず、陳腐さより、時代の新しさを感じさせる」とし、〈ほのほの(原文ではくりかえし記号)と茜の中や今朝の不二〉と〈白し青し相生の筑波けさの春〉の二句を紹介した寺田は、こう記しています。
「これらの句からは、藩境などといふもののなくなつた国土を、自由に走つて行ける眼と心の喜びと言つたものが直覚されるといふことは言はずにゐられない。」
そして、子規が独身であるにも関わらず、〈古妻のいきたなしとや初鴉〉という「虚構」を記した句も書いていることを注目した寺田は、「この春には春雨の題で、〈春雨のわれまぼろしに近き身ぞ〉/深々として不気味な句を作者は作つた」ことを紹介して、「これも、誰もまだ作ることのできなかつた句だと言へよう」と子規の句の「多様性」に注意を促していました。
さらに、〈あちら向き古足袋さして居る妻よ〉という句を評して、「この明るさは、現実に縛られず、その上に別種の世界をくりひろげる空想のそれだといふことである」とも寺田は書いていました。
子規に関していろいろな著書を調べていた際に、最も刺激を受けた子規論の一つが「虚構」をも許容する子規の「多様性」を指摘した寺田透のこの「解説」だったのです。
「歌は事実をよまなければならない。その事実は写生でなければならない」との持論を展開した子規には、「虚構」をも許容する「多様性」があったという寺田の指摘は非常に重要だと思えます。
なぜならば、1908年に長編小説『春』で、北村透谷との友情やその死について描くことになる島崎藤村(1872~1943)は、北村透谷(1868~1894)の追悼記事を書いた可能性の高い子規と1897年に会って新聞『日本』への入社についての相談をしたばかりでなく、子規の小説『花枕』についての感想も述べていたのです。
子規が小説「曼珠沙華」で部落民に対する差別の問題をも描いていることを考えるならば、後に長編小説『破戒』を書くことになる藤村が子規と会っていたことの意味は大きいでしょう。
リンク→正岡子規と島崎藤村の出会い――「事実」を描く方法としての「虚構」
(2016年2月3日。〈「事実をよむ」ことと「虚構」という方法〉より改題し、大幅に改訂)
関連記事一覧
「陶酔といふ理解の形式」と隠蔽という方法――寺田透の小林秀雄観(2)