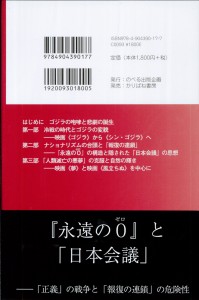昭和初期の暗く重い時期の若き詩人たちとの交友を描いた堀田善衛氏の自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』を読み返した時には、明治の『文学界』の同人たちとの交友を描いた島崎藤村の自伝的な長編小説『春』のことを思い起こしましたが、注目したいのは堀田氏が作家の司馬遼太郎氏やアニメ監督の宮崎駿氏との鼎談でこう語っていたことです。
「『この国』という言葉遣いは私は島崎藤村から学んだのですけど、藤村に一度だけ会ったことがある。あの人は、戦争をしている日本のことを『この国は、この国は』と言うんだ」(『時代の風音』朝日文庫、1997年、150頁)。
そのことに注目するならば、『若き日の詩人たちの肖像』が『夜明け前』を書いた島崎藤村の広い視野を強く意識して書かれていたことは確かでしょう。興味深いのは、鼎談者の一人の司馬遼太郎もまた『この国のかたち』と題したエッセー集の第5巻で平田篤胤の復古神道が「創造の機能には、産霊(むすび)という用語をつかい、キリスト教に似た天地創造の世界を展開した」と指摘していることです。
そして、「平田国学」が庄屋など「富める苗字(みょうじ)帯刀層にあたえた」影響を、「奈良朝の大陸文化の受容以来、篤胤によって別国が湧出したのである」と説明していました(太字は引用者)。
 (書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)
(書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)
「昭和初期」を「別国」あるいは、「異胎」の時代と呼んで批判していた司馬氏がここでも「別国」という独特の用語を用いていることは、昭和の「別国」と平田篤胤によってもたらされた「別国」との連続性を示唆していると思われます。
実は、『翔ぶが如く』を執筆中に著したエッセー「竜馬像の変遷」で、「人間は法のもとに平等である」というのが「明治の精神であるべき」で、「こういう思想を抱いていた人間がたしかにいたのに、のちの国権的政府によって、はるか彼方に押しやられてしまった」と記し、「結局、明治国家が八十年で滅んでくれたために、戦後社会のわれわれは明治国家の呪縛から解放された」と続けていたのです。
「王政復古」が宣言された一八六八年から敗戦の一九四五年までが、約八〇年であることを考えるならば、明治国家の賛美者とされることの多い司馬氏は、「明治国家」を昭和初期の敗戦まで続いた国家として捉えていたといえるでしょう。
しかも司馬氏は『竜馬がゆく』を執筆中の一九六四年には日中戦争の時に二五歳で戦死し、「軍神」とされた戦車隊の下士官・陸軍中尉西住小次郎についても、「明治このかた、大戦がおこるたびに、軍部は軍神をつくって、その像を陣頭にかかげ、国民の戦意をあおるのが例になった」と指摘していました(「軍神・西住戦車長」、『歴史と小説』、集英社文庫)。
このとき司馬氏の批判は日本の知識人を批判していた小林秀雄の歴史認識にも向けられていた可能性が高いと思われます。なぜならば、「疑惑 Ⅱ」というエッセーで「インテリゲンチャには西住戦車長の思想の古さが堪えられないのである。思想の古さに堪えられないとは、何という弱い精神だろう」と書いた小林はこう続けていたからです。
「今日わが国を見舞っている危機の為に、実際に国民の為に戦っている人々の思想は、西住戦車長の抱いている様な単純率直な、インテリゲンチャがその古さに堪えぬ様な、一と口に言えば大和魂という(中略)思想にほかならないのではないか」(太字は引用者。『小林秀雄全集』第七巻、六八頁)。
しかも小林は「伝統は生きている。そして戦車という最新の科学の粋を集めた武器に乗っている」と書いて国民の戦意を煽っていましたが、当時の日本の戦車はソ連などと比較するとすでに時代遅れのタイプであり、司馬氏は『坂の上の雲』を書き終わった一九七二年に発表したエッセーで、「戦車であればいいじゃないか。防御鋼板の薄さは大和魂でおぎなう」とした「参謀本部の思想」を厳しく批判していたのです(太字は引用者。「戦車・この憂鬱な乗り物」)。
しかも司馬氏は『竜馬がゆく』を執筆中の一九六四年に日中戦争の時に二五歳で戦死し、「軍神」とされた戦車隊の下士官・陸軍中尉西住小次郎についても、「明治このかた、大戦がおこるたびに、軍部は軍神をつくって、その像を陣頭にかかげ、国民の戦意をあおるのが例になった」と指摘していました(「軍神・西住戦車長」、『歴史と小説』、集英社文庫)。
夏目漱石は一九〇二年に締結された日英同盟の締結に沸く日本をロンドンから冷静に批判していましたがこのような「思想」によって、それからわずか四〇年足らずの一九四一年に日本は「神武東征」の神話を信じて、「皇軍無敵」と「鬼畜米英」を唱えて無謀な太平洋戦争へと突入していました。
それゆえ、劇作家・井上ひさし氏との対談で、戦後に出来た新しい憲法のほうが「昔なりの日本の慣習」に「なじんでいる感じ」であると語った司馬氏は「ぼくらは戦後に『ああ、いい国になったわい』と思ったところから出発しているんですから」、「せっかくの理想の旗をもう少しくっきりさせましょう」と語り、「日本が特殊の国なら、他の国にもそれも及ぼせばいいのではないかと思います」と続けていました。(「日本人の器量を問う」『国家・宗教・日本人』講談社、1996年)。
司馬氏との対談もある憲法学者の樋口陽一氏も、「大正デモクラシ-だけではなく、その前には自由民権運動があり、幕末維新の時代には『一君万民』という旗印で平等を求める動きもあった。それどころか、全国各地で民間の憲法草案が出ていた」ことに注意を促して「日本国憲法」が明治の「立憲主義」を受け継いでいることを明らかにしています。
さらに、樋口氏は井上氏との共著『日本国憲法を読み直す』(岩波現代文庫)の「文庫版あとがき」で、「井上ひさしの不在という、埋めることのできない喪失感を反芻しながら、一九九三~九五年の対論を読み返した。(中略)そのことにつけても、日本の現実を私たち二人と同様に――いや、もっとはげしく――憂えていた司馬遼太郎さんのことを、改めて思う」と記しているのです。
 (書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)
(書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)
本書では司馬氏が深く敬愛していた正岡子規や夏目漱石の「写実」や「比較」という方法に注目しながら、独裁的な「藩閥政府」との厳しい闘いをとおして「憲法」を獲得した時代に青春を過ごしていた明治の文学者たちの考察や島崎藤村の『破戒』と『夜明け前』を『罪と罰』をとおして詳しく読み解くことで、「憲法」のない帝政ロシアで書かれ権力と自由の問題に肉薄した『罪と罰』の意味に迫りました。
この作業をとおして19世紀のグローバリズムとナショナリズムの問題を直視しつつ、ドストエフスキーの作品の普遍的な意義に迫ろうとした北村透谷や島崎藤村などの深みと視野の広さだけでなく、日本国憲法の現代的な意義に迫ることができればと願っています。
ただ、日本文学や法律の専門家ではないので、思いがけない誤解があるかも知れません。忌憚のないご意見を頂ければ幸いです。(表記は現代表記に改めました)。
→ 一、小林秀雄の平田篤胤観と堀田善衛
(2018年8月18日、改題と改訂)