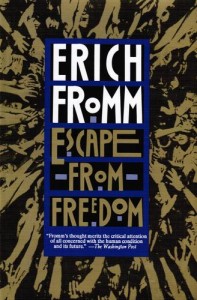「伝統は何処にあるか。僕の血のなかにある。若し無ければぼくは生きていないはずだ。」「僕は大勢に順応して行きたい。妥協して行きたい。」
(小林秀雄、「文学の伝統性と近代性」、昭和11年)(写真は二・二六事件)
「批評の神様」とも称される文芸評論家の小林秀雄(一九〇二~八三)は「国民文化研究会」の主宰者で、後に「日本会議」の代表者の一人にもなる小田村寅二郎の招きに応じて昭和36年から昭和53年にわたり5回の講演を九州で行っていました。
その際に行われた学生との対話を収録した『学生との対話』(新潮社、2014年)の「解説」を書いた編集者の池田雅延は、「永年、批評文を書いてきて、小林秀雄が到達した境地は、『批評とは他人をほめる技術である』でした」と記し、それは「小林秀雄が早くからめざしていたことの当然の帰結といってよいものでしたと続けています(「問うことと答えること」、194頁)。

実際、小林秀雄は一九六四年に発表した「批評」というエッセイで次のように記していました。
「自分の仕事の具体例を顧みると、批評文としてよく書かれているものは、皆他人への讃辞であって、他人への悪口で文を成したものではない事に、はっきりと気附く。そこから率直に発言してみると、批評は人をほめる特殊の技術だ、と言えそうだ。」
たしかに「人をけなすのは批評家の持つ一技術ですらなく、批評精神に全く反する精神的態度である、と言えそうだ……」と指摘しているこの文章を読むと一見、そうかとも納得させられるようになります。
しかし、この文章に強い違和感を覚えるのは、評論「現代文学の不安」でドストエフスキーについて、「だが今、こん度こそは本当に彼を理解しなければならぬ時が来たらしい」と記した小林が、その一方で芥川龍之介を「人間一人描き得なかつたエッセイスト」と激しくけなしていたからです。
そして、「この絶望した詩人たちの最も傷ましい典型は芥川龍之介であつた」と規定した小林は、「多くの批評家が、芥川氏を近代知識人の宿命を体現した人物として論じてゐる。私は誤りであると思ふ」と続けていました。
このエッセイが書かれたのは上海事変が起き、満州国が成立した一九三二(昭和七)年のことでした。その翌年には日本が国際連盟から脱退して国際関係において孤立を深めるとともに、国内でも京都帝国大学で滝川事件が起きるなど検閲の強化が進んでいました。そのことに留意するならば、2・26事件が起きた昭和11年に発表した「文学の伝統性と近代性」というエッセイで中野重治などを批判しつつ、「伝統は何処にあるか。僕の血のなかにある。若し無ければぼくは生きていないはずだ。こんな簡単明瞭な事実はない」と書くとともに、「僕は大勢に順応して行きたい。妥協して行きたい」と記すようになる小林が、芥川を批判することで早くも時勢に順応しようとしていたことが感じられます。(写真は二・二六事件)
 (「ウィキペディア」より)
(「ウィキペディア」より)
しかも、それは芥川龍之介に対してのみのことではありませんでした。1934年9月から翌年の10月まで連載した「『白痴』について1」で、「ムイシュキンはスイスから帰つたのではない。シベリヤから還つたのだ」と強調した小林は、「『罪と罰』の終末を仔細に読んだ人は、あそこにゐるラスコオリニコフは未だ人間に触れないムイシュキンだといふことに気が付くであろう」。
さらに、1937年に発表した「『悪霊』について」では「スタヴロオギンは、ムイシュキンに非常によく似てゐる、と言つたら不注意な読者は訝るかも知れないが、二人は同じ作者の精神の沙漠を歩く双生児だ」と断言していました。
こうして、読者を「注意深い読者」と普通の読者、「不注意な読者」の三種類に分類して、自分の読み方に従う読者を「仔細に読んだ人」と称賛する一方で、自分の読み方とは異なる読み方をする者を「不注意な読者」と「けなして」いたのです。
* *
このような傾向は『学生との対話』にも現れています。「僕たちは宿命として、日本人に生まれてきたのです。(……)日本人は日本人の伝統というものの中に入って物を考え、行いをしないと、本当のことはできやしない、と宣長さんは考えた。」と語った小林は、「考古学」に基礎を置いた歴史観をこう「けなして」いました(太字は引用者、95頁)。
「たとえば、本当は神武天皇なんていなかった、あれは嘘だとういう歴史観。それが何ですか、嘘だっていいじゃないか。嘘だというのは、今の人の歴史だ。」(「信ずることと考えること」、127頁)。
一方、小林秀雄の「宿命論」的な考えを批判するような思想を述べていたのがフランスの哲学者アランでした。「……人が宿命論を信ずれば、それだけで宿命は本物になってしまう。(……)いっそう明白なことは、民衆の全体が戦争が不可避だと信じれば、現実にそれはもう避けがたい。あまり人がしばしば通った道ではないが、辿る(たど)るのにそうむずかしくはない道がある。それは戦争を避けることが出来るということが真実になるためには、まず戦争が避け得ると信ずる必要があるという結論に到達するための道筋である。」
このことを堀田善衞は『若き日の詩人たちの肖像』のアランの翻訳をめぐる議論でこう指摘しています。「これね、翻訳あるんだけど、その翻訳ね、翻訳じゃないんだ、検閲のことを考えて、一章ごっそりないところや、削ったところなんか沢山あって、あれ翻訳じゃないんだけど、小林秀雄さんがあの翻訳のこととりあげて、良い本だ、っていうらしいことを書いていたの、あれいかんと思うんだけど……」
そして、こう続けられているのです。「その翻訳だと、戦争も生活の一つだ、地道に立向かって行け、ってことになるんだ、逆なんだ、本当は小林さんはこの原書を読んでないってことはないと思うんだけど」。
この言葉は宿命論的な考えに対する批判を省いてアランの戦争論を理解していた小林秀雄に対する鋭い批判となっているでしょう。
(2019年5月28日、加筆)
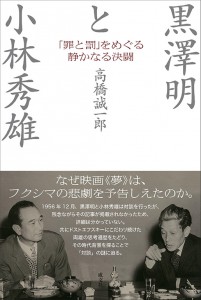


 写真の出典は奈良県立図書情報館。
写真の出典は奈良県立図書情報館。

 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)

 (朝日新聞出版)
(朝日新聞出版)

 (書影は『世界文学』126号、2017年)
(書影は『世界文学』126号、2017年)