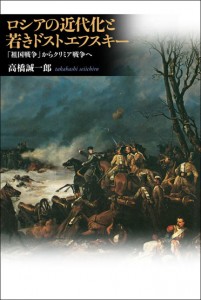目次
1、グローバリゼーションとナショナリズム
2、父親の世代と蘇峰・蘆花兄弟の考察――『ひとびとの跫音』の構成をめぐって
3、大正時代と世代間の対立の考察
4、ナショナリズムの批判――陸羯南と加藤拓川の戦争観
5、治安維持法から日中戦争へ――昭和初期「別国」の考察
6、記憶と継続――窓からの風景
7、司馬遼太郎の憂鬱――昭和初期と平成初期の類似性
2,父親の世代と蘇峰・蘆花兄弟の考察――『ひとびとの跫音』の構成をめぐって
『ひとびとの跫音』(中公文庫)は次のような章から成り立っている。
(上巻)電車、律のこと、丹毒、タカジという名、からだについて、手紙のことなど、伊丹の家、子規旧居、子規の家計/(下巻)拓川居士、阿佐ヶ谷、服装、住居、あるいは金銭について、ぼたん鍋、尼僧、洗礼、誄詩
「電車」と名付けられたこの小説の最初の章で司馬遼太郎は、かつて阪急電鉄株式会社に車掌としてつとめていた「忠三郎さんのことを書こうとしている」とし、「昭和五一年九月十日の朝、忠三郎さんは脳出血による七年のわずらいのあと、伊丹の自宅の近所の病院でなくなった。七十五歳であった」(太字引用者)と記した。
市井に生きる無名の人々の人情や自然の風景を、とぎすまされた感性で描いた藤沢周平は、司馬遼太郎の主な長編歴史小説を読んでいないことを認めつつも、自分が『この国のかたち』や『街道をゆく』シリーズの「人後に落ちない愛読者であった」と認め、さらに「『ひとびとの跫音』一冊を読んだことで後悔しないで済むだろうと思うところがある」と書き、『ひとびとの跫音』においては「ふつうの人人が司馬さんの丹念な考証といくばくかの想像、さらに加えて言えば人間好きの性向によって一人一人が光って立ち上がって見えてくる」として絶讃した(*8)。
実際、随筆風に書き進められているかに見えるこの小説でも、やはり読んで行くに従って、司馬遼太郎に独特の堅固で緻密な構成と明確な主題を持っていることに気づかされる。
たとえば、後にこの忠三郎が加藤拓川の実子であるとともに、正岡子規の死後に家を継いだ妹律の養子となった人物であることが明らかにされるのだが、この小説を読んでいくと最初の章に記されたさりげない多くの文章が次第に重要な意味を持ち、次の章の主題と直結していることがわかる。
たとえば、忠三郎の「七年のわずらい」を看病した妻のあや子についての描写は、「二十代から三十代にかけての七年間、兄の看病のために終始し、そのことにすべてを捧げた」子規の三歳下の妹律を描いた「律のこと」や「丹毒」の章へとつながるのである。しかも、そこで司馬は兄の死を看取った後で律が東京の共立女子職業学校で学んだことや、さらにそこを卒業した後は母校で教鞭をとっていたこと、さらにその律の養子となった忠三郎と律や実母ひさ、さらにはあや子と二人の義母との関わりなど、それまでほとんど知られていなかった事実を淡々と描いている。
さらに名字を省いて主人公を単に「忠三郎さん」と紹介するという方法は、自らを「タカジ」と呼ばせた西沢隆二について描いた「タカジという名」や「からだについて」の章にも直結しており、それに続く「手紙のことなど」の章では二高時代のタカジと忠三郎との友情が描かれることになる。
そして、「伊丹の家」、「子規旧居」、「子規の家計」などの章でも日中戦争の年に結婚した忠三郎とあや子との結婚の話を核としながら、彼らの生活を通して母となった律や実父加藤拓川、実母との関わりが描かれているだけでなく、実父加藤拓川と秋山好古や陸羯南との関わりなど子規を形作った人々について記されているのである。そして、これらの章の後に本書のクライマックスの一つといえる「拓川居士」において、拓川の愛国論批判が紹介されることになる。
忠三郎の葬儀がカトリックの教会で行われたことも第一章でさりげなく記されているが、このことは彼の「六つ下の末の妹」の「たへ」が洗礼を受けて「ユスティチア」となったいきさつや、彼女たち修道女が日本軍の占領政策のためにフィリピンへと行くことが描かれる後半の章「尼僧」や、忠三郎が妹の意をくんで洗礼をうけることになる「洗礼」の章とも深く関わっていたのである。
そして、忠三郎の葬式に際して葬儀委員長を引き受ける羽目になった司馬がなれぬ葬儀場の手配や「死亡記事」の扱いなどで振り回されたいきさつが記されているのだが、続いて彼はさりげなくこう書いていたのである。「そのあと八日たち、伊丹の正岡家の通夜の日、薄暗い台所で音をたてていたひとの亭主が、信州の佐久でなくなった」。そして、「ほどなく私事だが」、「私自身の父親が死んだ」。こうして、ここには「誄詩(るいし)」と題された終章につながる主要なことが提示されていたのである。
司馬はこの作品の執筆理由の一つとして「忠三郎さんとタカジというひとたちの跫音を、なにがしか書くことによってもう一度聴きたいという欲求があった」と書いているが、彼らは大正時代に青春を過ごした司馬自身の父親と同じ世代の人々であり、さらに司馬は忠三郎の父親の世代である正岡子規や律などを調べることによって、明治以降の三代の世代をも再考察しているのである。
この意味で注目したいのは、この作品では大正時代に生きた人々が主人公として選ばれていることに注目した評論家の小林竜雄氏が、この小説には「さりげなく隠されたものもある」とし、「司馬遼太郎自身の父親」のテーマも根底にあることを指摘していたことである(*9)。まず、小林氏は「誄詩」の章で短く触れられた次の文章に注意を向けている。「私の身辺にも、タカジよりすこし年上の父が、食道や気管にできた癌で入院していた。このとしは、その種のことで多忙だった。父は、忠三郎さんやタカジが亡くなってから、ほどなく死んだ」。
そして、小林氏は司馬の父「是定は頑固な父・惣八のせいで、江戸期のように寺子屋で学ばされ中学校にも行けなかった。そこで独立して試験を受け薬剤師となったのである。そこには”明治の父”に振り回された”大正の父”の姿があった」とし、「司馬はその父の『跫音』もこの物語から聞いていたのだろう」と書いた。
司馬の内面にも踏み込んだ鋭い指摘であり、大正末期に生まれた司馬が昭和初期に青春を迎えていることを考慮するならば、ここには明治から昭和にいたるまでの市井の人々の生き方が淡々と描かれているといっても過言ではないのである。クリミア戦争に負けて価値が混乱したロシアでは、価値観を巡る世代間の対立が激化して、ツルゲーネフの『父と子』やドストエフスキーの『虐げられし人々』などの作品が書かれたが、『ひとびとの跫音』においても大正時代に青春を過ごした忠三郎と父親の世代の子規や加藤拓川との関わりや、さらに忠三郎の子供の世代ともいえる大岡昇平や司馬遼太郎の世代にいたる三代の青春が描かれていることに気づく。
実際、司馬は忠三郎が中学校二年の一九一四年に、日本が日独戦争と呼んだ第一次世界大戦が始まったこと、司馬が生まれた一九二三年(大正一二)には関東大震災があったこと、忠三郎が就職した一九二七年(昭和二)には、「金融恐慌が進行して」いたこと、さらに忠三郎があや子と結婚した一九三七年が日中戦争の勃発の年であったことなど、個人の体験を日本史の流れの中に位置づけつつ描いているのである。
ただ、小林氏は司馬の父是定を「”明治の父”に振り回された”大正の父”」としたが、単に「振り回された」と言い切れるだろうか。司馬は最後の章「誄詩」で、「この稿の主題は」、「子規から『子規全集』まで」というべきものであったかと思っているとしているが、「言語についての感想(七)」という随筆や『坂の上の雲』のあとがきで司馬は正岡子規や徳冨蘆花の小説と出会ったのは、父親が買った全集によってであったと記しているのである(*10)。
すなわち、司馬はここで「私は少年のころ、父の書架に、正岡子規と徳冨蘆花の著書またはそれについての著作物が多く、つい読みなじんだ。この二人はほぼ同時代でありながら文学的資質に共通点を見出すことがむずかしい。また明治国家という父権的重量感のありすぎる国家にともに属しつつも、それへの反応はひどくちがっていた」と記して子規だけでなく、蘆花の全集にもふれていた。そして司馬は「蘆花の父一敬は横井小楠の高弟で、肥後実学を通じての国家観が明快であった人物で、蘆花にとって一敬そのものが明治国家というものの重量感とかさなっているような実感があったようにおもわれる」とし、「また父の代理的存在である兄蘇峰へも、一敬に対する嫌悪と同質のものがあり、しだいに疎隔してゆき、晩年は交通を絶った」と続けて父や兄との世代間の葛藤や対立にもふれていたのである(Ⅷ・「あとがき五」)。
つまり、「私事」としてあまり強くは語られてはいないが、「生涯、記録に値するような事跡はみごとなほどのこさなかった」が、「そのことでかえっていぶし銀のような地張りを感じさせてしまう」市井のひと、忠三郎という人物の姿は、強烈な個性を持ち、政府の欧化政策に反抗して学校にも入れなかった祖父のもとで、あまり反抗的な自己主張はしなかったが、子規や蘆花の全集を買い求めて読み込んでいた父親への思いが重なっていたように思えるのである。
徳冨蘆花は日露戦争後に書いた「勝利の悲哀」と題するエッセーにおいて、「一歩を誤らば、爾が戦勝は即ち亡国の始とならん、而して世界未曾有の人種的大戦乱の原とならん」と強い危機感を表明していた(*11)。
司馬も「勇気あるジャーナリズム」が、「日露戦争の実態を語っていれば」、「自分についての認識、相手についての認識」ができたのだが、それがなされなかったために、日本各地で日本政府の弱腰を責めたてる「国民大会が次々に開かれ」、放火にまで至ることになったと記して、ナショナリズムを煽り立てる報道の問題を指摘した(*12)。さらに『この国のかたち』の第一巻において司馬は、戦争の実態を「当時の新聞がもし知っていて煽ったとすれば、以後の歴史に対する大きな犯罪だったといっていい」と記して、当時の新聞報道を厳しく批判した。
蘇峰が『蘇峰自伝』の「戦時中の言論統一と予」と題した節で、「予の行動は、今詳しく語るわけには行かぬ」としながらも、戦時中には桂内閣の後援をして「全国の新聞、雑誌に対し」、内閣の政策の正しさを宣伝することに努めていたと書いていることを考えるならば、司馬の鋭い批判は、蘇峰と彼の『国民新聞』に向けられていたと言っても過言ではないだろう。実際、ビン・シン氏の考察によれば、「そうなら国民に事情を知らせて諒解させれば、あんな騒ぎはなしにすんだでしょうに」と問い質した蘆花に対して、蘇峰は「お前、そこが策戦(ママ)だよ。あのくらい騒がせておいて、平気な顔で談判するのも立派な方法じゃないか」として、敵と交渉をするためには味方を欺くことも必要だと答えていたのである(*13)。
しかも、天皇機関説論争が激しさを増した一九三五年(昭和一〇)に「第一天皇機関などと云ふ、其の言葉さへも、記者は之を口にすることを、日本臣民として謹慎す可きものと信じてゐる」と徳富蘇峰が書いていることを紹介した評論家の立花隆氏は、明治四五年に美濃部の『憲法講話』が公刊された際にも、すでに蘇峰の『国民新聞』に「美濃部説は全教育家を誤らせるもの」という批判記事が載っていたことを記している(*14)。
実際、歴史家の飛鳥井雅道氏によれば、この記事の筆者は「しきりに乱臣賊子にあらざることを弁解するに力(つと)むるも、其言説文字は、則ち帝国の国体と相容れざるもの多々なり」として美濃部達吉を厳しく批判し、『国民新聞』も社説などで美濃部の説を「遂に国家を破壊せざれば、已まざるなり」とした職を去ることを強く求めるキャンペーンを行っていたのである(*15)。
『ひとびとの跫音』においてもタカジと父親との対立も描かれていることを考えるならば、私たちはこの小説に「さりげなく隠された」テーマとして日露戦争後に平和を主張した蘆花と蘇峰の対立の問題も考慮にいれる必要があるだろう。
ところで司馬はこの小説について「歴史小説などとは違い、主人公たちは、ついさっきまで市井(しせい)を歩いていたのですからまずファクト(事実)がある。だから読めば気楽に読めますけれど、一点一画もおろそかにしてはいけないという気持ちで執筆しました」(太字引用者)と書いていた。
この言葉の意味は非常に重く、司馬遼太郎の歴史認識と作風の変化自体にもかかわっていると思える。この意味で注目したいのは、司馬が歴史小説を書き始めた頃に司馬が「私の小説作法」として、自分が鳥瞰的な手法をとることを明言していたことである。「ビルから、下をながめている。平素、住みなれた町でもまるでちがった地理風景にみえ、そのなかを小さな車が、小さな人が通ってゆく。そんな視点の物理的高さを私はこのんでいる。つまり、一人の人間をみるとき、私は階段をのぼって行って屋上へ出、その上からあらためてのぞきこんでその人を見る。同じ水平面上でその人を見るより、別なおもしろさがある」(*16)。
司馬の歴史小説のおもしろさの一端がここにあったのは間違いないだろう。磯田道史氏は蘇峰や司馬の歴史観が「大衆から圧倒的支持をうけた」と指摘し、「支持された理由は簡単である。ものの見方が実に大局的であり、わかりやすい言葉で語りかけたからである」と説明していた(*17)。実際、多くの読者が書き手である司馬と同じ歴史上の場面を見ながら、司馬の断言的で明快な解説により、それまで複雑で難解だと思っていた歴史に対する興味を持つようになったのである。
ただ、司馬は「鳥瞰的な手法」で歴史を描くとしたが、そのような視野を得るためには何らかの「基準」や「史観」が必要とされていたはずであり、それなくしては上からの風景は単なる「無秩序」になったと思える。それゆえ、「皇国史観」や「唯物史観」という特定の見方からの歴史観を排しつつ、『竜馬がゆく』など「国民国家」を形成する歴史上の人物を主人公とする作品を描き始めたとき、司馬自身はあまり意識していなかったにせよ、彼が依拠していたのは「自由や個性」を重視していた福沢諭吉の歴史観だったと思える。
しかし、すでにドストエフスキーが『地下室の手記』において厳しく批判していたように、福沢諭吉が依拠したバックルの『イギリス文明史』などの近代西欧の歴史観では、「文明」による「野蛮」の征伐が「正義の戦争」として認められており、また、「国益」が重視されることにより、個人間の場合の道徳とは異なり、自国の「国益」にかなわない「事実」は無視されるか、「事実」とは反対のことさえも主張されていたのである(*18)。
このことに気づいたあとでの執筆上の苦悩を司馬は『坂の上の雲』の中頃、正岡子規の死を描いた「十七夜」の次の章の冒頭でも次のようにうち明けている。「この小説をどう書こうかということを、まだ悩んでいる。/子規は死んだ。/好古と真之はやがては日露戦争のなかに入ってゆくであろう。/できることならかれらをたえず軸にしながら日露戦争そのものをえがいてゆきたいが、しかし、対象は漠然として大きく、そういうものを十分にとらえることができるほど、小説というものは便利なものではない(太字引用者、Ⅲ・「権兵衛のこと」)。
そして司馬は第四巻のあとがきでは、「当時の日本人というものの能力を考えてみたいというのがこの作品の主題だが、こういう主題ではやはり小説になりにくい」と記し、その理由としてこのような小説は「事実に拘束される」が、「官修の『日露戦史』においてすべて都合のわるいことは隠蔽」されていることを挙げるようになるのである。
ここには大きな歴史認識の変化が現れているといえるだろう。つまり、後期「福沢史観」と決別したとき司馬は、比喩的にいえば、羽を失って飛べなくなった鳥と同じ様に鳥瞰的な視野を失ったのである。こうして司馬は「国家」の作成による「歴史」ではなく、日露の歴史書を比較しながら自ら判断して書かざるをえないという事態と直面したのである。
それゆえ、『坂の上の雲』を書き終えた司馬遼太郎にとって、大きな課題として残されたのは、「国民」を幸せにすることを約束しつつ、富国強兵に邁進して「国民」を戦争や植民地の獲得へと駆り立てた近代西欧の「国民国家史観」や、そのような歴史観に対抗するために、「自国を神国」と称する一方で、「鬼畜米英」に対する防衛戦争の必然性を唱えて無謀な「大東亜戦争」へと突入することになった「皇国史観」に代わる歴史観を模索し、それを提示するという重たい課題であったと思われる。
この意味で注目したいのは、評論家の関川夏央氏との対談で歴史家の成田龍一氏が「『ひとびとの跫音』は時として異色の作品といわれることもあるようですが、私は非常に司馬遼太郎らしい作品だと読みました。同時にここでは司馬遼太郎が一九八〇年前後に新たな試みをはじめている」ことに注意を向けるとともに、司馬自身が登場人物の一人となっていることにも注意を促していることである(*19)。
つまり、この作品で司馬は鳥瞰的な視点から人物や歴史を描いているのではなく、司馬遼太郎自身が同じ平面にたって彼らと対話を交わしながらこれらの人物を描いているのである。そしてこの作品では司馬自身も自分が敬愛した正岡子規を同じように敬愛し、「子規全集」を出版しようとする熱意に燃えるひとびととの交友をとおして、新しい歴史観と文明観を提示し始めていたのである。
註(2)
* 8 藤沢周平「遠くて近い人」『司馬遼太郎の世界』、一九九六年
* 9 小林竜雄『司馬遼太郎考――モラル的緊張へ』中央公論社、二〇〇〇年
*10 司馬遼太郎『この国のかたち』第六巻、三二七頁
*11 徳冨蘆花「勝利の悲哀」『明治文学全集』(第四二巻)、筑摩書房、昭和四一年、三六七頁
*12 司馬遼太郎『「昭和」という国家』NHK出版、一九九八年、三六頁
*13 ビン・シン『評伝 徳富蘇峰――近代日本の光と影』、杉原志啓訳、岩波書店、一九九四年、および徳富蘇峰『蘇峰自伝』中央公論社、昭和一〇年参照
*14 立花隆『天皇と東大――大日本帝国の生と死』文藝春秋、二〇〇六年、下巻・一三五頁、上巻・四三四頁
*15 飛鳥井雅道『明治大帝』講談社学術文庫、二〇〇二年、四七~五一頁。なお、日露戦争後の教育をめぐる状況については、高橋『司馬遼太郎の平和観――「坂の上の雲」を読み直す』東海教育研究所、二〇〇五年参照
*16 司馬遼太郎『歴史と小説』集英社文庫、一九七九年(初出は一九六四年)、二七五~六頁
*17 磯田道史、前掲エッセー、二二頁
*18 科学的な装いをこらした西欧近代の「自国中心的」な歴史観に対するドストエフスキーの批判については、高橋「『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』第四章参照(刀水書房、二〇〇二年)
*19 関川夏央・成田龍一「(特別対談)『ひとびとの跫音』とは何か ある大正・昭和の描き方」(『文藝別冊 司馬遼太郎 幕末・近代の歴史観』河出書房新社、二〇〇一年、四〇頁、四八頁