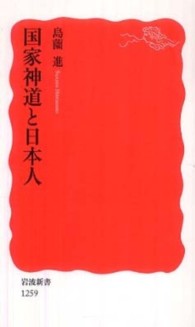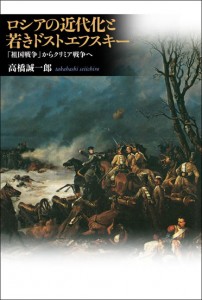資料1、講座の流れと主な引用箇所
はじめに――漱石と子規の青春と「教育勅語」の影
Ⅰ.子規の退寮事件と「教育勅語」論争
Ⅱ.陸羯南の新聞『日本』の理念と新聞『小日本』
Ⅲ.従軍記者・子規の戦争観と日露戦争中に書かれた『吾輩は猫である』
Ⅳ.漱石の『草枕』と子規の紀行文「かけはしの記」――長編小説『三四郎』へ
おわりに 「教育勅語」問題の現代性
主な引用・参考文献
→夏目漱石と正岡子規の交友と方法としての比較・関連年表
はじめに――漱石と子規の青春と「教育勅語」の影
a.「子規は果物(くだもの)が大変好(す)きだった。且(か)ついくらでも食(く)える男だった。」(『三四郎』第1章)
「我死にし後は」(前書き)、「柿喰ヒの俳句好みと伝ふべし」(子規、明治30年)
b.「憲法発布は明治二十二年だったね。その時森文部大臣が殺(ころ)された。君は覚えていまい。幾年(いくつ)かな君は。そう、それじゃ、まだ赤ん坊の時分だ。僕は高等学校の生徒であった。大臣の葬式に参列するのだと云って、大勢鉄砲を担(かつ)いで出た。墓地へ行くのだと思ったら、そうではない。体操の教師が竹橋内(たけばしうち)へ引っ張って行って、路傍(みちばた)へ整列さした。我々は其処(そこ)へ立ったなり、大臣の柩(ひつぎ)を送ることになった。」(『三四郎』第11章)
c.「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」(「教育勅語」)
Ⅰ.子規の退寮事件と「教育勅語」論争
a.「私は卯の年の生れですから、まんざら卯の花に縁がないでもないと思ひまして『卯の花をめがけてきたか時鳥(ほととぎす)』『卯の花の散るまで鳴くか子規(ほととぎす)』などとやらかしました。又子規といふ名も此時から始まりました。」(子規「啼血始末」)
b.「(佃にとっては)大学に文科があるというのも不満であったろうし、日本帝国の伸長のためにはなんの役にも立たぬものと断じたかったにちがいない。…中略…この思想は佃だけではなく、日本の帝国時代がおわるまでの軍人、官僚の潜在的偏見となり、ときに露骨に顕在するにいたる」(『坂の上の雲』第2巻「日清戦争」)。
c.「『義勇公に奉すべし』とのたまへる教育勅語、さては宣戦詔勅を非議」(大町桂月、与謝野晶子「君死にたまふこと勿(なか)れ」の批判)
d.『教育勅語』は「国体教育主義を経典化した」もの。
「正直に云えば、我が青年及び少年に歓迎せらるる書籍、及び雑誌等は、半ば以上は病的文学也、不完全なる文学也」(徳富蘇峰『大正の青年と帝国の前途』)
Ⅱ.陸羯南の新聞『日本』の理念と新聞『小日本』
a.「秘密秘密何でも秘密、殊には『外交秘密』とやらが当局無二の好物なり、…中略… 斯かる手段こそ当局の尊崇する文明の本国欧米にては専制的野蛮政策とは申すなれ」(新聞『小日本』)
b.「北村透谷子逝く 文学界記者として当今の超然的詩人として明治青年文壇の一方に異彩を放ちし透谷北村門太郎氏去る十五日払暁に乗し遂に羽化して穢土の人界を脱すと惜(をし)いかな氏年未だ三十に上(のぼ)らずあたら人世過半の春秋を草頭の露に残して空しく未来の志を棺の内に収め了(おは)んぬる事嗟々(あゝ)エマルソンは実に氏が此世のかたみなりけり、芝山の雨暗うして杜鵑(ほとゝとぎす)血に叫ぶの際氏が幽魂何処(いづこ)にか迷はん」(新聞『小日本』)。
c.「愚なるかな、今日に於て旧組織の遺物なる忠君愛国などの岐路に迷ふ学者、請ふ刮目(くわつもく)して百年の後を見ん」(北村透谷「明治文学管見(日本文学史骨)」)
d.「(松陰の)尊王敵愾(てきがい)の志気は特に頼襄(らいのぼる)の国民的詠詩、及び『日本外史』より鼓吹し来たれるもの多し」(徳富蘇峰『吉田松陰』)
e.「青木(モデルは北村透谷)君が生きていたら、今頃は何を為(し)てるだろう」/「何を為てるだろう。新聞でもやってやしないか――しきりに新聞をやって見たいッて、そう言ってたからネ」(島崎藤村『春』)
Ⅲ.従軍記者・子規の戦争観と日露戦争中に書かれた『吾輩は猫である』
a.「若し夫の某将校の言ふ所『新聞記者は泥棒と思へ』『新聞記者は兵卒同様なり』等の語をして其胸臆より出でたりとせんか。是れ冷遇に止まらずして侮辱なり」(子規「従軍記事」)
「一国政府の腐敗は常に軍人干政のことより起こる」(陸羯南「武臣干政論」)
b.「三崎の山を打ち越えて/いくさの跡をとめくれば、此処も彼処も紫に/菫花咲く野のされこうべ」(子規「髑髏」)。
c.「(景樹が)大和歌の心を知らんとならば大和魂の尊き事を知れ、などと愚にもつかぬ事をぬかす事、彼が歌を知らぬ証拠なり」(子規「歌話」)
「万の外国其声音の溷濁不清なるものは其性情の溷濁不正なるより出れば也」(香川景樹『古今和歌集正義総論』)
d.「世の中に比較といふ程明瞭なることもなく愉快なることもなし…中略…織田 豊臣 徳川の三傑を時鳥(ほととぎす)の句にて比較したるが如き 面白くてしかも其性質を現はすこと一人一人についていふよりも余程明瞭也」。「併シ斯く比較するといふことは総(すべて)の人又は物を悉(ことごと)く腹に入れての後にあらざれば出来ぬこと故 才子にあらざれば成し難き仕事なり」(子規「筆まかせ」)。
e.「大和魂(やまとだましい)! と叫んで日本人が肺病みの様な咳をした。/(中略)/大和魂! と新聞屋が云ふ。大和魂! と掏摸(すり)が云ふ。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂の演説をする。独逸(ドイツ)で大和魂の芝居をする/東郷大将が大和魂を有(も)つて居る。肴屋の銀さんも大和魂を有つて居る。詐欺師(さぎし)、山師(やまし)、人殺しも大和魂を有つて居る。/(中略)/誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇(あ)つた者がない。大和魂はそれ天狗の類か」(漱石『吾輩は猫である』第6章)。
f.「どうかしてイワンの様な大馬鹿に逢つて見たいと存候。/出来るならば一日でもなつて見たいと存候。近年感ずる事有之イワンが大変頼母しく相成候」(夏目漱石、内田魯庵『イワンの馬鹿』訳の礼状)
g.「社会の暗黒裡に潜める罪悪を解剖すると同時に不完全なる社会組織、強者のみに有利なる法律、誤りたる道徳等のために如何に無垢なる人心が汚され無辜なる良民が犠牲となるかを明らかにす」(内田魯庵『復活』について)
Ⅳ.漱石の『草枕』と子規の紀行文「かけはしの記」――長編小説『三四郎』へ
a.「やがて、長閑(のどか)な馬子唄(まごうた)が、春に更(ふ)けた空山(くうざ ん)一路の夢を破る。憐(あわ)れの底に気楽な響きがこもって、どう考えても画にかいた声だ。/ 馬子唄の鈴鹿(すずか)越ゆるや春の雨/ と、今度は斜(はす)に書き付けたが、書いて見て、これは自分の句でないと気が付いた。」(漱石『草枕』)
「馬子唄の鈴鹿(すずか)上るや春の雨」(子規、明治25年)
b.小説で「白いひげをむしゃむしゃと生やした老人」として描かれているのは熊本実学党の名士・前田案山子(かかし)で、彼が明治11年に建てた別邸には中江兆民が訪れてルソーの講義をしたり、女性民権家の岸田俊子が来て演説をおこなっていた(安住恭子『「草枕」の那美と辛亥革命』)白水社、2012年)。
c.「一体戦争は何のためにするものだか解らない。後で景気でも好くなればだが、大事な子は殺される、物価は高くなる。こんな馬鹿気たものはない」
d.「亡びるね」という男の言葉を聞いた三四郎は最初「熊本でこんなことを口に出せば、すぐ擲(な)ぐられる。わるくすると国賊取扱にされる」と感じた。しかし、「囚(とら)われちゃ駄目だ。いくら日本のためを思っても贔屓(ひいき)の引倒しになるばかりだ」という男の言葉を聞いたときに、「真実に熊本を出たような心持ちがした。同時に熊本にいた時の自分は非常に卑怯であったと悟った」と記されている(『三四郎』)。
e.「反動は愛山生を載せて走れり。而して今や愛山生は反動を載せて走らんとす」(北村透谷「人生に相渉るとは何の謂ぞ」)。
おわりに 「教育勅語」問題の現代性
a.「教育勅語」の「始まりと終わりの部分で天皇と臣民の間の紐帯、その神的な由来、 また臣民の側の神聖な義務について」述べられているという構造を持っている(島薗進『国家神道と日本人』岩波新書)。
b.「日本魂とは何ぞや、一言にして云へば、忠君愛国の精神也。君国の為めには、我が 生命、財産、其他のあらゆるものを献ぐるの精神也」(徳富蘇峰『大正の青年と帝国の前途』)
主な引用・参考文献
高橋誠一郎『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』人文書館、2015年。
――『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』成文社、2007年。
――『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房、2002年 。
――「北村透谷と島崎藤村――「教育勅語」の考察と社会観の深まり」『世界文学』 第125号、2017年。
――「作品の解釈と「積極的な誤訳」――寺田透の小林秀雄観」『世界文学』第122号、2015年。
――「司馬遼太郎の徳冨蘆花と蘇峰観――『坂の上の雲』と日露戦争をめぐって」『COMPARATIO』九州大学・比較文化研究会、第8号、2004年。
『漱石全集』全15巻、岩波書店、1965~67年(振り仮名は一部省略した)。
小森陽一『世紀末の予言者・夏目漱石』講談社、1999年。
木下豊房『ドストエフスキー その対話的世界』成文社、2002年。
大木昭男『漱石と「露西亜の小説」』東洋書店、2010年。
井桁貞義『ドストエフスキイ 言葉の生命』群像社、2011年。
安住恭子『「草枕」の那美と辛亥革命』白水社、2012年。
清水孝純『漱石『夢十夜』探索 闇に浮かぶ道標』翰林書房、2015年。
中村文雄『漱石と子規 漱石と修――大逆事件をめぐって』和泉書院、2002年。
『子規と漱石』(『子規選集』第9巻)、増進会出版社、2002年。
『子規全集』全22巻、別巻3巻、監修・正岡忠三郎・司馬遼太郎・大岡昇平他、講談社、1975~79年。
坪内稔典『正岡子規 言葉と生きる』岩波新書、2010年。
末延芳晴『正岡子規、従軍す』平凡社、2010年。
成澤榮壽『加藤拓川――伊藤博文を激怒させた硬骨の外交官』高文研、2012年。
『現代日本文學大系6 北村透谷・山路愛山集』筑摩書房、1969年。
槇林滉二「透谷と人生相渉論争――反動との戦い」、桶谷秀昭・平岡敏夫・佐藤泰正編『透谷と近代日本』翰林書房、1994年。
徳富蘇峰『吉田松陰』岩波文庫、1981年 司馬遼太郎『本郷界隈』(『街道をゆく』第37巻)朝日文芸文庫、1969年。
有山輝雄『陸羯南』吉川弘文館、2007年。
島崎藤村『春』、『破戒』、新潮文庫。
相馬正一『国家と個人――島崎藤村『夜明け前』と現代』人文書館、2006年。
木村毅「日本翻訳史概観」『明治翻訳文學集』筑摩書房、1972年。