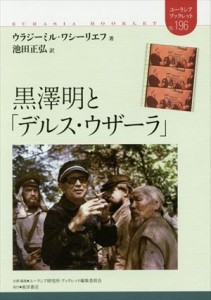一、 《愛の世界・山猫とみの話》から《赤ひげ》へ
戦時中の一九四三年一月に公開された映画《愛の世界・山猫とみの話》の脚本が主に黒澤明監督の手に成るものであったことは「ブログ」に記したが、この映画にはその後の黒澤明監督作品を予想させるような、テーマとシーンが見られた。
ことに注目されたのは、例会発表でも指摘されたように、両親と七歳で死別して曲馬団に売られ、その後も様々な職業を転々とするなかで時には凶暴性を発揮したり、何ヶ月も口を利かずに「山猫」とみとあだ名された少女の形象には、映画《赤ひげ》で行われることになる『虐げられた人々』の少女ネリーの見事に映像化がすでになされたいたことである。
私は映画《赤ひげ》(一九六五)におけるお粥の入った茶碗を少女おとよが壊すシーンと映画《白痴》におけるナスターシヤが花瓶を壊すシーンを比較して、心に傷を負った彼女たちの行動が見事に描き出されていることを指摘して、黒澤明監督の『虐げられた人々』と『白痴』理解の深さを指摘していた(拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』、成文社、九三~九八頁)。
つまり、ワルコフスキー公爵の実の娘でありながら、母親を捨てて死に追いやった父親の援助を拒んで幼くしてなくなった少女ネリーの人物造形は、火事で孤児になった後で無理矢理に「貴族」トーツキーの妾とされていたが、莫大な持参金を拒んで自立しようとして苦しんだ長編小説『白痴』のナスターシヤ像の先駆的な役割を担っていると思われるのである。
映画《赤ひげ》は一九五一年に公開された映画《白痴》から、はるか後年に撮られていることもあり、黒澤明監督の『虐げられた人々』の理解が深まったのは、映画《白痴》を撮った後であるという解釈も可能であった。しかし、映画《愛の世界・山猫とみの話》が一九四三年一月に公開されていたことは、映画《白痴》を撮ることになる黒澤明監督が、すでにこの時点で『虐げられた人々』のネリー像の重要性を理解していたことを強く示唆していると思われる。
この点に留意するとき、なぜ映画《白痴》の後で撮られた映画《生きる》(一九五二)では余生がわずかなことを知った主人公の前に、メフィストフェレスを自称する作家が犬を連れて現れることが描かれているのかも理解できる。
二、『虐げられた人々』の構成と粗筋
四部とエピローグからなる本格的な長編小説『虐げられた人々』(原題は『虐げられ、侮辱された人々』)でも、語り手である主人公のイワンがみすぼらしい老人とその老犬の死に立ち会うという印象的な場面から始まり、その孫娘ネリーの出生の謎をめぐって物語が展開されているのである。
映画《愛の世界》や《赤ひげ》の理解にも関わるので、あまり知られていない『虐げられた人々』の粗筋をまず簡単に紹介しておきたい。
この長編小説では少女ネリーをめぐる出来事と孤児となったイワンを養育したイフメーネフの没落と娘ナターシャをめぐる物語が並行的に描かれて行くが、物語が進むにつれて、しだいにこれらの悲劇の原因が、ネリーの父ワルコフスキー公爵の詐欺的な言動によるものであることがはっきりしてくる。
すなわち、ネリーの祖父はイギリスで工場の経営者だったが、娘がワルコフスキー公爵にだまされて父の書類を持ち出して駆け落ちしたために全財産を失って破産に陥っていたのである。
一方、一五〇人の農奴を持つ地主で主人公のイワンを養育したイフメーネフ老人の悲劇も、九〇〇人の農奴を所有する領主としてワルコフスキー公爵が隣村に引っ越してきて、イフメーネフ家を訪れて懇意になると自分の領地の管理を依頼し、さらに五年後には新たな領地の購入とその村の管理をも任せたことから始まる。
積極的にイフメーネフに近付いて、自分の領地の管理を任せてその能力に満足したと語っていた公爵は、後に自分の領地の購入に際してイフメーネフが購入代金をごまかしたという訴訟を起こし、有力なコネや賄賂を使って裁判を有利に運んだ。そのために、裁判に敗けて一万ルーブルの支払いを命じられたイフメーネフ老人は自分の村を手放さねばならなくなったのである。
こうして、少女ネリーの悲劇が描かれている長編小説『虐げられた人々』は、クリミア戦争敗戦後のロシアを揺るがせていた二つの大きな問題、農奴制の廃止と資本主義の導入の問題点を浮き彫りにして、混沌とした時代の雰囲気や「大改革」の時代の課題を描き出していたといえるだろう。
三、映画《愛の世界・山猫とみの話》における「鬱蒼とした森」の描写
長編小説『虐げられた人々』が連載された雑誌『時代』は、農奴制の廃止や言論の自由を求めたために捕らえられて死刑の判決を受けた後でシベリア流刑へと減刑されていたドストエフスキーが、刑期を終えて首都に帰還してから兄ミハイルとともに創刊した雑誌である。
クリミア戦争の敗戦により農奴制の問題が認識されて、農奴解放などが行われた「大改革」の時代に首都に戻ったドストエフスキーは、「われわれはこの上なく注目に値する重大な時代に生きている」とし、「欧化」でも「国粋」でもない、第三の道として「大地主義」の理念を掲げるとともに、文盲に近い状態におかれていた「農民」に対する教育の重要性とともに、「知識人」が「農民の英知」を学ぶ必要性も唱えていた。
そのような「農民の英知」の一つは、「森や泉」に深い敬意を払う民衆の自然観だろう。たとえば、木下豊房氏は『貧しき人々』や『虐げられた人々』、さらに『百姓マレイ』などにも言及しつつドストエフスキー家の領地であったダロヴォーエの森について書いたエッセー「フェージャの森」で、「都会の作家といわれるドストエフスキーの深奥には、実は豊かなロシアの自然と大地(土壌)が横たわっている」と指摘している(『ドストエフスキー その対話的世界』、成文社、二〇〇二年、二九七~三〇〇頁)。
さらに、論文「思い出は人間を救う――ドストエフスキー文学における子供時代の思い出の意味について」(『ドストエーフスキイ広場』、第一六号、二〇〇七年)では、具体的に『虐げられた人々』の文章にも言及しているので、《愛の世界》との関わりを具体的に示すためにも、まずはその文章を引用しておく。
「ニコライ・セルゲーヴィチ(引用者注――イフメーネフのこと)が管理人であったワシリエフスコエ村の庭園や公園は何と素晴らしかったことか。私とナターシャはこの庭園へよく散歩にでかけたものだった。庭園の向こう側には、鬱蒼とした大きな森があって、私たち二人の子供は一度、道に迷ってしまったことがあった……美しい黄金時代! 人生がはじめて、秘密めいて、誘惑にみちた姿で現れ、それを知ることは、何とも甘美であった」。
映画《愛の世界・山猫とみの話》から強い印象を受けた場面の一つは、少女救護院で自分をいじめた園児と激しい喧嘩をして脱走して、最初は歌を歌いながら自然の美しさに見とれ、自由を謳歌していた少女とみを描いた後で、次第に暗くなってくると道に迷って森から出られなくなったとみにとっては森が巨大な妖怪の住む無気味な世界へと一変したことが描かれていることである。
この美しい森から無気味な森への変化は、自然の変化を深く理解して見事な道案内人の役を果たしたデルスが、眼を悪くしたあとでは自然を恐れるようになったことが描かれている映画《デルス・ウザーラ》をも思い起こさせる。
しかも、畑仕事が厭で怠けていた少女とみは、映画の最後では畑仕事に喜んで従事している場面が描かれているが、それは文部大臣によって京都帝国大学の憲法学者滝川教授が罷免された事件を題材にして、敗戦直後の一九四六年に公開された映画《わが青春に悔なし》(脚本・久板栄二郎、黒澤明)のシーンを思い起こさせる。この映画でも父の教え子でジャーナリストになっていた野毛を敬愛して彼の元に走って同棲生活を送るようになった娘の幸枝が、野毛がスパイ容疑で逮捕され獄中で死亡した後では、野毛の実家へと行って彼の母親(杉村春子)を手伝って黙々と大地を耕すシーンがドキュメンタリー的な手法で描かれていたのである。
農民を指導して野武士の群盗たちと戦い百姓たちを守った七人の侍の雄々しい戦いが描かれている映画《七人の侍》(脚本・黒澤明、橋本忍、小國英雄)の最後のシーンでも、戦いに勝ったあとで百姓たちが行っていた田植えの場面がクローズアップされていた。そして「いや……勝ったのは……あの百姓たちだ……俺たちではない」と語った指導者の勘兵衛は、さらに「侍はな……この風のように、この大地の上を吹き捲って通り過ぎるだけだ……土は……何時までも残る……あの百姓たちも土と一緒に何時までも生きる!」と続けているのである(『全集 黒澤明』第四巻、九五頁)。
映画《愛の世界・山猫とみの話》は「国策映画」として製作されたために、表現は制限されてはいるが、ここには一九五四年に公開された映画《七人の侍》に見られるような黒澤明監督の「大地主義」への深い理解がすでに現れているように思われる。
四、小林秀雄の『虐げられた人々』理解と映画《赤ひげ》
『虐げられた人々』においては「庭園の向こう側には、鬱蒼とした大きな森」があったことが描かれていたが、「大地主義」の時期の代表的な作品である『罪と罰』では、本編におけるペテルブルグの「壮麗な眺望の謎」に対応するように、シベリアにおける「鬱蒼(うっそう)たる森林」の謎も読者の前に呈示されていた。
映画《夢》の分析において詳しく考察することになるが、この「鬱蒼(うっそう)たる森林」の謎を理解したことが、『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフの精神的な「復活」へとつながることが『罪と罰』では示唆されている。
しかし、今もドストエフスキー論の「大家」と見なされている文芸評論家の小林秀雄は一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で、『罪と罰』の「第六章と終章とは、半分は読者の為に書かれたのである」と書いて、ラスコーリニコフの「復活」を否定していた(『小林秀雄全集』第六巻、新潮社、一九六七年、五三頁。引用に際しては、旧漢字は新し漢字になおした)。
このような小林秀雄の理解には、ドストエフスキーが『地下室の手記』(一八六四)で「かつて、自分が拝跪していたものを…中略…泥の中に踏みつけてしまった」と記し、ニーチェとともにドストエフスキーを「理性と良心」を否定する「悲劇の哲学」の創造者と規定したシェストフからの強い影響があるだろう(拙著、『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』、刀水書房、二〇〇二年、一二六頁参照)。
しかも、ドストエフスキー自身は『虐げられた人々』について、後に次のような厳しい評価を下していた。
「『虐げられし人々』の時もさうだつた。雑誌には是非長篇が要る。何を置いても成功させねばならぬ。そこで僕は四部から成る長篇を一つ提供したわけだ。プランはずつと前から出来てゐるから、わけなく書けるし、第一部はもう書き上げてあるなどと言つて兄を安心させてゐたが、みんな出鱈目だつた。僕は金が欲しくて働いたのだ。僕の小説中に動いてゐるのは人形であつて、生き物ではない」。
『地下室の手記』によって前期と後期のドストエフスキー作品との間に深い断層を見たシェストフの見解を受け入れていた小林秀雄は、「ドストエフスキイの生活」で作家自身の言葉を引用することで、『地下室の手記』以前に書かれた『虐げられた人々』も失敗作とみなした。その一方で、ドストエフスキーを「理性と良心」を否定した作家と見なした小林は、『白痴』論では「たゞ確かなのはこの時ムイシュキンははや魔的な存在となつてゐる」とし、ナスターシヤを「この作者が好んで描く言はば自意識上のサディストでありマゾヒストである」と規定したのである(「『白痴』についてⅠ」)。
たしかに、急いで書いたこともあり、主人公のイワンをはじめ多くの人物造形がそれほど成功裏に描かれているとは言えないだろう。しかし、ドストエフスキーは謙遜的に記してはいるものの、この小説では幼いながらも高い誇りを持った虐げられた少女ネリーの形象がきわめていきいきと描かれていたばかりでなく、大地主の横暴さや法律の問題など当時の問題を浮き彫りにしており、ここで提起された多くの問題は『罪と罰』以降の長編小説で深められており、ことに『白痴』では誇り高い少女ネリーとナスターシヤの間にはあきらかな連続性が認められるのである。
しかし、映画《白痴》が一九五一年に公開された翌年の一九五二年から「『白痴』についてⅡ」を書き続けた小林は、長い間中断した後で一九六四年に付け加えた第九章では長編小説の結末について次のように記した。
「作者は破局といふ予感に向かつてまつしぐらに書いたといふ風に感じられる。『キリスト公爵』から、宗教的なものも倫理的なものも、遂に現れはしなかった。来たものは文字通りの破局であつて、これを悲劇とさへ呼ぶ事はできまい」。そして小林は、「お終ひに、不注意な読者の為に注意して置くのもいゝだろう。ムイシュキンがラゴオジンの家に行くのは共犯者としてである」と続けていたのである(傍線引用者、三三九~三四〇頁)。
このような小林の断定的な解釈について、私はエッセー「『不注意な読者』をめぐって」で、この時小林秀雄が強く意識していたのは、名指しをしてはいないが、映画《白痴》で病んだナスターシヤを看護しようとしたムィシキンに光をあてながら長編小説『白痴』の映画化をしていた黒澤明監督である可能性が高いという仮説を記した(『ドストエーフスキイ広場』、第二二号)。
誌面の都合上、詳しい理由を記すことはできなかったが、私が注目したのは映画《白痴》を撮った黒澤明監督による映画《赤ひげ》の制作開始記念パーティが一九六三年一〇月六日に行われていたことである(『大系 黒澤明』第四巻、八二〇頁)。
様々な事情のために映画《赤ひげ》の撮影は大幅に延びて、公開は一九六五年四月三日になったが、『虐げられた人々』の少女ネリーの形象が採り入れられているばかりでなく、精神的な医師としてのムィシキンの精神を受けついでいるとも思える医師「赤ひげ」とその若い弟子を主人公にした映画のことは、小林秀雄の耳にも入っていたと思える。
自分の『白痴』論を真っ向から否定するような映画《白痴》を撮った黒澤明監督による新しい映画の公開が、自分のドストエフスキー論の土台を覆す危険性を含んでいることを敏感に感じた小林秀雄が、「不注意な読者」を批判する断定的な文章を加えて、急遽『白痴について』(角川書店、一九六四年)を上梓したのではないかと私は考えている。
小林秀雄の『白痴について』を批判する評論を黒澤明監督は書いてはいない。しかし、一九七五年にロシアで撮った映画《デルス・ウザーラ》が日本で公開された後で、若者たちと行った座談会で黒澤明監督は、「小林秀雄もドストエフスキーをいろいろ書いているけど、『白痴』について小林秀雄と競争したって負けないよ」と語っているのである(黒澤明研究会編『黒澤明 夢のあしあと』共同通信社、二八八頁)。
このような発言にはロシアで映画を撮ることになったことで、黒澤映画《白痴》をきわめて高く評価するとともに、自分でも映画《罪と罰》(一九六九年)を撮っていたクリジャーノフ監督などととの会話をとおして、自分の『白痴』理解の正しさと「大地主義」の時期の重要さを再確認したためと思われる。
ただ、それはすでに新しいテーマなので稿を改めて書くことにしたい。
(本稿は『黒澤明と小林秀雄――長編小説『罪と罰』で映画《夢》を読み解く』と題して来年の三月に発行する予定の著作の第四章〈映画《赤ひげ》から《デルス・ウザーラ》へ――黒澤明監督と「大地主義」〉(仮題)に収録する予定である)。
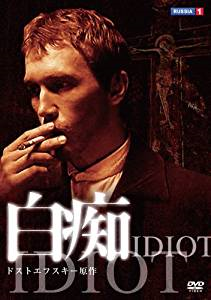

 (く黒澤
(く黒澤