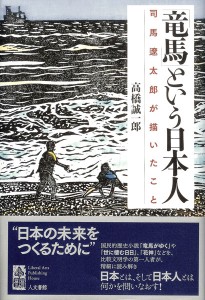【「(幕末の神国思想は――引用者註)明治になってからもなお脈々と生きつづけて熊本で神風連(じんぷうれん)の騒ぎをおこし、国定国史教科書の史観となり、昭和右翼や陸軍正規将校の精神的支柱となり、おびたたしい盲信者」を生んだ(司馬遼太郎、『竜馬がゆく』】
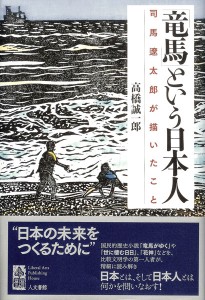 (←画像をクリックで拡大できます)
(←画像をクリックで拡大できます)
「総選挙を終えて」と題した2014年の記事では、〈一昨年の参議院選挙と同じように、国会での十分な審議もなく「特定秘密保護法」や「集団的自衛権」を閣議決定する一方で、原発の危険な状況は隠して〉行われたことに注意を促して、「若者よ、『竜馬がゆく』を読もう」と呼びかける記事を書きました。
なぜならば、その時の選挙で指摘された点の一つは若者の選挙離れでしたが、司馬氏は『竜馬がゆく』で最初は他の郷士と同じように「尊皇攘夷」というイデオロギーを唱えて外国人へのテロをも考えた土佐の郷士・坂本龍馬が、勝海舟との出会いで国際的な広い視野と、アメリカの南北戦争では近代兵器の発達によって莫大な人的被害を出していたなどの知識を得て、武力で幕府を打倒する可能性だけでなく、選挙による政権の交代の可能性も模索するような思想家へと成長していくことを壮大な構想で描いていたのです。
しかも長編小説『竜馬がゆく』おいて、幕末の「神国思想」が「国定国史教科書の史観」となったことを指摘した作家の司馬遼太郎は「日本会議」が正当化している「大東亜戦争」についても、「その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」と厳しく批判していたのです(『竜馬がゆく』文春文庫より)。
竜馬に「おれは薩長の番頭ではない。同時に土佐藩の走狗(そうく)でもない。おれは、この六十余州のなかでただ一人の日本人と思っている」と語らせた時、司馬は坂本竜馬という若者に託して神道によって「政教一致」の国家を建設するのではなく、民主的な理念によって統一国家としての日本を建設するという理念を記していたといえるでしょう。
実際、竜馬が打ち出した「船中八策」には、「明治維新の綱領が、ほとんどそっくりこの坂本の綱領中に含まれている」とした司馬遼太郎は、その用語が明治元年の『御誓文』にそのままこだましているだけでなく、ことに「上下議政局を設け、議員を置きて、万機を参賛(さんさん)せしめ、万機よろしく公議に決すべき事」という第二策は、「新日本を民主政体(デモクラシー)にすることを断乎として規定したものといっていい」と高く位置づけていたのです(Ⅶ・「船中八策」)。
→『「竜馬」という日本人――司馬遼太郎が描いたこと』(人文書館、2009年)
【吉田松陰から高杉晋作を経て、「権力政治家」山県有朋に至るまでを描いた『世に棲む日日』を視野に入れつつ、「天誅」やテロが横行していた幕末に、「オランダ憲法」を知って武力革命ではなく平和的な手段で政権を変えようとした若者の生涯を描いた『竜馬がゆく』を読み解く】
* * *
一方、日本国憲法の施行70周年にあたる今年を「節目の年」と指摘した安倍首相は、「新しい時代にふさわしい憲法」に向けた議論を深めようと「新しい」という形容詞を用いて呼びかけつつ、神道による「祭政一致」を目指す「国民会議」の意向に従って「改憲」を行う姿勢を一層明確に示しました。
しかし、作家・百田尚樹との共著『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』もある安倍首相を支え、「日本国憲法」を批判している「日本会議」の思想は、旧日本軍の「徹底した人命軽視の思想」と密接に結びついています。
たとえば、映画化もされた小説『永遠の0(ゼロ)』は、一見、特攻を批判しているように見えますが、その主要登場人物の武田が賛美している思想家の徳富蘇峰は、『大正の青年と帝国の前途』で「日本魂とは何ぞや、一言にして云へば、忠君愛国の精神也。君国の為めには、我が生命、財産、其他のあらゆるものを献ぐるの精神也」と書いた徳富蘇峰は、「大正の青年」たちに自立ではなく、「白蟻」のように死ぬ勇気を求めていました。
→〈若者よ 白蟻とならぬ 意思示せ〉
→〈子や孫を 白蟻とさせるな わが世代〉
つまり、蘇峰の思想は軍部の「徹底した人命軽視の思想」の先駆けをなしており、そのような思想が多くの餓死者を出して「餓島」と呼ばれるようになったガダルカナル島での戦いなど、6割にものぼる日本兵が「餓死」や「戦病死」することになった「大東亜戦争」を生んだと言っても過言ではないと思います。
このことに注目するならば、登場人物に徳富蘇峰が「反戦を主張した」と主張させることによって、彼の「神国思想」を美化している『永遠の0(ゼロ)』は、日本の未来を担う青少年にとってきわめて危険な書物だといえるでしょう。
* * *
それゆえ、前回は若者に『竜馬がゆく』を読もうと呼びかけたのですが、今回はかつての愛読者だった私たちの世代も含めて、偏狭なナショナリズムに支配されずに普遍的な価値観を目指す「投票権」のあるすべての人々に呼びかけることにしました。
なぜならば、司馬遼太郎は「私は戦後日本が好きである。ひょっとすると、これを守らねばならぬというなら死んでも(というとイデオロギーめくが)いいと思っているほどに好きである」(『歴史の中の日本』中公文庫)と書いていたからです。
このことを想起するならば、司馬作品の愛読者は戦前の「五族協和」というスローガンに似た「積極的平和主義」などという用語によって、古い「祭政一致」の軍事国家に移行しようとしている危険な安倍政権を退場させる年にしましょう。