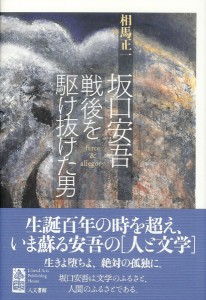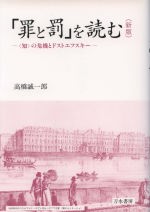(ネタバレあり)
『永遠の0(ゼロ)』を読み始めた私は、そのトリックが明らかになる後半に近づくにしたがって、この作品が「文学」を侮辱しているばかりでなく、その「作者」が「人間」を馬鹿にしていると激しい怒りを覚えました。
「黒幕は誰か」という今回のテーマについては、一応、推理小説的な構造を持つこの作品のネタバレになるので躊躇していました。
しかし、「臆病者」と罵(ののし)られながらも、「家族」のことを大切に思い、「命が大切」と語っていた宮部久蔵が終戦間際に「突撃」して亡くなるという最後の不自然さについては、すでにアマゾンのカスタマーレビューなどでも指摘されています。
それゆえ、まだ読んでいない人にはネタバレになることをお断りしたうえで、『永遠の0(ゼロ)』という小説の構造において、誰が「オレオレ詐欺」グループの黒幕的な働きをしているのを明らかにしたいと思います。
* *
まず、『永遠の0(ゼロ)』(講談社文庫)の家族関係と人間関係を確認しておきます。
家族関係
宮部久蔵(祖父、零戦のパイロット、特攻隊員として死亡)
宮部松乃(祖母、久蔵の死後、大石賢一郎と再婚)
佐伯清子(宮部夫妻の娘、姉弟の母、夫の死後、会計事務所を経営)
佐伯健太郎(清子の息子、語り手、弁護士を志す若者)
佐伯慶子(清子の娘、フリーのライター)
佐伯慶子をめぐる二人の男性
高山隆二(大手新聞社の終戦60周年のプロジェクトの一員。慶子に好意を抱く)
藤木秀一(大石賢一郎の法律事務所で学生時代からアルバイトをしながら司法試験を目指し、慶子が想いを寄せていた男性)
取材対象者
第2章/長谷川梅男(ラバウル航空隊の戦友、祖父の宮部を「臆病者」と罵る)
第3章/伊藤寛次(第一航空戦隊赤城時代の戦友。久蔵の空戦技術を高く評価)
第4章/井崎源次郎(ラバウル航空隊時代の部下。久蔵に二度助けられる)
第5章/井崎源次郎(ガダルカナル島での悲惨な戦いについて語る)
第6章/永井清孝(ラバウルで機体を整備。久蔵についての逸話を語る)。
第7章/谷川正夫(戦争後の苦労を語り、戦後のモラルの低下を批判)
第8章/岡部昌男(県会議員を4期勤める、「特攻は十死零生の作戦」と批判)
第9章/武田貴則(一部上場企業の元社長、徳富蘇峰を礼賛し、高山を追い返す)
第10章/景浦介山(祖父と空中戦を行って命を狙った・やくざ)
第11章/大西保彦(小さな旅館を営む元一等兵曹で沖縄戦の記憶を語る)
第12章/大石賢一郎(ここで初めて宮部久蔵との関わりを明かす)。
* *
察しのよい人ならば、この構成を見ただけで推測がつくと思いますが、この小説を姉弟の成長の物語として読もうとするとき、その致命的な欠陥が小説の構造と祖父・大石賢一郎が果たしている役割にあると思われます。
第1章で語り手の健太郎は、祖母・松乃の葬式からしばらく経って、祖父の大石賢一郎から、彼らの実の祖父が終戦間際に特攻で戦死した海軍航空兵で、祖父の死後に祖母は彼らの母・清子を連れて自分と再婚したことを知らされて驚いたが、「祖母からは前夫のことはほとんど知らされていなかったらしい」と記しています。
それから6年後に、司法試験に4度も落ちて「自信もやる気も失せて」いた「ぼく」が、フリーのライターをしている姉の慶子から取材のアシスタントを頼まれて、「特攻隊員」たちの取材をとおして戦争に迫ろうとするこの企画に参加するところから物語が始まります。
慶子から「本当のおじいさんがどんな人だったのか、とても興味があるわ。だってこれは自分のルーツなのよ」と語られた「ぼく」は、「突然、亡霊が現れたようなもの」と感じたと描かれており、なぜ祖父の大石賢一郎が自分の妻・松乃の死後まで彼らの実の祖父のことを黙っていたのだろうかという疑問が浮かんできますが、その疑問には答えられぬままに物語は進むのです。
* *
祖父の大石賢一郎については、30歳を過ぎてから弁護士となった「努力の人」であり、「貧しい人たちのために走り回る弁護士」で、「ぼくはその姿を見て弁護士を目指していたのだ」と描かれているだけでなく、事務所でアルバイトをしていた苦学生の藤木からも尊敬されるような「理想」の人物であることが強調されています。
第3章の冒頭では「ぼく」が実の祖父の調査を始めたことを告げると、一瞬、祖父の大石が「ちょっと怖いようなまなざし」で、「じっとぼくの目を見つめた」と描かれていますが、そこでは何も語られません。
注目したいのはこの章で、アルバイトをしていた苦学生の藤木との楽しい思い出や、中学生だった姉との関係が簡単に記されており、それが新聞記者・高山との比較という形で続いていくことになることです。
たとえば、この小説の山場の一つである第9章では、慶子に好意を寄せる新聞記者・高山が、一部上場企業の元社長にもなっていた特攻隊員の武田貴則から怒鳴られてすごすごと引き返す場面が描かれていました。
それゆえ、高山には姉の慶子に合わす顔もないはずなのですが、「最後」と題された第11章では、高山が武田への発言を深く反省して姉にもプロポーズをするが、弟から「ぼくはあの人を義兄さんとは呼びたくないな」と言われたことで迷っていた慶子は断念し、藤木との結婚を考えることが示唆されているのです。
* *
このような流れを経てようやく「流星」と題された第12章で、「臆病者」と罵られていた実の祖父・宮部久蔵の実像が「祖父」の大石賢一郎から明かされることになります。
映画《永遠の0(ゼロ)》の宣伝文では「60年間封印されていた、大いなる謎――時代を超えて解き明かされる、究極の愛の物語」と大きく謳われています。
しかし、第12章で大石は「いつかお前たちに語らなければならないと思っていた」と説明していますが、「命の大切」さを訴えていた宮部の理念を娘の清子に伝えようとはせず、60年間も沈黙し続けたのでしょうか。
結論的にいえば、「命の大切」さを訴えていた宮部の理念ではなく、自分の思想を植え付けるためだったと思われます。
進化した「オレオレ詐欺」では、様々な役を演じるグループの者が限られた情報を一方的に伝えることによって次第に被害者を信じ込ませていきます。
それと同じように小説『永遠の0(ゼロ)』でも大石の沈黙こそが、巧妙に構成された順番に従って登場する「特攻隊員」の語る言葉とよって、次第に読者を「滅私奉公」の精神と「白蟻」の勇敢さを教えた戦前の「道徳」に基づいて行動するように誘導することを可能にしていたのです。
* *
次回の予告
このシリーズは年を越す前に一気に書き上げたいと考えていましたが、最終回は来年になります。
次回: 侮辱された主人公・宮部久蔵――「オレオレ詐欺」の手法と『永遠の0(ゼロ)』(10)


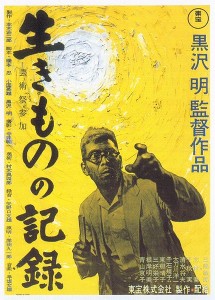
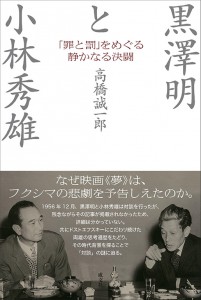
 (朝日新聞出版)
(朝日新聞出版)