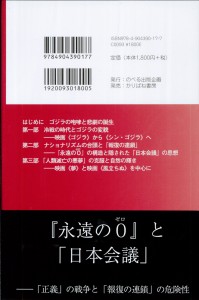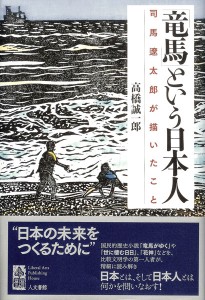『ゴジラの哀しみ』
— 高橋誠一郎 執筆中『ドストエフスキーの「悪霊」と日本の文学――黙示録的な世界観との対峙』 (@stakaha5) May 10, 2024
第一部「冷戦の時代と悲劇の誕生」
第二部「ナショナリズムの台頭と「報復の連鎖」」
第三部「「人類滅亡の悪夢」の克服と自然の輝き」https://t.co/zX3L5NNpaF https://t.co/DiOJ8UxwUw
序章 ゴジラの誕生まで
一、「不敗神話」と「放射能の隠蔽」
「水爆大怪獣」と名付けられた初代の「ゴジラ」がスクリーンに現れたのは、ビキニ沖の環礁で行われた水爆「ブラボー」の実験により、「第五福竜丸」が被曝し、久保山愛吉無線長が亡くなった一九五四年のことであった。
だが、その発端は第二次世界大戦の終戦直前の一九四五年八月にウラン型原子爆弾「リトルボーイ」とプルトニウム型原爆「ファットマン」が、相次いで広島と長崎に投下されたことにあった。オリバー・ストーン監督はその著書で原爆の研究者たちが「議論を重ねるうち、原子爆弾の爆発によって海水中の水素や大気中の窒素に火がつき、地球全体が火の玉に変わるかもしれない」可能性が出て来たので計画が一時中断された時期があったことを記している*1。
アメリカでは今も多くの人々が、原爆投下を多くのアメリカの軍人と日本人の生命を救うためにはやむをえない手段だったと考えているが、それは原発開発を行ったマンハッタン計画の当事者が被爆者の苦しみや痛みを「隠匿する政策」をとったためであり、新しい仮想敵国となったソ連との対決を意識したアメリカは投下を決行したのだった。しかも、その予算は日本の一九四〇年度の国家予算(六十一億円)をはるかに超える総額二十億ドル(当時のレートで約八十五億円)という巨額なものであった*2。
終戦後に広島を訪れたニューヨーク・タイムズのH・ロレンス記者は九月五日付けの記事で、「原爆によって四平方マイルは見る影もなく破壊しつくされ」、さらに「原爆で一瞬に死ぬのは少数であって、多くの死者は数時間、数日間、あるいは十数日間の激しい痛み苦しみの後に死ぬ」と記した。しかし、マンハッタン計画の副責任者の地位にあったというファーレル准将は、この記事が出た翌日に記者会見を開いて「広島・長崎では死ぬべきものは死んでしまい、九月上旬現在においては、原爆放射線のため苦しんでいるものは皆無だ」と声明し、その一週間後にはロレンス記者は先に自分が書いた「広島レポートすら否定する記事」を書いた。このことを明らかにした政治家の宇都宮徳馬はこのような措置が取られたのは、第一次世界大戦に際して用いられた化学兵器が、その非人道的な威力から禁止されたことを想起するならば、「生き残った被爆者が、原爆の後遺症のためにどれだけ苦しんでいるか」が明らかにされれば、「核兵器は明らかに『不必要な苦痛を与える兵器』として毒ガス、細菌毒素とともに、その製造使用を禁ぜられるべき兵器」とされたからであると説明している*3。
しかし、放射能の危険性を隠蔽したのはアメリカ軍だけではなかった。一九四一年一〇月に東条英機内閣は「次年度の政府予算案に理化学研究所への委託研究費として八万円(現在の四億円相当)を計上し」、その二年後には「特に米国の研究が進んでいるとの情報もある。この戦争の死命を制することになるかもしれない。航空本部が中心となって促進を図れ」との命令を原爆研究の第一人者・仁科博士に下していた*4。そして「ペグマタイに含まれるわずかな天然ウラン」に目をつけた陸軍は、「『君たちの掘っている石がマッチ箱一つくらいあれば、ニューヨークなどいっぺんに吹き飛んでしまうんだ。がんばってほしい』」と励まして少年たちをウランの砕鉱に駆り出していた*5。
立川賢の原爆小説『桑港(サンフランシスコ)けし飛ぶ』が、「『新青年』の一九四四年七月号に掲載された」ことを指摘した小野俊太郎は、日本が原子爆弾を先に完成させていれば、原子爆弾がアメリカに対して用いられていた可能性があったことを指摘し、原爆は「敗戦色が濃い中で、一気に情勢を反転できる究極の兵器だった」と説明している*6。
しかも広島に原爆が落とされた後では、「放射能力ガ強キ場合ハ人体ニ悪影響ヲ与フルコトモ考ヘラレル。注意ガ必要」との報告がなされたにもかかわらず、「放射能による被ばくを隠すため」に、「国民はおびえ、戦意を失うのではないか」と恐れた「当時の内閣や軍部はその事実を握りつぶした」*7。「神州不滅」の「神話」を信じ、危機的な事態には元寇の役のときのように「神風」が吹くと信じていた狂信的な政治家や軍人は、最後まで国民を戦争に駆り立てようとしていたのである。そのために、放射能の危険性を知らされなかった「身内の安否確認や救助のため市内に入った」多くの人たちも被曝することになったのである。
二、「新たな神話」と「核エネルギーの批判」
日本を占領したアメリカ軍が原爆の報道の厳しい検閲をしていたために被曝の被害の情報があまり広まらなかったこともあり、一九四六年七月二六日の『読売新聞』にはすでに「原子エネルギー平和産業に活用すれば 慈雨も呼び台風も止める」という題の記事が載っていた。さらに、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞のニュースの報を受けた後の一九四九年一一月五日付けの『読売新聞』は、「今日でこそ原子力はただちに原子兵器と関連して考えられているが」、「やがてそれが生産に応用されて人類の文明に新時代を開く日を期待することは全くの夢想ではないのである」という内容の社説を掲載していた*8。
注目したいのは、その前年に湯川博士と対談した文芸評論家の小林秀雄が、「私、ちょうど原子爆弾が落っこったとき、島木健作君がわるくて、臨終の時、その話を聞いた。非常なショックを受けました」と切り出し、「人間も遂に神を恐れぬことをやり出した……。ほんとうにぼくはそういう感情をもった」と語って、いち早く原子力をエネルギーとすることの危険性を鋭く指摘していたことである*9。
それに対して湯川が太陽熱も原子力で生まれており「そうひどいことでもない」と主張すると、「高度に発達する技術」の危険性を指摘した小林は、「目的を定めるのはぼくらの精神だ。精神とは要するに道義心だ。それ以外にぼくらが発明した技術に対抗する力がない」と厳しく反論し、湯川が「平和はすべてに優先する問題なんです。今までとはその点で質的な違いがあると考えなければいけない。そのことを前提とした上でほかの問題を議論しないといけない。アインシュタインはそういうことを言っている。私も全然同感です」と答えると、それに同意した小林は、「科学の進歩が平和の問題を質的に変えて了ったという恐ろしくはっきりした思想、そういうはっきりした思想が一つあればいいではないか」と結んでいた。
実際、アメリカは原爆を投下することでその脅威を見せつけることがソ連への圧力になると考えたのだが、それは自国にも投下されるのではないかという恐怖を煽ることになり、一九四七年四月にトルーマン米大統領が原子兵器の使用をためらわないと明言してから半年も経たない九月には、原爆の開発を急いだソ連の原爆保有が明らかになった。それゆえ、原爆などの大量破壊兵器によって人類が滅亡することを恐れたアメリカの科学誌『原子力科学者会報』は、一九四七年には世界の終末までの時刻を示す時計を発表して、その時刻が終末の七分前であることに注意を促していた。だが、その二年後には世界終末時計の針は三分前を指すようになっていた*10。
このような状況を受けて東京大学総長の南原繁は卒業式の演説で「原子爆弾や水素爆弾の近代科学の粋を集めた世界の次の総力戦は、おそらく有史以来の大戦、全人類の運命を賭けてのものと想像せられる」と語りかけ、この演説は『世界』の一九五〇年五月号に「世界の破局的危機と日本の使命」と題されて掲載されることになる*11。
「およそ将来の世界戦争においてはかならず核兵器が使用されるであろう」と核の時代における戦争が地球を破滅に導く危険性を指摘し、「あらゆる紛争問題の解決のための平和な手段をみいだすよう勧告する」という湯川秀樹博士ら著名な科学者が署名した「ラッセル・アインシュタイン宣言」が発表されたのが、「第五福竜丸」事件から一年後の一九五五年のことである*12。そのことに留意するならば、科学者が陥る科学技術の盲信に対する先駆的な批判をとおして、真実を見抜く観察眼の必要性と辛くても事実を見る勇気と「道義心」を強調していた小林秀雄や南原繁の文明観は、先見の明があったといえよう。
戦争中は三度も徴兵され、一九四六年にようやく中国から復員した本多猪四郎監督も、映画《ゴジラ》と原爆との関連についてこう明確に語っていた。
「『ゴジラ』は原爆の申し子である。原爆・水爆は決して許せない人類の敵であり、そんなものを人間が作り出した、その事への反省です。なぜ、原爆に僕がこだわるかと言うと、終戦後、捕虜となり翌年の三月帰還して広島を通った。もう原爆が落ちたということは知っていた。そのときに車窓から、チラッとしか見えなかった広島には、今後七二年間、草一本も生えないと報道されているわけでしょ、その思いが僕に『ゴジラ』を引き受けさせたと言っても過言ではありません」*13。
本多猪四郎監督「『ゴジラ』は原爆の申し子である。原爆・水爆は決して許せない人類の敵であり、そんなものを人間が作り出した。その事への反省です」
— 高橋誠一郎 執筆中『ドストエフスキーの「悪霊」と日本の文学――黙示録的な世界観との対峙』 (@stakaha5) August 3, 2020
(ポスターには「水爆大怪獣映画」と「死の放射能」の文字が!)
→ホームページhttps://t.co/x3yHokxyBJhttps://t.co/eIaglxoWJv pic.twitter.com/N5kOASEMQT
→『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の目次
註
*1 オリバー・ストーン、ピーター・カズニック、鍛原多恵子他訳『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史1 二つの世界大戦と原爆投下』早川書房、二〇一三年、二九一~二九三頁。
*2 中日新聞社会部編『日米同盟と原発 隠された核の戦後史』東京新聞、二〇一三年、三三頁。
*3 宇都宮徳馬『軍拡無用 21世紀を若者に遺そう』すずさわ書店、一九八八年、一四四~一四六頁。
*4 中日新聞社会部編、前掲書、二一頁。
*5 同右、二九頁。
*6 小野俊太郎『ゴジラの精神史』彩流社、二〇一四年、九一頁。
*7 中日新聞社会部編、前掲書、三七頁。
*8 山本昭宏、前掲書、六~七頁。
*9 小林秀雄「対談 人間の進歩について」、『小林秀雄全作品』第一六巻 、新潮社、二〇〇四年、五一~五四頁。
*10 「世界終末時計」の時刻は、「ウィキペディア」の説明による。
*11 山本昭宏、前掲書、一五頁。
*12 「ラッセル・アインシュタイン宣言」、日本パグウォッシュ会議、HP参照。http://www.pugwashjapan.jp/
*13 堀伸雄「世田谷文学館・友の会」講座資料「『核』を直視した四人の映画人たち――黒澤明、本多猪四郎、新藤兼人、黒木和雄」より引用。
第一部の構成
レビュー
返信
2024/05/10、改題と追加