
 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)
長編小説『若き日の詩人たちの肖像』が出版されたのは、元号が慶応から明治に改元された1868年10月23日から100周年となるのを記念して日本政府主催の「明治百年記念式典」が盛大に挙行された昭和43年のことでした。
佐藤栄作首相の時に行われたこの式典の準備会議・広報部会には林房雄も参加していましたが、「日本浪曼派」の保田與重郎は昭和18年(1943)に新聞に寄稿した小論では「明治の精神」を「その源に於いて『尊王攘夷』を根底としたものをさす」と定義して、「天誅」の名前で行われていた幕末のテロや自国を絶対化する「正義」の戦いを肯定していました。
この意味で注目したいのは、日本文化を重んじて物質より精神を重視する皇道派の影響を受けた陸軍青年将校たちが「昭和維新、尊皇斬奸」をスローガンに起こした昭和11年(1936)の2・26事件の背後関係や影響も『若き日の詩人たちの肖像』で描かれていることです。

すなわち、この事件の前年に起きた相沢事件――統制派の中心人物・永田鉄山陸軍省軍務局長の殺害事件――についても、皇道派の中心人物とされていた真崎甚三郎大将の息子である学友Mとの交友に関連して言及されています。
『ファッシズム批判』などの著作が1938年に発売禁止となり、翌年には休職処分とされて起訴された河合栄治郎・東京帝国大学教授の「二・二六事件の批判」(帝国大学新聞)や軍国主義と「国体明徴」運動を批判して伏字ばかりの文章となっていた『中央公論』の巻頭論文も詳しく紹介されているのです。
こうして、第一部の終わり近くでは主人公の「生涯にとってある区分けとなる影響を及ぼす筈の、一つの事件」が起きます。それはラジオから流れてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から「明らかにある種の脅迫」を感じた主人公が、続いて流れてきた「フランスのただの流行歌(シャンソン)」に「異様な感銘」を受け、「異様なことに、いますぐ何かをしなければならぬ」と思って背広を着て外に出た主人公は、それまで学んでいたドイツ語を捨てて新たにフランス語の勉強を始めて、法学部政治学科から仏文科に転科することになるのです。
その後で作者は、「空には秋の星々がガンガンガラガラに輝いていた」のを見た「若者は、星を見上げて、つい近頃に読んだある小説の書き出しのところを思い出しながら、坂を下りて行った」と書いています。そして、題辞でも引用していた『白夜』の冒頭の文章「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた(後略)」(米川正夫訳)を引用した堀田は、「小説は、二十七歳のときのドストエフスキーが書いたものの、その書き出しのところであった」と説明しています。
それまで主人公を「少年」と記していた作者がここで主人公を「若者」と呼び変えたことや『白夜』を書いたドストエフスキーがハンガリー出兵の前に起きたペトラシェフスキー事件で逮捕され、偽りの死刑宣告を受けた後でシベリアに送られていたことを思い起こすならば、ゲッベルスの演説から受けた「異様な衝撃」の大きさが感じられるでしょう。第一部はこう結ばれています。「水平線を見詰めて、下宿を引っ越そう、と若者は考えていた。」
さらに第2部でも、「まったくの偶然であったのだが、若者が引っ越したこのアパートの隣室に二・二六事件のときの首謀者中の首謀者であったI(注:モデルは磯部浅一)という男の未亡人が住んでいた」と記され、彼女が「夫の死後、軍首脳部弾劾と裁判の違法性について縷々(るる)と綴られたIの遺書を入手し、夫人はこれをある右翼の新聞記者とはかって写真で複写をし世上に流布させよう」としていたことも描かれているのです。こうして、「二・二六は最終的な落着におちつくまで接着してはなれなかった」と描かれているように、この事件は強い影を長編小説全体に投げかけています。
つまり、この事件の首謀者は非公開で弁護人なしという特設軍法会議で裁かれ処刑されましたが、それによって軍部における統制派の権力は強まり、また国粋的な「尊王攘夷思想」も広がるという結果を生んだのです。『ファッシズム批判』を1934年に発行していた自由主義知識人・河合栄治郎の2・26事件についての記述はその後の日本の政治の流れをも示唆しているといえるでしょう。
治安維持法のもとで左翼だけでなく自由主義者の若者たちが次々と逮捕され、あるいは戦死していったことが描かれている第2部では、ゲッベルスの演説の後で聞いたシャンソンからフランス語への関心を強めた若者が、仏文科に転科するまでの過程が詳しく描かれています。そして第3部では小林秀雄の『白痴』解釈を否定するような主人公のムィシキン観が記されていますが、開戦直前に定められた「大学学部等の在学年限又は修業年限短縮に関する件勅令要綱」によって3年生の9月で卒業させられることになった堀田は急いで書き上げた卒論で、「ランボオとドストエフスキー作『白痴』の主人公ムイシュキン公爵とを並べてこの世に於ける聖なるもの」を考察することになるのです。
少し、先を急ぎましたが、ヴェルレーヌの詩集の英語との対訳をまず買った若者は(上、177頁)、英語で書かれたフランス語の文法書を古本屋で買い求めて、仏語の私塾の中等科に強引に入ってフランス語の習得に専念し、仏蘭西文学科の「白柳君」(モデルは白井浩司)から模擬試験を受けました。
その時に出された問題が哲学者アランのMars ou la guerre jugée (1921年, 邦題『裁かれた戦争』)の一部で、その個所を見た若者が「ここには恐ろしいような真理がずばりと書き抜いてある」と感じながら訳出すると、白柳君は「もう仏文に来ても大丈夫だよ」と告げるとともに次のように語ったのです。
「これね、翻訳あるんだけど、その翻訳ね、翻訳じゃないんだ、検閲のことを考えて、一章ごっそりないところや、削ったところなんか沢山あって、あれ翻訳じゃないんだけど、小林秀雄さんがあの翻訳のこととりあげて、良い本だ、っていうらしいことを書いていたの、あれいかんと思うんだけど……」
それは次のような文章でした。「……人が宿命論を信ずれば、それだけで宿命は本物になってしまう。(……)いっそう明白なことは、民衆の全体が戦争が不可避だと信じれば、現実にそれはもう避けがたい。あまり人がしばしば通った道ではないが、辿る(たど)るのにそうむずかしくはない道がある。それは戦争を避けることが出来るということが真実になるためには、まず戦争が避け得ると信ずる必要があるという結論に到達するための道筋である。」
その訳を聞くと白柳君は、「いま君が訳した、戦争のところなんか、あの翻訳じゃ素通りだよ。その翻訳だと、戦争も生活の一つだ、地道に立向かって行け、ってことになるんだ、逆なんだ、本当は小林さんはこの原書を読んでないってことはないと思うんだけど」と語ったのです。
小林が2・26事件が起きた昭和11年に発表した「文学の伝統性と近代性」というエッセーで、「伝統は何処にあるか。僕の血のなかにある。若し無ければぼくは生きていないはずだ。こんな簡単明瞭な事実はない」と書くとともに、「僕は大勢に順応して行きたい。妥協して行きたい」とも記していたことを想起するならば、先の記述はアランの『精神と情熱とに関する八十一章』を大正6年に邦訳していた小林秀雄の戦争観に対する鋭い批判となっているでしょう。
しかも、皇紀2600年が祝われた昭和15年に鼎談「英雄を語る」で、「時に、米国と戦争をして大丈夫かネ」と作家の林房雄から問われて「大丈夫さ」と答え、「実に不思議な事だよ。国際情勢も識りもしないで日本は大丈夫だと言つて居るからネ」と楽観的な説明をした小林秀雄は、昭和17年には日本文学報国会評論随筆部会常任理事に就任していたのです。
一方、『若き日の詩人たちの肖像』の主人公が仏文科に転科への決意をしたのは、昭和15年秋のことでしたが、そこでは白柳君との会話などをとおして、日本では「商工省の通達があって、洋書の輸入は禁止された」が、「一九三五年にパリで行われた国際作家会議の記録によると、ドイツの作家代表は匿名は無論のこと、顔に覆面までをかぶって出て来るというひどい政治の有様」になっていたことなどが記されています。
この長編小説ではラジオから流れてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説が主人公の重要な転機になっていましたが、1933年1月にナチスが政権を握ったドイツでは「非ドイツ的な魂」に対する抗議運動が行われるようになり、5月10日のユダヤの知識人の書物を大量に焚書にした際にもゲッベルスが扇動的な演説をしていたのです。
 (ナチス・ドイツの焚書)
(ナチス・ドイツの焚書)
ドイツの公法学者ゲオルク・イェリネックの本も彼がユダヤ人であったために焚書の対象とされましたが、彼の著書『人権宣言論』を1906年に訳出していたのが「天皇機関説」事件でやり玉に挙げられることになる美濃部達吉だったのです。
そのために、1933年に相次いで国際連盟を脱退していた日本とドイツは、孤立を防ぐために相互の提携を模索して、2・26事件が起きた1936年の11月には日独防共協定が結ばれ、1940年9月には日独伊三国同盟が結ばれることになるのです。

(「仲良し三国」-1938年の日本のプロパガンダ葉書。写真は「ウィキペディア」より)
こうして、ナチス・ドイツへの接近の機運が日本で高まると美濃部の著書や学説は目障りとなり排斥された一方で、ドイツ国民のバイブル扱いを受けて終戦までに1000万部を売り上げたとされるヒトラーの『我が闘争』の訳はすでに1932年に内外社から『余の闘争』と題して刊行され、それ以降も終戦までに大久保康雄訳(三笠書房、1937年)、真鍋良一訳(興風館)(ともに日本の悪口を書いてある部分を削除しての出版)の訳などが刊行されました(「ウィキペディア」の記述などを参考にした)。
そして、小林秀雄も室伏高信訳の『我が闘争』(第一書房、1940年6月15日)の書評でヒトラーをこう讃美していたのです。「彼は、彼の所謂主観的に考へる能力のどん底まで行く。そして其処に、具体的な問題に関しては決して誤たぬ本能とも言ふべき直覚をしつかり掴んでゐる。彼の感傷性の全くない政治の技術はみな其処から発してゐる様に思はれる。/これは天才の方法である。僕は、この驚くべき独断の書を二十頁ほど読んで、もう天才のペンを感じた。」(太字は引用者)
問題はこのような記述をしていた小林秀雄が、戦後に「評論の神様」として復権するとアメリカとの安全保障条約で1960年5月に『文藝春秋』に掲載された「ヒットラアと悪魔」というエッセーでは『悪霊』にも言及しながら戦時中に書いた『我が闘争』の書評の内容を一部書き換えながら詳しく再掲し、「日本会議」などで代表委員を務めることになる小田村寅二郎に招かれて「全国学生青年合宿所」と銘打たれた研修会で5回も講演していたことです。
一方、『文学界』だけでなく『日本浪曼派』の同人にもなり、小林などとの鼎談で「負けたら、皆んな一緒にほろべば宣いと思つてゐる」と「一億玉砕」を美化するような発言をしていた林房雄も、「大東亜戦争肯定論」という題名で先の戦争を肯定する評論を『中央公論』に1963年から16回にわたって連載していたのです。
堀田善衞は復権した岸首相が「満州国の高級官吏」であったことを指摘して、1960年の事態を権力の「痙攣(けいれん)」と呼び、「自民党主流というものが満州事変以来」の「昭和史をむき出しのままで」うけついでいることがはっきりしたと書いていましたが(「新しい日本の出発点」)、元A級戦犯だった岸信介首相が結んだ「新安保条約」と「日米地位協定」では、後に明らかになるように施設の提供だけでなくアメリカ軍の特権も定められていました。
それゆえ、「マチネ・ポエティクス」の詩人の中村真一郎や福永武彦とともに堀田が書いた映画《モスラ》の原作『発光妖精とモスラ』では、当時の日本の政治状況を反映してネルソンが「外交特権でケースを開けさせずに小美人を連れ去った」ことも描かれていたのです。

その一因としては、反核的な要素も強い映画《ゴジラ》の後で映画《モスラ》を公開した本多猪四郎監督の戦争観も反映されていると思えます。彼は二・二六事件の際に将校に率いられた反乱部隊に所属していたために満州に送られ、軍に再召集されるなど苦労をしていたのです。
原作『発光妖精とモスラ』の著者の一人・堀田善衛が一九六〇年春に「私はつくづくと、ほとんど自分のこれまでの全生涯をさかのぼって再体験をするような思いにかられた」とも書いていることに留意するならば、復活した岸首相や「昭和維新」の再評価についての考察が、自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』の構想につながっていることはたしかだろう。
→『若き日の詩人たちの肖像』における「耽美的パトリオティズム」の批判(1)――真珠湾の二つの光景
→『若き日の詩人たちの肖像』における「耽美的パトリオティズム」の批判(2)――「海ゆかば」の精神と主人公
→『若き日の詩人たちの肖像』における「耽美的パトリオティズム」の批判(3、増補版)――小林秀雄の芥川龍之介観と『白痴』論の批判
(2019年5月1日、5月3日、青い字を加筆し最後の個所を次回に移動。リンク先と写真を追加、6月21日誤字を訂正)
 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)


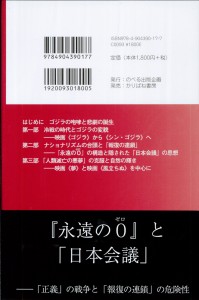


 (ナチス・ドイツの焚書)
(ナチス・ドイツの焚書)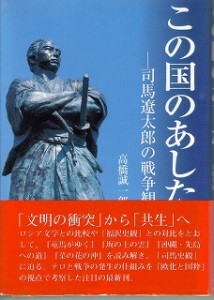


 (「ウィキペディア」より)
(「ウィキペディア」より)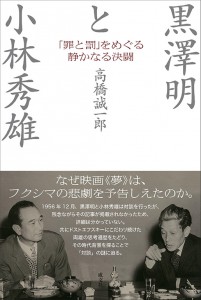
 写真の出典は奈良県立図書情報館。
写真の出典は奈良県立図書情報館。




