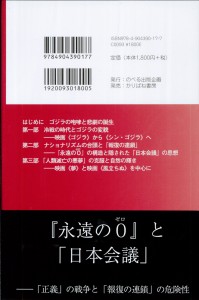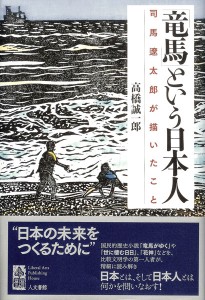(図版はアマゾンより)
(図版はアマゾンより)
三、清水幾太郎の核武装論と「日本会議」
「日本核武装論――清水幾多郎と西村真悟の間」と題された第三章では、1960年には「日米安保条約改定反対運動をリードした」社会学者・清水幾多郎が、1980年に『諸君!』7月号に載せた論文「核の選択」とそれについての反響が紹介されている。
その第一部「日本よ国家たれ」で「国家の本質は軍事力である」と書いた清水は、「世界はすでに核兵器という平面にのぼってしまっている」とし、「被爆国」の「日本こそが真先に核兵器を製造し所有する特権を有している」と記したのである(85~86)。
さらに「自衛隊の元最高幹部といっしょに組織」していた「軍事科学研究会」の名で書かれていた第二部では、「ソ連の脅威が強調され」、「航空・海上・陸上各方面の大幅な軍事増強」を提案していた。
興味深いのはこの論文が『諸君!』に掲載される経緯を清水自身が10月号で書いており、自費で3000部出版した「核の選択」を防衛庁長官と同庁幹部に送っただけでなく、右派団体の日本青年協議会にも2000部を送っていたと明らかにしていたことである(87)。
なぜならば、菅野完が『日本会議の研究』で明らかにしたように、学生運動で左翼と激しく戦った右翼の学生組織を母体とした「日本青年協議会」は現在、安倍政権を支える「日本会議」の「中核」となっており(同書、87頁)、かつては「日本の核武装をも検討すべき」と主張していた稲田朋美氏が防衛相に任命されているからである。
1960年には「反戦・平和の旗を掲げていた」清水の変貌に対しては「猪木正道、野坂昭如などさまざまな立場の知識人が反論」を書き、作家の山口瞳も清水の言説を「デマゴギー」と批判し、その頃はまだ「日本の核武装について総じて否定的な姿勢をとってきた」雑誌『正論』も、翌年には清水には「思想的主体」がないと批判した松本健一の論文などを集めた特集を組んでいた(91~92頁)。
軍事に関しては素人なので専門的な考察はできないが、広島や長崎での「被爆」だけでなく、広島型原爆の1000倍もの威力を持つ水爆ブラボーの実験で被爆した「第五福竜丸」事件だけでなく、前年の1979年にはアメリカでスリーマイル島原発事故が起きていた。
拙著『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の第一部では映画《ゴジラ》や《生きものの記録》などポピュラー文化との関連に注意を払いながら、「日本人の核意識の変化」について考察したが、水爆実験や原発事故なども踏まえて総合的に判断するならば、清水的な政策は19世紀には有効でありえたかもしれないが、核の時代にはむしろきわめて危険な思想に見える。
地殻変動によって国土が形成されて今も地震や火山の噴火が続いている日本においては、核兵器ばかりでなく、核エネルギーの危険性に対する認識の深まりと世界に反核の流れを作り出すことこそが、日本人の本当の意味での「安全保障」につがると思える。
一方、清水はすでに1963年に『中央公論』に論文を発表して、時代の変化に応じた「新しい歴史観」の必要性を唱えていたが(90)、「核武装の必要性」が声高に論じられて戦争の危機が煽られたことで、日本が行った「大東亜戦争」の評価などにも強い影響を及ぼしたようだ。
「空想と歴史認識」と名付けられた第9章で詳しく論じられているように、徐々に復古的な思想が強まる中で、文藝春秋の社長・池島信平が高く評価していた気骨のある歴史学者・林健太郎(1913~2004)は、1994年には雑誌『正論』誌上で「大東亜戦争は解放戦争だった」と主張する「日本会議」の小田村四郎や小堀桂一郎に「侵略戦争だった」との反論を行い、さらに「解放戦争」論者の中村粲(あきら)とも論争していた(380~388)
しかし、「新しい歴史教科書をつくる会」が活動を始めた1996、97年ごろから『諸君!』『正論』両誌の論文では、「反日」という言葉やレッテルをはりつけることが目立つようになったと指摘した著者は、1997年3月に「『自虐史観』を超えて」というテーマで開かれた「自由主義史観」を唱える「新しい歴史教科書をつくる会」の設立記念シンポジウムの模様を「完全収録」した『正論』は、その後は「つくる会の機関誌の様相」を呈するようになったと記している(389頁)。
本書の第2章では、「事実」を「報道」する新聞社でありながら、「産経新聞社には社史がない」ばかりでなく、「縮刷版もない」ことが指摘されていた。1962年の社説で「古い価値体系はくずれさり」と書いていたこの新聞の変質の一因は、「歴史」の軽視によるものであると思える。
1999年に「日本の核武装を国会で議論すべきだ」という発言を行った西村真悟が防衛政務次官を更迭されると産経新聞と『正論』はさらに復古的な論調を強めることとなった。
すなわち、西村真悟の発言に対しては自民党首脳だけでなく、朝日、毎日、読売の各紙も厳しい批判をしたが、産経新聞は「引責責任はやむを得ない」としながらも「憂国の思い」への理解を示した。西村を擁護した『諸君!』と『正論』の両誌は、「さらに熱心に西村を誌上に登場」させたのである(99~100)。
著者は2002年の「阿南大使、腹を切れ! 今こそ興起せよ、大和魂」など「『諸君!』に掲載された一連の対談の過激な題名を挙げているが、2008年に日本の国防を担う航空自衛隊制服組のトップにいた元航空幕僚長・田母神俊雄が「日本は侵略国家であったか」と題する論文で、「日本軍の軍紀が他国に比較して」も「厳正であった」などと書いたことが原因で更迭される波紋は『諸君!』『正論』両誌の論調にも及んだ。
著者によれば、この問題に対する「姿勢は対照的」であり、「「『諸君!』が田母神の主張を相対化してとらえ」、「田母神から距離をおいた」のに対し、『正論』は「田母神を全面的に擁護」していた(370)。
たとえば、2009年4月号の『諸君!』は、ニーチェの専門家でもある「新しい歴史教科書をつくる会」の西尾幹二が「彼の論文には一種の文学的な説得力もある。細かいことはどうでもいいんでね」と弁護したことに対して、対談者の現代史家・秦郁彦が「やはり、そうはいかんのですよ。田母神さんは私の著書からも引用しているが、趣旨をまったく逆に取り違えている」と厳しい批判をしていたことももきちんと掲載していた。
一方、『正論』は問題となった田母神の受賞論文をそのまま載せるとともに「朝日新聞の恐るべきダブルスタンダード」と題した論文で、「『思想』そのものを問題とし罷免にまで追い込むことになれば、これは明らかに、『思想信条の自由』の侵害であり、憲法違反である」と記した日本会議の常任理事で憲法学者・百地章の論文を載せていた(370)。
しかし、その批判は権力を振りかざして「電波停止」発言をして、「報道の自由」を脅かした高市総務相にこそ当てはまると思える。『正論』の読者投稿欄でデビューした稲田朋美・防衛相も、2005年の演説では「売国奴」という「憎悪表現」を用いて朝日新聞社を壇上から非難したが(第8章「朝日新聞批判の構造」)、その翌年に小説『永遠の0(ゼロ)』でデビューした百田尚樹も小説において新聞記者の高山をあからさまに貶し、後に安倍首相との共著『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』(ワック、2013年)に収められた対談ではそれが朝日新聞の記者であると明かしていた。
拙著『ゴジラの哀しみ』では、『永遠の0(ゼロ)』の思想的骨格には「自由主義史観」からの影響が強く見られることを具体的に示したが、その百田は田母神俊雄が2014年都知事選に出馬すると、NHK経営委員という立場でありながら複数回にわたって応援演説を行い、「この人は男だ」、「本当にすばらしい歴史観、国家観をおもちです」などと大絶賛したのである。
「カリスマの残影」と題された第7章「岸信介と安倍晋三を結ぶもの」では、『諸君!』や『正論』と安倍首相との関わりだけでなく岸元首相の「大東亜戦争観」が分析されており、『永遠の0(ゼロ)』で描かれている義理の祖父・大石と孫・健太郎との関係に注目しながら、この小説を読み解いていた私にとってことに興味深かった。
結語
以上、司馬遼太郎の研究者の視点から本書を読み解いてみた。できれば『諸君!』『正論』両誌における原発問題についての論文にもふれてもらいたかったが、政治史にはうとかった私にとっては両誌の論調の変遷をたどる過程で「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」との関係にもふれられている本書からは多くのことを知ることができた。
本書の第4章では「靖国神社と東京裁判」が、第5章では「A級戦犯合祀」などの重たい問題が考察された後で、第6章「永遠の敵を求めて」では論争のパターンが分析されている。それらは「国家神道」の問題とも深く関わるので機会を改めて考察したい。