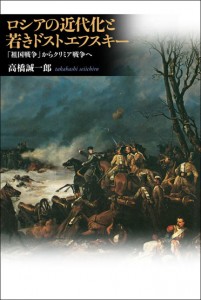一、 小林秀雄の『白痴』論と三種類の読者
小林秀雄氏の『白痴』論を何度か読み直す中で強い違和感を抱くようになった最初のきっかけは、小林氏が読者を「注意深い読者」と「多くの読者」、「不注意な読者」の三種類に分類していることであった(〔〕内のアラビア数字は、『小林秀雄全集』(第6巻、新潮社)のページ数を示す)。
すなわち、1934年9月から翌年の10月まで連載した「『白痴』について1」で、「ムイシュキンはスイスから帰つたのではない。シベリヤから還つたのだ」と繰り返し強調した小林氏は、「『罪と罰』の終末を仔細に読んだ人は、あそこにゐるラスコオリニコフは未だ人間に触れないムイシュキンだといふことに気が付くであろう」と書き〔82~83〕、さらに死刑について語った後でムィシキンが「からからと笑ひ出し」たことを、「この時ムイシュキンははや魔的な存在となつてゐる」と説明し、「作者は読者を混乱させない為に一切の説明をはぶいてゐる」ので、「突然かういふ断層にぶつかる。一つ一つ例を挙げないが、これらの断層を、注意深い読者だけが墜落する様に配列してゐる作者の技量には驚くべきものがある」と続けていた〔下線引用者、90~91〕。
これらの解釈には重大な問題があるが、1937年に発表した「『悪霊』について」で小林氏は「スタヴロオギンは、ムイシュキンに非常によく似てゐる、と言つたら不注意な読者は訝るかも知れないが、二人は同じ作者の精神の沙漠を歩く双生児だ」と断言して〔下線引用者、158~159〕、自分の読み方とは異なる読み方をする者を「不注意な読者」と決めつけていた。
この他に小林氏は、「夢の半ばで目覚める苦労は要らない」ような一般的な「多くの読者」にも言及している〔96〕。
そのような小林氏の読み方からは、人間を「非凡人」「凡人」「悪人」の三種類に分類していた知識人ラスコーリニコフの「非凡人の理論」との類似性が感じられ、小林氏の解釈に疑いを抱くようになったのである。
二、「沈黙」あるいは「無視」という方法
ここで注目したいのは、自分の読み方とは異なる読み方をする「不注意な読者」との論争の際に、小林氏が自分の気に入らない主張や相手の質問に対しては、「沈黙」という方法により無視して、自分の考えのみを主張するという方法をとっていたことである。
そのような方法が数学者の岡潔氏との対談『人間の建設』(新潮社)からも感じられる。ここでは具体的に引用することで、ムィシキンを好きだと率直に語っていた岡氏が、「専門家」の小林に言い負かされていく様子を分析することにする。
この対談が行われたのは、『「白痴」について』(角川書店)が単行本として発刊された1964年5月の翌年のことであり、10月に雑誌『新潮』に掲載された(〈〉内のアラビア数字は、文庫本『人間の建設』(新潮社)のページ数を示す)。
『白痴』が好きだった岡潔氏はこの対談で、「ドストエフスキーの特徴が『白痴』に一番よくでているのではないかと思います」とすぐれた感想を直感で語っていた〈85〉。
これに対して小林秀雄氏はなぜ岡氏がそう思ったかを尋ねることをせずに、「ドストエフスキーという人には、これも飛び切りの意味で、狡猾なところがあるのです」と早速、厳しい反論をしている〈87〉。それを聞いた岡氏が、「それにしてもドストエフスキーが悪漢だったとはしらなかった」と語ると、小林氏はさらに「悪人でないとああいうものは書けないですよ」と言葉を連ねて説明している。
それに対して岡氏は、「そうですか。悪人がよい作品を残すとは困ったのですな」という率直な感想を漏らしている〈90〉。
このような経過を読むと、一方的に自分の読み方を批判されている岡氏に同情したくなるが、小林氏は矛を収めずにさらに「『白痴』もよく読むと一種の悪人です」と発言して「不注意な読者」を戒め、「ムイシキン公爵は悪人ですか」と問いただされると、「悪人と言うと言葉は悪いが、全く無力な善人です」と言い直した小林氏は、前年に発行した『白痴』論で、「お終ひに、不注意な読者の為に注意して置くのもいゝだろう」という言葉の後の文言を繰り返すかのように次のように発言している。
「小説をよく読みますと、ムイシキンという男はラゴージンの共犯者なんです。ナスターシャを二人で殺す、というふうにドストエフスキーは書いています。…中略…あれは黙認というかたちで、ラゴージンを助けているのです」。
そして小林氏は、「これは普通の解釈とはたいへん違うのですが、私は見えたとおりを見たと書いたまでなのです」と文芸評論家としての権威を背景にして語り、こう諭している。
「作者は自分の仕事をよく知っていて、隅から隅まで計算して書いております。それをかぎ出さなくてはいけないのです。作者はそういうことを隠していますから」(下線引用者)。
これに対して自分のことを専門家ではない「多くの読者」の一人と感じていた岡氏は、「なるほど言われてみますと、私はただおもしろくて読んだだけで、批評の目がなかったということがわかります」と全面的に自分の読みの浅さを認めてしまっていた。
三、長編小説『白痴』の解釈とイワンの「罪」の「黙過」
ただ、岡氏は「悪人」が書いたそのような作品を「なぜ好きになったかという自分をいぶかっているのです」と続けていた〈100〉。ガリレオが裁判で自分の間違いを認めた後で「それでも地球は回る」とつぶやいたように、岡氏のつぶやきは重たい。果たして岡氏の読みは間違っていたのだろうか。
注目したいのは、「ドストエフスキーという人には、これも飛び切りの意味で、狡猾なところがあるのです」と語っていた文芸評論家の小林氏が、小説の構造の秘密を「かぎ出さなくてはいけないのです。作者はそういうことを隠していますから」と主張していたことである。
しかし、小林氏は本当に「作者」が「隠していること」を「かぎ出した」のだろうか、「狡猾なところがある」のはドストエフスキーではなく、むしろ論者の方で、このように解釈することで、小林氏は自分自身の暗部を「隠している」のではないだろうか。
このように感じた一因は、岡氏との対談でムィシキンを「共犯者」と決めつけた小林氏が、その後で『白痴』論から話題を転じて、ドストエフスキーは「もっと積極的な善人をと考えて、最後にアリョーシャというイメージを創(つく)るのですが、あれは未完なのです。あのあとどうなるかわからない。また堕落させるつもりだったらしい」と続けていたことにある(下線引用者)。
なぜならば、「『白痴』についてⅠ」で「キリスト教の問題が明らかに取扱はれるのを見るには、『カラマアゾフの兄弟』まで待たねばならない」と書いていた小林氏は、太平洋戦争直前の1941年10月から書き始めた「カラマアゾフの兄弟」(~42年9月、未完)では、「今日、僕等が読む事が出来る『カラマアゾフの兄弟』が、凡そ続編といふ様なものが全く考へられぬ程完璧な作と見えるのは確かと思はれる」と書き、「完全な形式が、続編を拒絶してゐる」と断言していたからである〔170〕。
よく知られているように、長編小説『カラマーゾフの兄弟』では自殺したスメルジャコフに自分が殺人を「指嗾」をしていたことに気づいたイワンが「良心の呵責」に激しく苦しむことが描かれている。一方、小林氏はこのことに触れる前に「カラマアゾフの兄弟」論を中断していた。
そのことを思い起こすならば、戦争中に文学評論家として「戦争」へと「国民」を煽っていたことを認めずに、「僕は政治的には無智な一国民として事変に処した」と戦後に発言していた小林氏は、イワンの「罪」を「黙過」するために今度は『カラマーゾフの兄弟』の解釈を大きく変えたのではないかとさえ思えるのである。
* * *
キューバ問題で核戦争の危機が起きた1962年の8月には、アインシュタインと共同宣言を出したラッセル卿の「まえがき」が収められている『ヒロシマわが罪と罰――原爆パイロットの苦悩の手紙』(筑摩書房)が発行されていた。
それから3年後の1965年に行われてアインシュタインとベルグソンとの関係も論じられたこの対談は、「原子力エネルギー」や「道義心」の問題も含んでおり、福島第一原子力発電所の大事故が起きた現在、きわめて重たいので、稿を改めて考察することにしたい。
リンク→「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(1)
リンク→「不注意な読者」をめぐってーー黒澤明と小林秀雄の『白痴』観
リンク→小林秀雄の原子力エネルギー観と終末時計