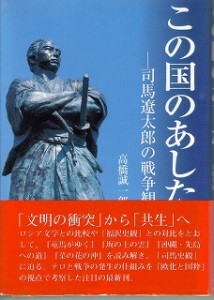リンク→「主な研究」のページ構成
はじめに
私がドストエフスキーの作品と出合ったのは、ベトナム戦争が行われていた高校生のころで、原子爆弾が発明され投下されるなど、兵器の近代化によって五千万人もの戦死者を出した第二次世界大戦の後も戦争が続けられることに憤慨して、私は宗教書や哲学書、さらに文学書を学校の授業もおろそかにして読みふけって価値観を模索していた。
それゆえ、長編小説『罪と罰』や『白痴』を読んだ際には、社会状況をきちんと分析しながら、自己と他者の関係を深く考察することで個人や国家における「復讐の問題」を極限まで掘り下げているこれらの作品は、「殺すこと」が正当化されている状況を根本的に変える力になると思えたのである。そして、そのような思いから戦後も高く評価されていた小林秀雄のドストエフスキー論も一時期、熱心に読んだ。
1,情念の重視と神話としての歴史――小林秀雄の歴史認識と司馬遼太郎
しかし、私がロシア文学ではなく文明学を研究対象とした理由の一端は、一九三五年から一九三七年にかけて雑誌『文學界』に連載されていた小林秀雄の『ドストエフスキイの生活』の冒頭におかれていた「歴史について」と題された「序」にあった。
この「序」で、「歴史は神話である。史料の物質性によつて多かれ少かれ限定を受けざるを得ない神話だ」と規定した小林は、「既に土に化した人々を蘇生させたいといふ僕等の希ひと、彼等が自然の裡に遺した足跡との間に微妙な均合が出来上る」とし、「歴史とは何か、といふ簡単な質問に対して、人々があれほど様々な史観で武装せざるを得ない所以である」とし、「一見何も彼も明瞭なこの世界は、実は客観的といふ言葉の軽信或は過信の上に築かれてゐるに過ぎない」と記していた((下線引用者、『小林秀雄全集』第五巻、新潮社、一九六七年、一四~一六頁。引用に際しては、旧漢字は新漢字に改めた。)。
この『ドストエフスキイの生活』が発表されていた一九三六年に日本はロンドン軍縮会議からの脱退を宣告し、一九三七年からは太平洋戦争に直結することになる日中戦争が始まっていたが、「僕は本質的に現在である僕等の諸能力を用ひて、二度と返らぬ過去を、現在のうちに呼び覚ます」と記した小林は、「僕は一定の方法に従つて歴史を書かうとは思はぬ」と宣言し、「立還るところは、やはり、さゝやかな遺品と深い悲しみとさへあれば、死児の顔を描くに事を欠かぬあの母親の技術より他にはない」と情緒的な言葉で自分の「方法」の特徴を示し、「要するに僕は邪念といふものを警戒すれば足りるのだ」という言葉で「序」を結んでいた。
こうして、この「序」で「自然」や「歴史」の問題に言及しながら、自分の方法の特徴を端的に記した小林は、「自分の情念」を大事にしながら、自分の選んだ作品の主人公や主要な登場人物について考察している。しかし、青年に達した「死児」はすでに自分独自の交友関係を有しているのであり、いかに子供を深く愛していても「母親」の「情念」だけでは、「死児」の全体像を描き出すのは難しいと思われる。
実際、日本では恋愛小説として理解されている長編小説『白痴』では、貧富の格差や貴族たちのモラルの腐敗の問題が、きわめて鮮明に描き出されているが、小林秀雄の『白痴』論ではこれらの問題にはほとんど言及されていない。
最初はこのことを不思議に感じたが、「四民平等」を謳った明治維新後に導入された「華族制度」は、帝政ロシアの貴族制度とも似ていたので、『白痴』に描かれているこれらの問題に言及することは、日本の華族制度の批判とみなされる危険性があったのである。しかも問題は、戦後になって厳しい検閲制度が廃止された後でも小林が自分の『白痴』観を変えなかったことである。
それゆえ、そのような小林秀雄の歴史認識に疑問を感じていた私は、帝政ロシアの問題をきちんと分析していない小林秀雄のドストエフスキー論が戦後も高く評価されていることに深い危機感を抱いた。なぜならば、クリミア戦争の敗北後に帝政ロシアでは、農奴制の廃止や言論の自由などの「大改革」が行われたが、しかし自分たちの利権が失われることを嫌った貴族たちによって改革は骨抜きにされて再び厳しい言論統制がおこなわれるようになり、露土戦争での勝利や日露戦争での敗戦を経て革命にいたっていたからである。
一方、司馬遼太郎は『昭和という国家』(NHK出版、一九九八年)の「買い続けた西欧近代」と題された第九章で、真珠湾攻撃の後に行われた「近代の超克」という座談会に「当時の知識人の代表者」だった小林秀雄も参加していたことを紹介し、「小林秀雄さんを尊敬しております」と断りつつも、このときの座談会については「太平洋戦争の開幕のときの不意打ちの成功によっても、日本のインテリは溜飲を下げた」ときわめて厳しい批判を投げかけていた。
このことに注目しながら、戦争中に書かれた小林の「歴史と文学」や「疑惑 Ⅱ」というエッセーを読むと、芥川龍之介の『将軍』観や菊池寛の『西住戦車長伝』観が、司馬遼太郎の見方とは正反対であることに気づく。(リンク→)最後に戦時中に書かれた「歴史と文学」における小林の歴史認識と司馬遼太郎との違いを確認することで、これまで矮小化されてきた司馬遼太郎の「文明史家」としての大きさを明らかにしたい。
2、小林秀雄の「隠された意匠」と「イデオロギーフリー」としての司馬遼太郎
「歴史と文学」の第一章で小林秀雄は、「歴史は繰返すという事を、歴史家は好んで口にする」が、「歴史は決して二度と繰返しはしない。だからこそ僕等は過去を惜しむのである。歴史とは、人類の巨大な恨みに似てゐる。歴史を貫く筋金は、僕等の愛情の念といふものであって、決して因果の鎖といふ様なものではないと思ひます」と記していた。
そして、「大正以来の日本の文学は、十九世紀後半のヨオロッパ文学の強い影響」下にあることを指摘し、「作家たちによる、人間性といふものの無責任な乱用」や、唯物史観の影響下にある文学を批判した小林秀雄は、『大日本史』の列伝では「様々な人々の群れが、こんなに生き生きと跳り出す」ことを指摘して、作家たちが「腕に縒りをかけて、心理描写とか性格描写とかをやつてゐる」、「現代の小説」のつまらなさを糾弾していた(二一七頁)。
さらにこの文章の末尾で「僕は、日本人の書いた歴史のうちで、『神皇正統記』が一番立派な歴史だと考えてゐます」とも記した小林は、この書を小田城などの陣中で書いた北畠親房が「心性明らかなれば、慈悲決断は其中に有り」と記していることに注意を促して、物事を判断する「悟性」よりも「心性を磨くこと」の大切さを強調し、「この親房の信じた根本の史観は、今もなほ動かぬ、動いてはならぬ」と主張していた。
一方、『竜馬がゆく』(文春文庫)には「歴史こそ教養の基礎だ」とする武市半平太が、宋の学者司馬光が編んだ「古代帝国の周の威烈王からかぞえて千三百年間の中国史」を描いた「編年体」の『資治通鑑(しじつがん)』を自分が教えると誘うが、坂本竜馬はこの提案を断って漢文で書かれたこの難解な歴史書を我流で読んで、書かれている事実を理解するという場面が面白おかしく描かれていた(第二巻・「風雲前夜」)。
このエピソードは一見、竜馬の直感力の鋭さを物語っているだけのようにも見えるが、「イデオロギーフリー」としての司馬の歴史観を考えるうえではきわめて重要だろう。なぜならば、『竜馬がゆく』において幕末の「神国思想は、明治になってからもなお脈々と生きつづけて熊本で神風連(じんぷうれん)の騒ぎをおこし、国定国史教科書の史観」となったと記した司馬は、さらに「その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」と痛烈に批判しているからである(第三巻・「勝海舟」)。
実は、作家の海音寺潮五郎が司馬との対談『日本の歴史を点検する』(講談社文庫)で語っているように、古代の中国の歴史観では自国を世界の中心と見なす「中華思想」が強く、ことに漢民族が滅亡するかもしれないという危機の時代に編まれた『資治通鑑』には、「尊王攘夷」や「大義名分」などの考え方が強く打ち出されていた。そして司馬は、南北朝の時代に『神皇正統記』を著した北畠親房を「中国の宋学的な皇帝観の日本的翻訳者」と位置づけているが、危機的な時代に著された『神皇正統記』にはそのような「尊王攘夷」史観が強く、徳川光圀が編纂した『大日本史』もそのような見方を強く受け継いでいたのである。
しかも、「歴史と文学」の第一章で、「歴史は繰返すという事を、歴史家は好んで口にする」が、「歴史は決して二度と繰返しはしない」と記していた小林秀雄は、敗戦後の一九四六年に行われた座談会で、トルストイ研究者の本多秋五から戦前の発言を問い質されると、「僕は政治的には無智な一国民として事変に処した。黙って処した。それについては今は何の後悔もしていない」と語っていた。
この発言について司馬は何も言及していない。しかし、満州の戦車隊で「五族協和・王道楽土」などのイデオロギーというレンズの入った「窓」を通してみることの問題点を痛感した司馬は、もし戦場から生きて帰れたら「国家神話をとりのけた露わな実体として見たい」と思うようになり、この「露わな実体」に迫るために「自分への規律として、イデオロギーという遮光レンズを通して物を見ない」という姿勢を課していた(「訴える相手がないまま」『十六の話』)。
そして、ノモンハン事件の研究者クックから戦前の日本では、国家があれほどの無茶をやっているのに、国民は「羊飼いの後に黙々と従う」羊だったではありませんかと問われた司馬は、「日本は、いま世界でいちばん住みにくい国になっています。そのことを、ほとんどの人が感じ始めている。『ノモンハン』が続いているのでしょうな」と答えていたのである。(「ノモンハンの尻尾」『東と西』朝日文庫)。
司馬遼太郎は「唯物史観」の批判者という側面のみが強調されることが多いが、「大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」、「尊王攘夷史観」の徹底した批判者でもあったのである。
青年のころに「神州無敵」といったスローガンに励まされて学徒出陣したことで、「イデオロギーにおける正義というのは、かならずその中心の核にあたるところに、『絶対のうそ』」があります」と書いている(「ブロードウェイの行進」『「明治」という国家』NHK出版)。国家が強要する「”正義の体系”(イデオロギー)」によってではなく、世界史をも視野に入れつつ自分が集めた資料や隣国の歴史などとの比較によって日本史を再構築しようとした司馬遼太郎の試みは壮大だったということができるだろう。
さらに、「二十一世紀に生きる君たちへ」という自分の文明観を分かりやすく子供たちに語りかけた文章で、「私ども人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考え」の必要性を訴えた司馬は、「今は、国家と世界という社会をつくり、たがいに助け合いながら生きている」ことを強調し、「自国」だけでなく「他国」の文化や歴史をも理解することの重要性を明確に示していた(『十六の話』)。
分かりやすい文章で書かれた司馬遼太郎の長編小説では、描かれている個々の人物も屹立した樹木のように見事なので、一部分だけが引用されると誤解されることが多いが、その全体像は鬱蒼たる森のように奥深く、彼の文明観は厳しい形で幕が開いた二十一世紀のあり方を考える上でもきわめて重要だと思える。
(〈司馬遼太郎と小林秀雄――「軍神」の問題をめぐって〉『全作家』第90号、2013年より、歴史認識の問題を独立させ、それに伴って改題した)。
リンク→司馬遼太郎と小林秀雄(2)――芥川龍之介の『将軍』をめぐって