子規の青春と民主主義の新たな胎動(改訂版)
今回の拙著『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』(人文書館)では正岡子規を主人公として新聞『日本』を創刊した恩人・陸羯南との関わりや夏目漱石との友情をとおして『坂の上の雲』を読み解きました。
そのことにより「新聞紙条例」による日本の言論弾圧と帝政ロシアの検閲との比較や、「正教・専制・国民性」を強調することによって帝政ロシアの独自性を訴えた1833年の「ウヴァーロフの通達」が出された後に作家活動に入ったドストエフスキーと「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と説いた「教育勅語」が「憲法」が施行される前月に発布された後の子規や漱石との類似性をより具体的に分析することができたのではないかと考えています。
なぜならば、日本は明治時代に自由民権運動の高まりをとおして強力な薩長藩閥政府を追い詰めて、国会を開設するという約束を明治一四年に獲得したという歴史を持っているからです。
そのような時期に青春を過ごした子規は松山中学校の生徒の時に、「国会」と音の同じ「黒塊」をかけて立憲制の急務を説いた「天将(まさ)ニ黒塊ヲ現ハサントス」という演説を松山中学校で行い、その後に叔父の加藤拓川をたよって上京しました。そして、「栄達をすてて」新聞記者となった子規は、文芸の道に邁進して日本の伝統的な俳句を再発見しただけでなく、分かりやすい日本語で一人一人が自分の思いを語れるように俳句の改革を行っていました。
そして、この長編小説を書く中で近代戦争の発生の仕組みを分析し、機関銃や原爆など近代兵器の問題を考察していた司馬氏も、「日本というこの自然地理的もしくは政治地理的環境をもった国は、たとえば戦争というものをやろうとしてもできっこないのだという平凡な認識を冷静に国民常識としてひろめてゆく」ことが、「大事なように思える」とも明確に記していたのです(以下、太字は引用者。「『「大正生れの『故老』」『歴史と視点』)。
* * *
これまで『坂の上の雲』については何冊かの拙著で論じてきましたので、簡単に今回の著書に至る流れをふりかえることで、問題点を確認しておきたいと思います。
学生の頃に『竜馬がゆく』を読んで魅力的な人物描写だけでなく、国際的な広い視野に支えられた壮大な構想を持つ司馬作品に魅せられていた私が強い衝撃を受けたのは、司馬遼太郎氏が一九九六年に亡くなられた後で起きたいわゆる「司馬史観」論争でした。この小説を賞賛する人だけでなく、批判する人の多くが『坂の上の雲』では戦争を肯定的に描かれていると解釈していることでした。
しかし、夏目漱石は日英同盟の締結に沸く日本をロンドンから冷静に観察していましたが、司馬氏も『坂の上の雲』において「自国の東アジア市場を侵されることをおそれ」たイギリスが同盟国の日本に求めたのは、「ロシアという驀進(ばくしん)している機関車にむかって、大石をかかえてその前にとびこんでくれる」ことだと書いていました(六・「退却」)。
それゆえ、「戦争する気概」を持っていた明治期の人々が『坂の上の雲』では描かれているとする解釈に強い危機感を感じた私は、自分で司馬論を書くしかないと思い、『竜馬がゆく』から『坂の上の雲』を経て、『菜の花の沖』に至る司馬作品の流れを分析した『この国のあした――司馬遼太郎の戦争観』(のべる出版企画)を二〇〇二年に上梓しました。
さらに、『坂の上の雲』の映像化について「この作品はなるべく映画とかテレビとか、/そういう視覚的なものに翻訳されたくない作品であります」と司馬氏が記述していたにもかかわらず(『「昭和」という国家』日本放送出版協会、一九九八年)、NHKがこの作品の大河ドラマを放映しようとしていることを知り、急遽、『司馬遼太郎の平和観――「坂の上の雲」を読み直す』(東海教育研究所)を二〇〇五年に発行しました。
この著書ではトルストイの『戦争と平和』が『坂の上の雲』にも強い影響を与えていることを明らかにするために、司馬遼太郎が精読していた徳冨蘆花のトルストイ観や蘆花が鋭く批判した兄・徳富蘇峰の戦争観などとの詳しい比較を行いました。また、日露の戦略の比較や将軍たちの心理描写の分析をとおして『坂の上の雲』における法律や教育や軍事、さらに情報の問題についても考察しました。
* * *
『坂の上の雲』において司馬氏は一九世紀末を「地球は列強の陰謀と戦争の舞台でしかない」と規定していましたが、二一世紀の初めに「同時多発テロ」が起ると、核兵器の先制使用も示唆したブッシュ政権はアフガンに続いてイラクでも「大義なき戦争」に突入し、一時はアメリカが一方的に勝利したかに見えましたが、そのイラクからはテロをも厭わないIS(イスラム国)が誕生し、今世紀の国際情勢はこれまで以上に複雑な様相を見せ始めています。
そして、地球上で唯一の被爆国であるという重たい事実の上に定着していた「憲法」を持つにもかかわらず日本でも、「報復の権利」を主張するアメリカの戦争に引きずられるようにして、今年の九月に自衛隊の派兵を可能とする「安保関連法」が成立しました。
一方、『坂の上の雲』執筆中の一九七〇年に「タダの人間のためのこの社会が、変な酩酊者によってゆるぎそうな危険な季節にそろそろきている」ことに注意を促していた司馬氏は(「歴史を動かすもの」『歴史の中の日本』中央公論社、一九七四年、一一四~一一五頁)、「政治家も高級軍人もマスコミも国民も、神話化された日露戦争の神話性を信じきっていた」と書いていました(太字は引用者。「『坂の上の雲』を書き終えて」)。
さらに司馬氏は言葉を継いで、幕末期だけでなく昭和初期をも視野に入れつつ、「尊皇攘夷」などのイデオロギーに酔って自分の眼で事実を見ない人々を次のように厳しく批判していたのです。
「自国や国際環境についての現実認識をうしなっていた。日露戦争の勝利はある意味で日本人を子供にもどした。その勝利の勘定書が太平洋戦争の大敗北としてまわってきたのは、歴史のもつきわめて単純な意味での因果律といっていい」。
現在の日本は「立憲主義」の根幹が揺らぎ、「明治憲法」さえなかった時代に逆戻りする危険性のある「文明の岐路」に立たされているように見えます。
ただ、このような事態に際して学生団体シールズが「民主主義ってなんだ」と若々しい行動力で問いかけ、それに呼応するかのように「学者の会」などさまざまの会や野党が立ち上がった今回の動きを見ている中で、私は民主主義の新たな胎動が始まっていると感じました。
来年は私が司馬作品の考察を本格的に始めてから二〇年目になりますが、その前夜に文明論的な視野の面で多くの示唆を受けていた司馬氏の学恩に答えることができる書をなんとか発行することができ、嬉しく感じています。
「白い雲」を目指して苦しい坂を登った子規など、明治の「楽天家」たちの青春に焦点を当てて『坂の上の雲』を読み解いた『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』(人文書館)が、私と同世代の愛読者だけでなく、新しい時代を模索する現代の若者にも子規たちの若々しいエネルギーを伝えることができればと願っています。
(2017年10月6日、書影を追加し加筆。11月5日、改訂)
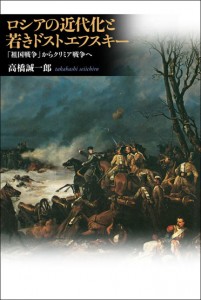
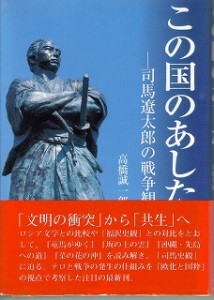


コメントを残す