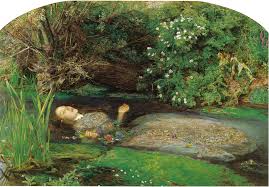中編『生きよ、そして記憶せよ』(一九七四)と『火事』(一九八五)でソ連邦国家賞を二度受賞し、二〇〇〇年にはソルジェニーツィン賞を受賞した農村派の作家ラスプーチンが昨年の三月に亡くなった。 その報を受けて、 作家とは個人的にも旧知の間柄であり、『病院にて ソ連崩壊後の短編集』(群像社、二〇一三)の訳書もある大木昭男氏がこれまでの論稿をまとめたのが本書である。
作家の小説だけでなく、ルポルタージュや「我がマニフェスト」をも視野に入れた本書は、作家の全体像を把握できるような構成になっている(本稿では著者の表記「ドストエーフスキイ」で統一した)。
第一章 ロシア独自の道とインテリゲンチヤ
第二章 モスクワ騒乱事件直後のラスプーチン
第三章 ドストエーフスキイとラスプーチン――「救い」の問題試論
第四章 ラスプーチン文学に現れた母子像
第五章 ロシア・リアリズムの伝統とラスプーチン文学
第六章 失われた故郷への回帰志向―小説のフィナーレ
第七章 ラスプーチン文学に見る自然 エピローグ――「我がマニフェスト」翻訳とコメント
ドストエーフスキイとの関連で注目したいのは、「わたしはここ十年間ドストエーフスキイを何回も読み返しています」と一九八六年に語ったラスプーチンが、「ドストエーフスキイはわたしにとってどういう作家であるかといえば、気持ちの上で一番近い存在であり、精神的にもっとも影響を受けた作家であるという答えが一番正しい答えになると思います」と続けていたことである(第三章)。
この言葉を紹介して、ラスプーチンの「精神の中核にはやはり正教の人間観が厳然と在る」と指摘した大木氏は、「ドストエーフスキイの提唱した『土壌主義』は、『母なる大地』と融合したプーシキン文学の伝統を継承したもの」であり、「その伝統を現代において受け継いだ作家こそワレンチン・ラスプーチンなのである」と主張している(第四章)。
ただ、本書に収録されている作家の略年譜によれば、ラスプーチンが洗礼を受けたのは中編『マチョーラとの別れ』(一九七六)の後の一九八〇年のことだったことがわかる。では、なぜラスプーチンはこの作品の後で正教徒となったのだろうか。ここでは中編『火事』(一九八五)とドストエーフスキイの作品との関係を詳しく分析した第三章を中心に、この作品に至るまでとその後の作品を分析した著者の考察を追うことで、ラスプーチンのドストエーフスキイ観に迫ることにしたい。
* * *
一九三七年三月に今はダムの底に沈んだシベリアの小さな村に生まれたラスプーチンは、ナチス・ドイツとの「大祖国戦争」の苦しい時期に少年時代を過ごし、大学卒業後は新聞記者として勤めながら小説も書き始めた。 「ソ連崩壊後、国民の実に六〇%が貧困層に転落し、とりわけ年金生活者の多くが医療にもかかれないまま路頭に迷った。
ラスプーチンはそのような悲惨な現実をよく見据えている」と指摘した大木氏は、彼の作品を貫く方法について、ドストエーフスキイの第一作『貧しき人々』にも言及しながら、「ここにわたしは、一九世紀以来のロシア・リアリズムの伝統を感ずる」と書いている(第五章)。
「小説のフィナーレ」に注目しながらラスプーチンの主な作品を分析した第六章は、現実をしっかりと見つめて描くリアリズムが初期の段階からあったことを示すとともに、ドストエーフスキイの「土壌(大地)主義」への理解の深まりをも示していると思える。
すなわち、中編『マリヤのための金(かね)』(一九六七)では、コルホーズ議長の要請で小売店の売り子として勤めたが、決算時になって千ルーブルもの不足金があることが判明するという事件が発生し、不正などするはずのない純朴な農婦マリヤとその夫が苦境に陥るという出来事をとおして、「昔ながらの共同体的な相互扶助の精神」が廃れつつある状態が描かれている。
中編『アンナ婆さんの末期』(一九七〇)でも、村で百姓として一生を過ごしたアンナ婆さんの臨終の場面をとおして、村に残った子供と村を出て行った子供たちとの関係が描かれており、「夜中、婆さんは死んだ」という最後の文章に注意を促した大木氏は「寿命のつきた一個人の死ではあるが、もっと大きなものの死を暗示しているように思われる」と記している。
そのテーマは「大祖国戦争」で勇敢に戦って負傷したグシコフが、快復したあとで再び戦場に送られることを知って脱走したために、「故郷への回路」を断ち切られてしまうという悲劇を描いた中編『生きよ、そして記憶せよ』(一九七四)や、壮大なダム建設のために水没させられることになったためにアンガラ河の中州の島退去を迫られた農民たちの悲劇を描いた中編『マチョーラとの別れ』(一九七六)でも受け継がれている。
注目したいのは、島の名前の「マチョーラ」が「母」を意味する「マーチ」という単語から作られた固有名詞であると指摘した大木氏が、『マチョーラとの別れ』という題名は、「母なる大地」との別れも示唆していることに注意を促していることである。
ラスプーチンが洗礼を受けた後で書かれた中編『火事』(一九八五)では、ダムの建設によって水没した故郷の村を去り林業に従事することになった主人公イワンが、林業場倉庫の火事の現場で目撃した出来事が描かれている。 この 作品が「『マチョーラとの別れ』の続編とも言うべきもの」であると指摘した大木氏は、火事場で見た「無秩序な光景」について考え始めたイワンの思索が、「自分の内部の無秩序についての内省へと移っていく」ところに、ドストエーフスキイの手法との類似性を見ている。
注目したいのは、この小説のラストシーンで描かれている、「彼は今小さな林の陰に回り、永遠に姿を消してしまうのだ」という「謎めいた表現」は、「主人公の別世界への新たな旅立ちを意味するシーンである」と著者が解釈していることである。 訳出されている「あたかも夜の災厄のために苦しんでいたかのように、静かでもの悲しい秘められた大地がやわらかな雪の下に横たわっていた」という文章から、最後の「大地は沈黙している。/おまえは何であるのか、無言の我が大地よ、おまえはいつまで沈黙しているのか?/本当におまえは沈黙しているのか?」という詩的な文章に至る箇所は、ラスプーチンにおける「土壌(大地)主義」の重みを象徴的に物語っているように思える。
『罪と罰』のエピローグでも「一つの世界から他の世界への漸次的移行」が示唆されていることに注目した著者は、『カラマーゾフの兄弟』でも「ガリラヤのカナ」の章では、「天地を眺めて神の神秘にめざめ、大地を抱擁し、泣きながら接吻する」というアリョーシャの体験が描かれていることを指摘して、中編『火事』の結末においても、「キリスト教的な『過ぎ越し』」が描かれていると主張しているの である(第三章)。
残念ながら日本ではドストエーフスキイ作品を自分の主観でセンセーショナルに解釈する著作の人気が高いが、ドストエーフスキイが一八六四年に書いたメモで人類の発展を、一、族長制の時代、二、過渡期的状態の文明の時代、三、最終段階のキリスト教の時代の三段階に分類していたことを指摘した大木氏は、『白痴』における「サストラダーニエ(共苦)」や「美は世界を救う」という表現の重要性を強調している。
実際、著者が指摘しているように、『白痴』の創作ノートでもムイシキンが「キリスト教的愛の感情に従って行動することを、ナスターシャ・フィリポヴナの救済と彼女の世話と見なして」おり、「長編における三つの愛」が「情熱的直接的愛――ロゴージン」、「虚栄心からの愛――ガーニャ」、そして「キリスト教的愛――公爵」であると明確に定義されているのである。
それゆえ、ラスプーチンが「魂の動きにおいては、ロシア的スタイルは、沢山の苦しみをなめた人へのサストラダーニエであり、思いやりであり」、「共同性である」と書いていることに注意を促した大木氏は、「この認識はドストエーフスキイの民衆観を継承している」と記している。
本書の構成は論文の執筆順になっているので最初に置かれているが、「ロシア独自の道とインテリゲンチヤ」と題された章では、一九九二年のインタビューで「今は検閲がなく、自由がありますが、文学がありません」と語ったラスプーチンの言葉を紹介しつつ、「欧米流マス文化」の氾濫による「精神的空虚と不安定の兆候」を指摘した大木氏は、異文化に対しても排他的な態度を取らない「文化的民族主義」を唱える作家の立場を「新スラヴ派」と位置づけている(第一章)。
短編『同じ土の中に』(一九九五)で「ソ連崩壊後のロシアは、またしても革命前の現実とほとんど同様の貧困と格差の社会になってしまった」ことを描き出したラスプーチンが、一九九七年に「我がマニフェスト」で『カラマーゾフの兄弟』にも言及しながら、「ロシアの作家にとって、再び民衆のこだまとなるべき時節が到来した。痛みも愛も、洞察力も、苦悩の中で刷新された人間も、未曾有の力をもって表現すべき時節が」と宣言したのは、このような時代的な背景によるものだったのである(エピローグ)。
最後の中編『イワンの娘、イワンの母』(二〇〇三)を考察した論文の冒頭で「ロシアの『母子像』といえば、先ず思い浮かべるのは、幼児イエスとその母マリヤの二人が描かれている聖母子イコンであろう。それは慈愛のシンボルであり、キリスト教的『救い』のイメージと結びついている」と記した大木氏は、「イワン」という名前が「ヨハネ」に由来しており、「イワンの日」と呼ばれる民衆的な祭りがあるほどこの名前はロシア人の間ではきわめてポピュラーで、ロシア正教会ではこの日が「洗礼者ヨハネの誕生日」とされていることも説明している(第四章)。
そして、「ロシア社会の重要な、最も救済力に富んだ革新は、勿論、ロシア人女性の役割に属する」とドストエーフスキイが『作家の日記』に書いていたことを紹介した著者は、「ロシア人女性の大胆さ」が描かれているこの小説は「『我がマニフェスト』の意欲的実践の作として評価されるべき」と書いている。 ラスプーチンの小説を高く評価した文化学者のリハチョーフが「文化環境の保護も自然環境の保護に限らず本質的な課題です」と書いていたことに関連して、ドストエーフスキイの「美は世界を救う」という表現にも言及した大木氏は、「その『美』とは、人間の精神的な美を意味する言葉であるが、自然環境の美が保たれてこそ、人間精神の美も育まれてゆくものであろう。ラスプーチンはそのような認識にもとづいて『バイカル運動』をはじめとする自然保護運動を積極的に展開してきたのであった」と続けている(第七章)。
中編『マチョーラとの別れ』論で大木氏は、経済的な観点からの「ダムの建設は環境破壊をもたらし、そこで暮らしている住民たちの土地と結びついた過去の記憶を奪うことになる」と指摘していたが、それは三・一一の大事故による放射能で故郷から追われた福島の人々にもあてはまるだろう。
国民には秘密裏に行われて成立したTPPの交渉では農業分野で大幅な譲歩をしていたことが明らかになり、近い将来日本でも農村の疲弊と大地の劣化が進む危険性が高い。 ラスプーチンの「民族主義」的な主張には違和感を覚えるところもあるが、シベリアの小さな村の出来事などとおしてロシアの厳しい現実を丹念に描き出したラスプーチンの小説が、「土壌(大地)主義」を唱えたドストエーフスキイの精神を受け継いでいることを明らかにした本書の意義は大きい。
(『ドストエーフスキイ広場』第25号、2016年、108~112頁)。
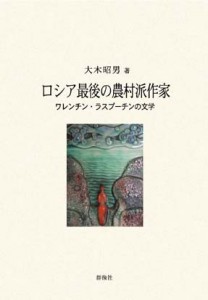

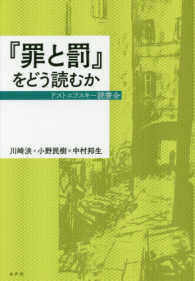

![ロマノフ王朝の最期【デジタル完全復元版】 [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/417WP62DGDL._SY445_.jpg)