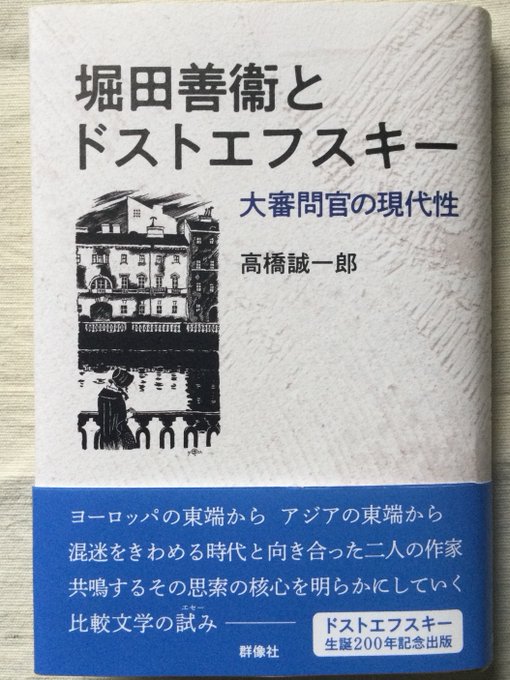はじめに
ロシアと日本の近代化の類似性に注目して司馬遼太郎の2・26事件観にふれていた「司馬遼太郎のドストエフスキー観」(『ドストエーフスキイ広場』第12号、2003年)を、旧かなづかいと旧字を現代の表記に改めるなど文体を一部修正し 、 註を本文中の()内に記す形で再掲する。なお、本稿では敬称は略した。

一、昭和初期の「別国」とニコライ一世の「暗果の三〇年」
「自国に憲法があることを気に入っていて、誇りにも思っていた」若き司馬遼太郎は、「外務省にノンキャリアで勤めて、どこか遠い僻地の領事館の書記にでもなって、十年ほどして、小説を書きたい」という自分の人生計画を持っていた*1。しかし太平洋戦争の最中、文化系の学生で満二十歳を過ぎている者はぜんぶ兵隊にとるということ」になった時、自国の憲法には「徴兵の義務がある」ことが記されていることも知って、司馬は「観念」したのであった(「あとがき」『この国のかたち』Ⅴ)*2。
しかも学徒出陣で彼が配属されたのは、満州の戦車隊であった。司馬は後に戦車について「悲しいほど重要なことは、あれは単なる機械ではなく、日本国家という思想の反映、もしくは思想のカタマリであった」と記して、「無敵皇軍とか神州不滅とかいう」用語によって、「自国」を「他と比較すること」を断った当時の日本を厳しく批判した。つまり日本軍の戦車は「敵よりもはるかに鋼材が薄く、砲が敵にかすり傷も与えることができないほどに小さすぎた」ので、「敵戦車が出現した瞬間が私の死の瞬間になる」ことを意味していた。そして、敵の強力な戦車とは、ロシア(ソ連)の戦車に他ならなかったのである。
司馬は戦車の閉ざされた空間の中で「国家とか日本とかいうものは何かということ」を考え込んでいるうちに、「むこうの外界にあらわれたのは敵の戦車ではなく、…中略…成立後半世紀で腐熱しはじめた明治国家が、音をたてて崩れてゆく」という幻影を見、もし生きて帰れたら「明治国家成立の前後や、その成立後の余熱の限界ともいうべき明治三十年代というものを、国家神話をとりのけた露わな実体として見たいという関心をおこした」と記している。 明治国家の「露わな実体」に迫ろうとした司馬は、同時に自分に死を宣告する筈だったロシアの「露わな実体」をも明らかにしたいと思った筈であり、このことが司馬に日露戦争を主題とした『坂の上の雲』を書かせたといっても過言ではないだろう。
ところで、司馬遼太郎が深く尊敬していた福沢諭吉は、一八七九年に書いた『民情一新』で、日本に先駆けてロシアの「文明開化」を行ったピョートル大帝の改革を高く評価した。その一方で彼は、西欧の「良書」や「雑誌新聞紙」を見るのを禁じただけでなく、国内の学校においては「有名なる論説及び学校読本を読むを禁じ」、さらには「学校の生徒は兵学校の生徒」と見なしたニコライ一世治下の政治を「未曽有(みぞう)の専制」と断じ、このような結果、「人民も政府も共に狼狽して方向に迷う者」の如くになったと批判したのである。
実際、ロシアは「富国強兵」策によって強国となり、貴族の富は増大したものの、それに反比例する形で民衆、ことに農民の「奴隷化」が進んだのである。しかも、ロシアの文部大臣となったウヴア一口フは、西欧化の流れの中で若者にも影響力をもち始めていた「自由・平等・友愛」という理念に対抗するために、「ロシアにだけ属する原理を見いだすことが必要」と考えて、「わが皇帝の尊厳に満ちた至高の叡慮によれば、国民の教育は、正教と専制と国民性の統合した精神においてなされるべきである」とし、国民にたいしてこの理念の遵守を求めた通達を一八三三年に出した。しかし、国内の劣悪な政治状況を放置したまま「為政者」にではなく「国民」に「道徳」を課し、これを批判する者を厳しく罰したこの理念は、ロシアにおける「欧化と国粋」の対立の激化を招いたのである*3。
ドストエフスキーが生涯敬愛し続けたプーシキンは、このようなロシアの二重性を叙事詩『青銅の騎士』(一八三三)において見事に描き出していた。すなわち、この作品の主人公である若い官吏エヴゲーニイは、ペテルブルグを襲った大洪水で最愛の婚約者を失った悲しみから茫然として街をさまよい、ついにはピョートル大帝の「青銅の騎士」像に追いかけられるという強迫観念に駆られて狂死したのである。
ドストエフスキーもフランス二月革命が起きた一八四八年に書いた小説『弱い心』で、最愛の娘との婚約にまでこぎつけた主人公の若い官吏が、有頂天になって仕事に手が着かず、「職務不履行のために兵隊にやられる」のではないかと恐れて「発狂」するという悲劇を描いた。こうして、農奴制の改革などを求めて、ペトラシェーフスキイの会に参加していたドストエフスキーは、佳作『白夜』の発表から間もなく捕らえられて刑が決まるまでの約八か月、サンクト・ぺテルブルクの中心部に位置したペトロパヴロフク要塞の独房に監禁されたのである。
司馬は「私はいまでもときに、暗い戦車の中でうずくまっている自分の姿を夢にみる」と書いていた(「石鳥居の垢」『歴史と視点』)。ドストエフスキーもまた、いつ看守が死刑を告げにくるかも知れぬ暗い独房の中で、「うずくまっている自分の姿を夢に」見てうなされたことであろう。そして、そのような閉ざされた空間の中で、「ロシアとかいうものは何かということ」を考え込んでいるうちに、彼が見たのはピヨートル大帝によって造られた壮麗な都市サンクト・ぺテルブルクが「音をたてて崩れ」、もとの沼地に戻るという光景だったのではないだろうか。
年譜の作成者は司馬遼太郎が学生時代には『史記』だけでなく、ロシア文学を耽読していたことも記している。司馬遼太郎がドストエフスキーに言及している箇所はそれはど多くはないが、以下に詳しく見るように、言及されている箇所は司馬の「作風」や文明観の変化にも係わる重要な役割を担っているのである。本稿ではドストエフスキーが青春を過ごしたニコライ一世の「暗黒の三〇年」と、司馬が「別国」と呼んだ昭和初期の類似性に注目しながら、司馬のロシア観の変化を追うことによって、ドストエフスキーヘの言及の意味に迫りたい。

二、日露戦争の考察と近代化の問題点の認識
日露戦争を中心に措いた『坂の上の雲』の初期においては、司馬は「憲法」を持たなかったことから未曽有の大混乱となりついには革命に至ったロシアと、アジアで最初に「憲法」を持つようになった民主的な国家日本を比較しながら、祖国の防衛戦争として日露戦争を位置づけて、その意義を強調していた。
たとえば、司馬は福沢と共に「当時の西ヨーロッパ人からみれば半開国にひとしかった」ロシアの「文明開化」を行ったピョートル大帝の改革を高く評価し、彼が使節団を西欧に派遣したり「ひげをはやしている者には課税」するなど岩倉使節団や断髪令など日本の明治維新に先行して「つぎつぎに改革と西欧化を断行した」ことを指摘している(Ⅱ・「列強」)。その一方で司馬は、民衆には将校になる可能性がほとんどなかったニコライ一世治下のロシアと比較しながら、「日本ではいかなる階層でも、一定の学校試験にさえ合格できれば平等に将校になれる通がひらかれている」明治の新しい教育制度のよさに注意を向けている(Ⅰ・「七変人」)。
この時、司馬は主人公の一人である秋山好古が福沢諭吉を尊敬していたことを強調することによって、自由民権運動や教育における福沢の意義に注意を促していたが、ロシアを「野蛮」とする見方は、福沢諭吉が『民情一新』において示したロシア観とも重なるものだったのである。だが、このような日露観は日露戦争という悲劇的な形で現れた日本とロシアという二つの強国の接触を、雄大な構想のもとに具体的な事実を丁寧に調べ直しながら描いていた『坂の上の雲』を書く中で次第に変化していく。たとえば、第四巻のあとがきには「当時の日本人というものの能力を考えてみたいというのがこの作品の主題だが、こういう主題ではやはり小説になりにくい」と記され、その理由としてこのような小説は「事実に拘束される」が、「官修の『日露戦史』においてすべて都合のわるいことは隠蔽」されていることが挙げられている(Ⅷ・「あとがき四」)。事実に対する「冷厳な感覚」によって日露戦争の実態を綿密に調べながら書くことによって、彼は日本の近代化の問題点についての理解も深めていくのである。
たとえば、第五巻でロシア側が都市を要塞化して守っていた旅順攻防の悲惨な戦いを描く中でクリミア戦争に言及した司馬は、二十七歳の時にクリミア戦争に「下級将校として従軍」していたトルストイがロシア要塞の攻防を描いた小説『セヴァストーポリ』を「籠城の陣地」で描いていたことに言及している。そして、トルストイがそこで「愛国と英雄的行動についての感動をあふれさせつつも、戦争というこの殺戦だけに価値を置く人類の巨大な衝動について痛酷なまでののろいの声をあげている」ことに注目している(Ⅴ「水師営」)。
こうして、日露戦争における旅順の攻防とクリミア戦争のセヴァストーポリの攻防との類似性に気づいた司馬は、日露戦争以降に顕著になった「時世時節の価値観が事実に対する万能の判定者になり、都合のわるい事実を消す」という傾向を指摘し、日露戦争の戦史が事実を伝えていない事が多いことに触れて、「日本人は、事実を事実として残すという冷厳な感覚にかけているのだろうか」という深いため息にも似た言葉をも記すようになるのである(「『坂の上の雲』を書き終えて」『歴史の中の日本』)。
この時司馬は、「祖国戦争」によってヨーロッパの大国・フランスに対する勝利を奇跡的に収めた後では、ヨーロッパ文明に対するそれまでの劣等感の反発から「自国」を神国化する「国粋」的な思想が広がったロシアと、強国ロシアを破って日露戦争に勝利した後の「明治国家」との間にある類似性に気づいたと言えよう。
この意味で興味深いのは、木下豊房が「空想家の系譜――ネフスキー大通りから地下室へ」において、「空想家に特有のロマン主義的現実離脱の願望が、時代閉塞状況での『弱き心』から生まれることをいみじくも指摘したのは、石川啄木であるが、ニコライ一世の専制体制下と明治絶対天皇制下に類似する精神的閉塞の状況において、ドストエフスキーと啄木のエッセイに次のような似通った記述が見られるのは興味深い」と指摘していることである。*6すなわち、ドストエフスキーは一八四七年のフェリエトン「ぺテルブルグ年代記」において、「二人の親しいぺテルブルグ人がどこかで出会って、挨拶を交わしたあと、『声を合わせたように、何か新しいことはないか? とたずねると、どんな声の調子で会話が始まったにせよ、しみいるような憂鬱な気分が感じられる』」と書いていた。石川啄木も一九一〇年に起きた大逆事件の頃にエッセイ「硝子窓」で、その頃、若い人々の間で、「何か面白いことは無いかねえ」がはやり言葉になり、「“無いねえ”、“無いねえ″、そういって口を噤むと、何がなしに焦々した不愉快な気持ちが滓(かす)のように残る」と書いていたのである。
比較文明学の視点からロシアと日本の近代化を比較した山本新は、「一〇〇年以上の距離をおいて二つの文明のあいだに並行現象がおこっている」と分析していた*7。司馬遼太郎も『坂の上の雲』を書き終えた後では、「自分たちは西のほうに行けばロシア人だといってばかにされるけれど、東に行けば自分たちは西洋人でもある」とドストエフスキーが言っていたはずだと先のエッセイで書いている。この時、司馬遷太郎は強い近代化(欧化) への圧力の中でロシアの知識人もまた、「拝外と排外」という心理の揺れを持っていたことを認識したのであり、名誉白人であることを望む日本人の心理にもロシア人の場合と同じような「欧化と国粋」のねじれがあることに気付いたと思える*8。
三、「父親殺し」のテーマと昭和初期の「別国」視
このことに注目する時、司馬遼太郎の「作風の変化」が、実は、日露文明の比較の深まりや「近代化」の問題点の認識と対応していることに気づく。たとえば、日露の衝突を防いだ商人高田屋嘉兵衛を主人公としつつ、江戸時代の文化的な成熟度の高さを丹念に描いた『菜の花の沖』において司馬は、「『国家』という巨大な組織は、近代が近づくにつれていよいよばけもののように非人間的なものになってゆく。とくに、国家間が緊張したとき、相手国への猜疑と過剰な自国防衛意識」が起きるだけでなく、「さらには双方の国が国民を煽る敵愾心の宣伝といった奇怪な国家心理」も働くと鋭く指摘するのである。つまり、司馬遼太郎は「欧化と国粋」のサイクルの問題を踏まえた上で、それを乗り越え多様性を許容するような新たな文明のあり方を考察していたと言えよう。
沼野充義は司馬遼太郎のロシア観について、「それは自由で因習に捕らわれない発想に満ちていながら、深い学識に裏打ちされて」いるとし、『ロシアについて - 北方の原形』を「ロシアの専門家には決して書けないような種類の非常に優れたロシア論であることは、確かである」と結んでいるが、それは決して誉めすぎではないのである*9。
注目したいのは、『菜の花の沖』の中の嘉兵衛がロシア人に捕らえられるきっかけとなったゴロヴニーンの日本での抑留のエピソードをめぐる考察の中で、司馬がドストエフスキーに言及していることである。この抑留という状態について司馬は、「被抑留者の精神はそれを味わったものでしかわからない。『生命』というものを相手ににぎられてしまっているのである」と説明し、このような中で、一人の青年士官が「監禁と死の恐怖」から精神に異常をきたしたことを伝えて、「幽囚が、人間としていかに耐えがたいものであるかが、この一事でもわかる」と解説している。それは「戦車」の中に閉じこめられて死を待っていた司馬自身や「独房」の中にいたドストエフスキーにも通じることだろう。
この後、司馬はこの青年士官の変節についてゴロヴニーンがくわしく書いた文章にふれて、そこには「すこしの攻撃的なにおいもないばかりか」、若者の弱さに対する「理解といたわりがあった」ことに注目し、「背信に対し、相手を人間として理解すべく努めようとする知的寛容さは、…中略…近代が生んだ精神といっていい」とし、「この時代、ロシアの知識階級にはすでに『近代』があったということをあざやかに思うべきである」と記している。そして、司馬はこの十年後に、「人間の心理の中の質と相剋をつきつめた」ドストエフスキーが生まれていることに注意を喚起している(Ⅴ・「カムチャツカ」)。こうして新しい視野を得た後で司馬は、心理的なタブーを克服して醜い現実をも直視できるようになったドストエフスキーの作品を高く評価するのである。
この意味で注目したいのは、一九三九年のノモンハン事件を主題にした長編小説をも描こうとして膨大な資料類を集めていた司馬が、「戦闘というより一方的虐殺」となった、「ばかばかしい戦闘を現場でやらせられた」、「有能な指揮官」が発狂したことを怒りをこめて書き記していることである(「戦車・この憂鬱な乗り物」『歴史と視点』)。
実は、このような発狂の可能性は戦車中隊の指揮官であった司馬自身にもあった。すなわち、司馬は終戦間際にアメリカ軍との本土決戦のために満州から引き揚げて北関東に配置されたが、そこで敵の邀撃(ようげき)作戦などを説明するために大本営から来た将校は、「東京方面から大八車などに家財道具を積んで逃げてくる物凄い人数の人々をどのように交通整理するのか」との問いに対して、「昂然と、『轢っ殺してゆけ』と、いった」のである。司馬は「国家」のために死を覚悟したが、ここでは民衆を守るはずの「国家」が「同じ国民」を殺すことを命じたのである。
この言葉を聞いた瞬間、若き司馬遼太郎の脳裡をどのような思いが走ったのだろうか。そして、彼はどのようにしてその思いを耐えたのだろうか。松本健一は「司馬さんが、天皇制イデオロギーにほかならない皇国史観ばかりでなく、五・一五事件や二・二六事件に対する違和感、いや憤りのような感情をいだいていた」と書いている*10。
追記(2022/04/30)、(一方、華族のための学習院の初等科6年生の時に2・26事件と遭遇していた三島由紀夫は『英霊の聲』ではこの事件の「スピリットのみを純粋培養して作品化しようと思った」と記し、青年将校たちの精神を美化していた。
ただ、それは思想や見方の違いだけに帰着するのではなく、年代の差によるところが大きいだろう。司馬と三島の年齢差はわずか二歳であったが、三島が徴兵を免れたのに対して、司馬は満州の戦車隊に徴兵されていたのである。堀田の親友・中村真一郎はそのことについてこう記している。
「私だけの経験で云えば、昭和になってからの十数年は、まことに慌ただしいもので、昭和元年の二十歳と昭和十年の二十歳とでは、殆んど会話が不能であり、いや、昭和十三年に二十歳であった私には、昭和十年に二十歳であった野間宏とも、非常に大きな感覚的な相違が感じられることがある。」(『全集』、解説「同時代者堀田善衞」)
堀田が『若き日の詩人たちの肖像』で詳しく記しているように彼の世代にはすでに体制に批判的な行動を起こすことはできなかったが、まだ批判的に見ることはできた。しかし、それから7年後の三島の時代には「昭和初期の政治的軍人」を批判的に見るような自由も残されていなかったように思える。
「革命思想」の正当性をめぐって内ゲバをくり返していた学生運動を鋭く批判した次の文章はこの時司馬が受けた「絶望」に近い衝撃の大きさを正確に物語っていると思われる。「昭和初期の政治的軍人とそっくりの、つまり没常識・非論理的のなかでこそ大閃光を発するという貧相で陰惨なしかし、であればこそ民族的な深層心理に訴えやすいという日本的ファナティズムが学生運動の分裂のあげくに出てきているようである。幻想と没常識のタイプも酷似しているし、他民族への(学生運動の場合は他の分派への)残忍さまでそっくりである。…中略…それはかつての日本軍が中国人に対して加えたそれとひどく似ているようにおもえて、暗然とした。日本人は地球から消えてしまえと思いたくなったほどだが」(「戦車・この憂鬱な乗り物」『歴史と視点』)。
この文章は、説得力が豊かで穏やかな司馬の普段の文体とは全く異なる。ここで、司馬は論理的な考察を拒絶して、感情的に自分より「次の世代」の学生たちを論じつつ、「日本人」を全否定している。そしてこの時、司馬遼太郎は自分の信じるイデオロギーを唯一の「普遍的な正義」とした学生たちの考えと、「自国」を「神国」と称して太平洋戦争を導くにいたる自分より「前の世代」の国粋主義的な政治的軍人たちとのあいだに明らかな類似性を見ていたのである。
最初、この文章と出会ったとき私は司馬を捉えていた絶望の深さに愕然としたが、何度か読み返す中で、母親や農民たちに対する実の父親の暴虐ぶりに暗澹たる思いをしたであろうドストエフスキーの絶望が重なり合った。卓越した心理描写で読者を驚かせたドストエフスキーが、父親の欠点をも直視しつつ、「父親殺し」のテーマを真正面から描いたのは、ようやく最後の作品『カラマーゾフの兄弟』においてであった。ドストエフスキーにおける「父親殺し」のテーマと比較する時、この文章こそが「司馬史観」の争点の一つとなっている「昭和初期の(別国)」論を解く鍵だとも言えるだろう。
ジラールは父と息子の対立のテーマを分析しながら、「ある意味で父親と息子は同一である」ので、非道な「父親は『他者』として憎まれるが、もっと深いところでは『自己』としての羞恥心の対象」であり、「圧制者=父親に向けられた奴隷=息子の犯罪」といえる「父親殺し」は、「殺人であると同時に自殺」でもあると結論している*11。「父親」の欠点は、父という存在がきわめて大切で身近であり、それらが直接「自分」にもつながっているだけに、それらの欠点が直前に示された場合には、それを論理的に考察するのは精神的につらいので、できれば自分の前から消えて欲しいと願うのであろう。
同じことが、「自分」と「祖国」の関係についてもほぼ当てはまる(ついでながら、ロシア語では「親」と「祖国」の語源は同じである)。つまり、ニコライ治世下のロシアで育ったドストエフスキーは少年の時に「正教、専制、国民性」をロシアの理念として教育されたが、五・一五事件の二年前の一九三〇年に尋常小学校に入学した司馬も「とにかく、あらゆる式の日に非常に重々しい儀式を伴いながら、教育勅語が読まれた」と語っているように、文部省が『国体の本義』を発行して国粋的な教育をいっそう強化していた時代に青少年時代を過ごしたのである。おそらく、子供から青年期の時代に、論理だけでなく感性的なレベルで教育を受けた者にとって、「国家」と「自分」を距離を置いて客観的に考えるのは難しかったのである。
このように見てくる時、ドストエフスキーが「父親殺し」を直接のテーマとして描くには、多くの歳月を必要としたが、昭和前期を司馬が『十数年の“別国″』と見なしたのも、「日本人」全体を否定したくなるような衝動や深い絶望を抑えるための、一種の『仮構』だったと言っても過言ではないように思える。
四、「教育勅語」と「ウヴァ一ロフの通達」
福沢諭吉は日本の「文明開化」のモデルの一つがピョートル大帝のロシアであることを十分に知っていたが、『坂の上の雲』を書き終えた後での司馬遼太郎の認識の深さは、日露戦争に勝って「神州不滅」を唱えるようになる日本の近代化が、ニコライ一世の独裁制をモデルにしていたことを明らかにしていることである。
たとえば、司馬遼太郎は山県有朋にとって、「国家的象徴に重厚な装飾を加える」ことが「終生のテーマだった」とし、その理由を「ニコライ二世の戴冠式に、使節として出席し」て、「ギリシア正教で装飾された」、「戴冠式の荘厳さ」を見た彼が、強いショックを受けたからであると説明している(「竜馬像の変遷」『歴史の中の日本』)。
しかも司馬は、「教育勅語」はその意味が分かりにくかったが、それは文章が「日本語というよりも漢文」だったためとして、この「勅語」が形式的にはかつての「文明国」中国をモデルとすることで権威付けされていたことを明らかにしていた(「教育勅語と明治憲法」『語る日本』)。実際、西村茂樹は「修身書勅撰に関する記録」において、清朝の皇帝が「聖諭広訓を作りて全国に施行せし例に倣い」(太字引用者)、我が国でも「勅撰を以て」、「修身の課業書を作らしめ」るべきだと記していたのである。
さらに、「教育勅語」の執筆者の一人である元田永孚は「国教大教」において、「天皇は全国治教の権を統べられること」を強調していたが、西村茂樹も「修身書勅撰に関する記録」の冒頭で「西洋の諸国が昔より耶蘇教を以て国民の道徳を維持し来れるは、世人の皆知る所なり」とし、ことにロシアでは形式的には皇帝と総主教に分かれてはいるが、実質的には、「其国の皇帝と宗教の大教主とを一人」で兼ねており、それゆえ「国民の其の皇帝に信服すること甚深く世界無双の大国も今日なお君主独裁を以て其政治を行えるは、皇帝が政治と宗教との大権を一身に聚めたるより出たるもの亦多し」と述べた*12。こうして彼は、我が国でも「皇室を以て道徳の源となし、普通教育中に於て、其徳育に関することは 皇室自ら是を管理」すべきであると説いたのである。この箇所は日本における「修身教育」の実質的なモデルが、ロシアの国教である正教への信仰と、皇帝への忠誠心を持つことを徹底させたロシアの教育制度であったことを物語っているだろう。
しかも、司馬遼太郎が中学に入学した翌年の一九三七年には文部省から『国体の本義』が発行されたが、「国体の本義解説叢書」の一冊として出版された『我が風土・国民性と文学』と題する小冊子では、「敬神・忠君・愛国の三精神が一になっていることは」、「日本の国体の精華であって、万国に類例が無い」と強調されていた*13。それは「正教・専制・国民性」 の「三位一体」こそが、「ロシアの理念」であるとした文部大臣「ウヴァ一口フの通達」を連想させるのである。
この意味で注目したいのは、司馬が『若き日の詩人たちの肖像』の著者である堀田善衞や宮崎駿との鼎談を一九九二年に行っていることである。堀田善衞はこの長編小説において、上京した日に二・二六事件に遭遇した主人公の若者が、ラジオから聞こえてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から受けた衝撃と比較しながら、厳しい言論弾圧と迫り来る戦争の重圧の中で描かれた『白夜』(一八四八年)の冒頭の美しい文章に何度も言及していた。しかもこの作品で堀田は、ドストエフスキーの作品の鋭い分析を行うとともに、厳しい検閲制度や監視のもとに時勢が「右傾化」する中でドストエフスキーの読み方を変えていった愛読者の姿や、烈しい拷問によって苦しんだいわゆる「左翼」の若者たちや、イデオロギー的には異なりながらも彼らに共感を示して「言論の自由」のために文筆活動を行っていた主人公の若者の姿をとおして、昭和初期の暗い時代を活き活きと描いていたのである*14。
このような堀田の作品理解を踏まえて司馬は、芥川龍之介が自殺した後で中野重治など同人雑誌『驢馬』に係わっていた同人たちが「ほぼ、全員、左翼になった」と指摘している*15。そして、司馬は「後世の人たち」は「その理由がよくわからないでしょう」が、「私は年代がさがるので一度もなったことはないけれども」と断りつつも、「昭和初年、多くの知識青年が左翼になった」「そういう時代があったということは、これはみんな記憶しなければいけない」と続けていたのである*16。こうして昭和初期の検閲の厳しく暗い「別国」の時代に青春を過ごした司馬の言葉は、「ロシアの教育勅語」ともいわれる「ロシアの理念」が打ち出されて、自由思想すらも厳しく規制されていたニコライ一世の「暗黒の三〇年」の時期に、なぜドストエフスキーがペトラシェーフスキイ事件に関与するようになったのかをも説明し得ているであろう。
つまり、言論や集会の自由が奪われて厳しい監視下におかれ、自国の欠点に対する批判も禁じられていた日露両国においては、「出口」が見いだせないなかで、ドストエフスキーや堀田善衞のように感受性豊かな青年たちが、極端な「国粋思想」に対する反発から新しい「原理」を示した「左翼」に共感を示すようになったのである。
たとえば、立花隆は「私の東大論」において、「日本中を右傾化させた」事件として、一九三二年(昭和七年)の五・一五重件と神兵隊事件を挙げるとともに、「ほとんどこの事件と重なるようにして」、滝川幸辰教授に辞職を求めた文部大臣に対して、京都帝国大学法学部の教授全員だけでなく助教授から副手にいたる三九名も辞表を提出し抗議した、いわゆる滝川事件が起きていたことを指摘している。そして立花はこの時の辞任要求の真の理由は滝川教授が治安維持法に対して「最も果敢に闘った法学者だった」ためではないかという説を展開している*17。すなわち、治安維持法は一九二五年(大正一四年)に制定されたが、同じ年に全国の高校や大学で軍事教練が行われるようになると、これに対する反発から全国の高校や大学で反対同盟が生まれて「社研」へと発展したが、文部省は命令により高校の社研を解散させるとともに、「学問の自由」で守られていた大学の「社研」に対しては、治安維持法を最初に運用して一斉検挙を行ったのである。しかもこの京都学連事件では、後に著名な文化人類学者となる石田英一郎は、治安維持法への違反が咎められただけでなく、中学時代の日記に天長節で「教育勅語」を読み上げ最敬礼させることへの批判が書かれていたとして不敬罪にも問われていたのである*18。
こうして、司馬が青春を過ごした昭和初期は、外国の書物の輸入が禁止されたばかりでなく、国内での検閲も強まり学校でも軍事教練が行われるなど、福沢諭吉が「野蛮」と見なして厳しく批判したニコライ一世の「暗黒の三〇年」ときわめて似た政治状況に陥っていたのである。
晩年の『風塵抄』で司馬は、「健全財政の守り手たちはつぎつぎに右翼テロによって狙撃された。昭和五年には浜口雄幸首相、同七年には犬養毅首相、同十一年には大蔵大臣高橋是清が殺された」と記し、「あとは、軍閥という虚喝集団が支配する世になり、日本は亡国への坂をころがる」と厳しく批判した(『風塵抄』Ⅱ)。
五,「大地主義」と「『公』としての地球」→「人類滅亡の悪夢」とその克服
堀場正夫は真珠湾攻撃の翌年に出版された『英雄と祭典』において、『罪と罰』を「『ヨーロッパ近代の理知の歴史』とその『受難者』ラスコーリニコフの物語」ととらえ、「大東亜戦争を、西欧的近代の超克への聖戦」と見なした。むろん、このような読みは現在のレベルでの研究を踏まえた上での読みから見れば、明らかな「誤読」であると言える。
(移動)ドストエフスキーはこの長編小説において、「近代的な知」に囚(とら)われて自分をナポレオンと同じ様な「非凡人」と考え、自分が「悪人」とみなした「他者の殺人」をも正当化したラスコーリニコフの悲劇を描き出すとともに、そのエピローグではシベリアの流刑地で「人類滅亡」の悪夢を見させることにより、自己中心的な「非凡人の思想」が、自国中心的な「国民国家」史観に基づいていることを示唆して、「自国の正義」や「報復の権利」を主張して、限りなく大規模化する近代戦争の危険性を明らかにした。そして、エピローグでは主人公をぺテルブルクから遠く離れたシベリアの大地で暮らさせることにより、森や泉の尊さや民衆の「英知」にも気づいた彼の「復活」を描き出して、「自然支配」の思想との決別をも描いていたのである*20。
しかし、堀場正夫の「誤読」には、時代的な背景もあった。ニーチェによるドストエフスキー理解を踏まえたシェストフは、ドストエフスキーをも「超人思想」の提唱者であり、「悲劇の哲学」 の創始者の一人とした。このようなシェストフの解釈が日本でも受け入れられる中で、優れた批評家であった小林秀雄ですらも、『罪と罰』のエピローグではラスコーリニコフは影のような存在になっていると指摘して、書かれている彼の更生を否定していた*21。それは「近代人が近代に勝つのは近代によってである」とした彼の近代観から導かれたものでもあった*22。
一方、司馬遼太郎は真珠湾攻撃の後で「近代の超克」を謳って河上徹太郎や小林秀雄など日本の一流の知識人が行い、この「当時の読者に大きな衝撃を与えた」座談会について、当時は「読みはしたものの難しかった」ので、「よくわからなかった」と認めた。そして、彼は現在読み返してみると「基本的におかしなことは」、「ここでいう超克すべき近代というのは、要するにヨーロッパの近代」であり、当時の一流の知識人たちが江戸時代に培われた日本の文化的伝統をまったく無視していると指摘している。こうして司馬は、「ヨーロッパの近代に対して、太平洋戦争の開幕のときの不意打ち成功によって、日本のインテリは溜飲を下げた」が、「それは嘘の下がり方なんですよ」と厳しく批判したのである(「買い続けた西欧近代」『「昭和」という国家』)。
この時司馬は「西欧派とスラヴ派」の激しい対立にゆれた近代ロシアにおいて、「大地主義」の視点から「西欧派と国粋派」の和解だけでなく、「知識人と民衆」との和解の可能性をも探求した『罪と罰』の意義を理解していたと言えるだろう。つまり、彼が『菜の花の沖』の主人公で、ナポレオンと同じ年に生まれた高田屋嘉兵衛に「好んでいくさを催し、人を害する国は、国政悪しき故」と語らせている背景には、ナポレオン以降の「自国中心」の歴史観を、「自己中心の迷妄」と断じたトインビーと同じような歴史認識があったのである*23。
加筆(2022/04/30)【東京大空襲を体験した後で国際文化振興会の上海資料調査室に赴任した堀田善衞は、広島と長崎に原子爆弾が投下された後には「日本民族も放射能によって次第に絶えて行くのだ」という流言を聞いて、『ヨハネの黙示録』の次のような文章の恐ろしさを実感していた。
「第一の御使(みつかひ)ラッパを吹きしに、血の混りたる雹(へう)と火とありて地にふりくだり、地の三分の一焼け失せ、樹(き)の三分の一、焼け失せ、もろもろの青草(あをくさ)焼け失せたり」という記述のある進めて行って、「ほんとうに身に震えを感じた」と書いている。
この時、堀田は『罪と罰』のエピローグでラスコーリニコフが流刑地のシベリアで見た、「知力と意志を授けられた」「旋毛虫」におかされ自分だけが真理を知っていると思いこんだ人々が、互いに自分の真理を主張して殺し合いを始め、ついには地球上に数名の者しか残らなかったという夢が、単なる悪夢ではなく、現実にも起こりうることを実感したはずである。
実際、「高利貸しの老婆」を悪人と規定して殺害していたラスコーリニコフに対して司法取締官のポルフィーリイは、「あの婆さんを殺しただけですんで、まだよかったですよ。もし別の理論を考えついておられたら、幾億倍も醜悪なことをしておられたかもしれない」とラスコーリニコフに語っていたが、ヒトラーの「非凡民族」という理論は実際にユダヤ人虐殺という醜悪な結果を招いていた。
さらに化学兵器はその非人道性ゆえに禁止されたが、広島と長崎に投下された原子爆弾の悲惨さが隠蔽されたために、原水爆は禁止されなかったためにその実験でも多大の被害を生み出し、それはチェルノブイリ原発事故と福島第一原子力発電所の事故にもつながった。】
一方司馬は、「地面を投機の対象にして物狂い」をした現象に対しては、「日本国の国土は、国民が拠って立ってきた地面なのである」とし、「大地」に対する哲学的な見方の変革を求め、「でなければ、日本国に明日はない」と書いた(『風塵抄』Ⅱ)。さらに、「樹木と人」という講演で司馬は、「ソ連のチェルノブイリの原子炉」の事故で「死の灰が各地で降って大騒ぎ」になったことにふれて、「この事件は大気というものは地球を漂流していて、人類は一つである、一つの大気を共有している。さらにいえばその生命は他の生物と同様、もろいものだという思想を全世界に広く与えたと思います」と語り、言葉を続けて一九八〇年代になって、「ようやく、われわれは地球の緑をすべて守らなければいけない、切ったら必ず植えなければいけない、そして生態系を変えるような切り方はしてはいけない」ことに気づいたのだと強調した(「樹木と人」『十六の話』)。
しかも、ロシア帝国の貴族たちと日本の高級官僚との類似を意識しながら司馬は、日露戦争のあとで「教育機関と試験制度による人間が、あらゆる分野を占めた」が、「官僚であれ軍人であれ」、「それぞれのヒエラルキーの上層を占めるべく約束されていた」彼らは、「かつて培われたものから切り離されたひとびとで」あり、「わが身ひとつの出世ということが軸になっていた」とした(「あとがき」『ロシアについて』)。それはロシアの大地から遊離したロシアの知識人に対するドストエフスキーの鋭い批判とも重なり合うのである。そして司馬は、これらの官僚や軍人たちは「自分たちが愛国者だと思っていた。さらには、愛国というものは、国家を他国に対し、狡猾に立ちまわらせるものだと信じていた」とし、「それを支持したり、煽動したりする言論人の場合も、そうだった」と厳しく批判したのである。
さらに、ノモンハン事件の研究者クックは、戦前の日本では、国家があれほどの無茶をやっているのに、国民は「羊飼いの後に黙々と従う」羊だったではありませんかと司馬に問い質したが、この指摘の正しさを認めた司馬も、大蔵省のかけ声のもとに国民がこぞって金儲けに走った問題にふれて、「日本は、いま世界でいちばん住みにくい国になっています。そのことを、ほとんどの人が感じ始めている。『ノモンハン』が続いているのでしょうな」と続けた(「ノモンハンの尻尾」『東と西』)。
加筆(2022/04/30)【「司馬史観」論争では司馬が右派の思想家とされてしまったために、残念ながら司馬の言説は説得力を大きく失った。しかし、すでに『竜馬がゆく』(文春文庫)で幕末の「神国思想」が「国定国史教科書の史観」となったと指摘した司馬遼太郎は、「その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」と記していた。
そして司馬は、晩年の『この国のかたち』(第五巻)でも、「キリスト教に似た天地創造の世界を展開した」平田篤胤によって、「別国が湧出したのである」と続けていた。
「昭和別国」という特徴的な用語を使っていた司馬氏がここでも「別国」と記していることは、堀田善衞が『若き日の詩人たちの肖像』に記した堀田善衞の平田篤胤批判に通じると思われるのである。】
こうして司馬は、「国際化」に対応するために個性の尊重を謳いながら、多発するようになった青少年犯罪を「行きすぎた欧化」のせいであるとして、「権威」や「国家」への「服従」を求める「国粋」的な傾向を強めている教育のもとで、日本の国民は再び「従順な羊」になり始めているのではないかという深刻な不安を示したのである。
実際、自国の「国益」を優先しつつ、グローバリゼーションを押し進めるアメリカ政府に対する反撥から、世界では各国においてナショナリズムが野火のような広がりを見せつつある。このように見てくる時、日露の「文明開化」の比較をとおして、「欧化と国粋」のサイクルの危険性を認識し、「自国の正義」を主張して「野蛮」と規定した「他国」の征伐を正当化するような歴史観を鋭く批判した司馬遼太郎の文明観とその意義は、改めて見直されるべきであろう。
注
*1 司馬遼太郎・井上ひさし「普遍性なき『絶対主義』」『国家・宗教・日本人』
*2 本稿においては、司馬遼太郎の作品は、章と作品名、および巻数をローマ数字で本文中に示す
*3 高橋誠一郎『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房、二〇〇二年、四八~五三頁参照
*4 山野博史編「司馬遼太郎の七二年」『司馬遼太郎の跫音』中公文庫、一九九八年、六九二頁
*5 中島誠(文)、清重仲之(イラスト)『司馬遷太郎と「坂の上の雲」』現代書館、二〇〇二年参照
*6 木下豊房『ドストエフスキー その対話的世界』成文社、二〇〇二年、八九~九〇頁)
*7 山本新著、神川正彦・吉澤五郎編『周辺文明論――欧化と土着』刀水書房、
*8 高橋誠一郎『この国のあした――司馬遼太郎の戦争観』のべる出版企画、二〇〇二年、第二章参照
*9 沼野充義「司馬遷太郎とロシア」『大航海』No.13、一九九六年、六九頁
*10 松本健一『司馬遼太郎 歴史は文学の華なり、と』小沢書店、一九九六年、三八頁
*11 ルネ・ジンラール、鈴木晶訳『ドストエフスキー二重性から単一性へ』法政大学出版局、一九八三年、前掲訳書、一二二~三頁
*12 西村茂樹「修身書勅撰に関する記録」『教育に関する勅語換発五〇年記念資料展覧図録』(教学局編纂)、昭和一六年、一〇〇頁。
*13 教学局編纂『我が風土・国民性と文学』(国体の本義解説叢書)、昭和一三年、六一頁
*14 堀田善衞『若き日の詩人たちの肖像』新潮社、一九六八年(集英社文庫、一九七七年)参照
*15 司馬遼太郎・堀田善衞・宮崎駿『時代の風音』朝日文芸文庫、一九九七年、四二~四四頁
*16 この時代のドストエフスキーをめぐる日本の状況については、池田和彦「詩人たちのドストエフスキイ」『ドストエーフスキイ広場』第一一号、および菅原純子「『広
場』合評会報告」「読書会通信」七五~七七号参照
*17 立花隆「私の東大論」『文藝春秋』二〇〇二年九月号~一一月号
*18 同右、『文藝春秋』二〇〇二年一一月号、三七二~三七九員
*19 松本健一『ドストエフスキーと日本人』朝日新聞社、昭和五〇年、一五頁
*20 高橋『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』刀水書房、二〇〇〇年、第九章「鬼」としての他者、および第一〇章「他者としての自然」参照
*21 小林秀雄『ドストエフスキイ』講談社、昭和四一年、二七五頁
*22 河上徹太郎、竹内好他『近代の超克』富山房百科文庫、昭和五四年、二四七頁。なお、小林秀雄の戦争観については、森本淳生『小林秀雄の論理――美と戦争』人文書院、二〇〇二年参照
*23 トインビー、長谷川松治訳『歴史の研究』第二巻、社会思想社、昭和四二年、七五~六頁
『ドストエーフスキイ広場』第一一号